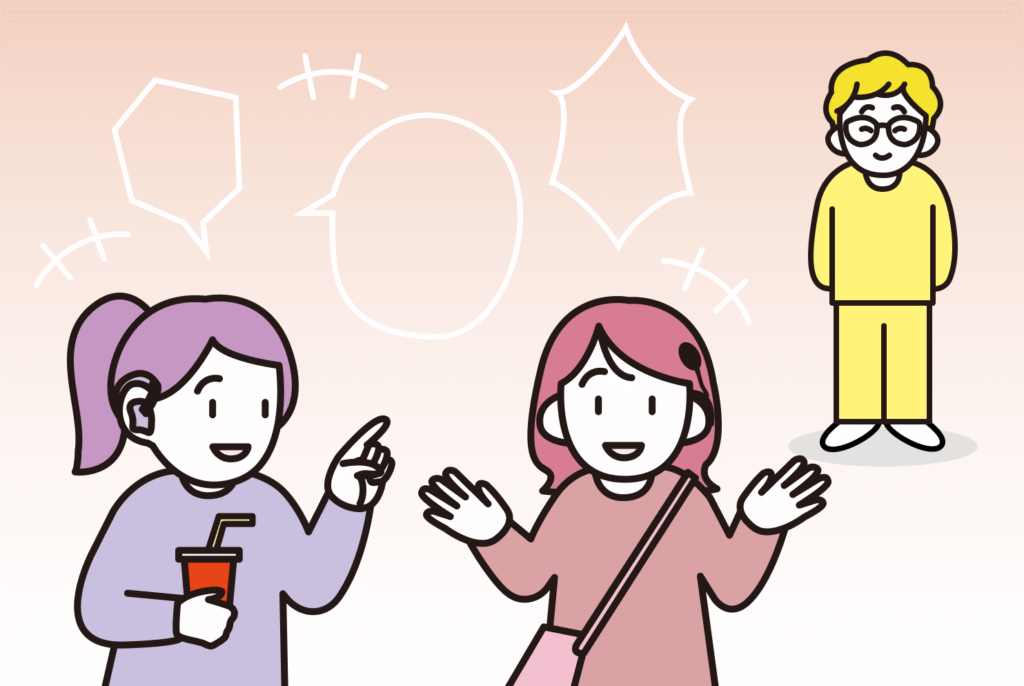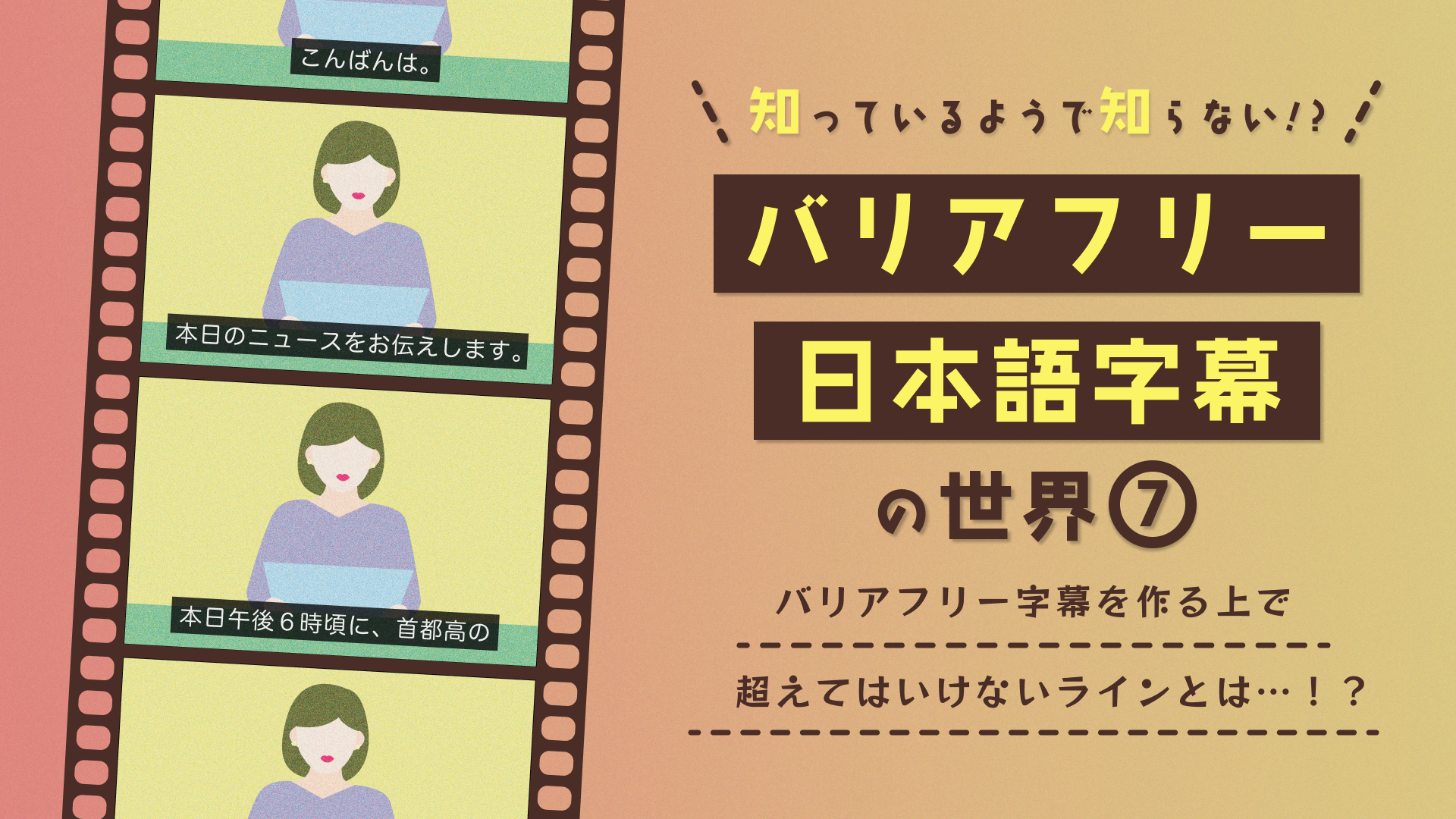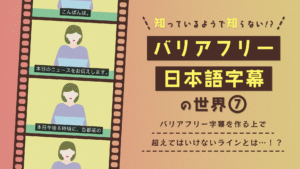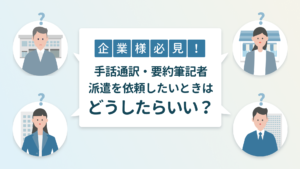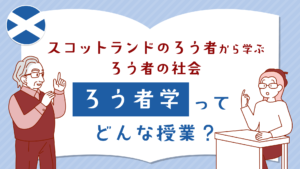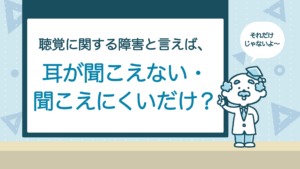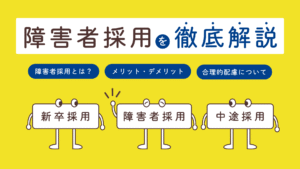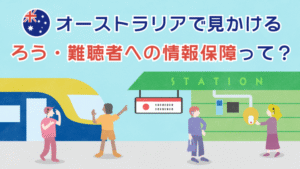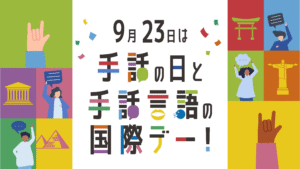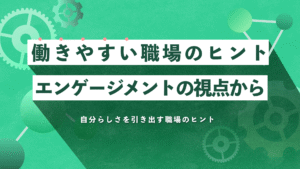字幕をつける仕事をしていると、いろんな作品に出会います。
ときには、どこに気持ちを添えればいいのか少し迷う作品も…
しかし、そんな時ほど私は、ひとつの問いを抱えるのです。
「本当に、何も伝えたいことはなかったのだろうか?」
やっぱり、どの作品にもどこかに“何か”がある気がして——。
これは、私が密かに大切にしていることの話です。
「つまらない」をつくる仕事?
映画を観ていて、「うーん、正直あんまり面白くなかったな……」と思ったこと、ありませんか?
たとえば展開が読めすぎて、感情がついていかない。
セリフのリズムもどこかぎこちなくて、いつのまにか終わっていたり、眠ってしまっていたり。
どんなに有名な作品でも、誰にでもそういう体験は一度や二度はあると思います。
そして私は、そんな作品に字幕をつけることがあります。
職業柄、観客よりも少し早く作品を観て、言葉を聞き取り、字幕を制作します。
そんな時、ふと、こんなことを思うことがあります。
「……この作品、面白くないなあ」
もちろん、そういう時でも作品に誠実であろうとします。しかし、正直な感想として湧いてしまうのです。
そしてその度に、少し申し訳なさのような気持ちになります。
なぜなら、その「つまらない」体験が、私の字幕を通して誰かに伝わってしまうのではないかと、どこかで思ってしまうからです。
ある時、とある監修者にこう言われました。
「面白くない作品は、面白くないって思ってもらって構わない。その責任は、作品を作った人たちにある。私たちは、作品を変えずに伝える。それだけのこと。」
その言葉は、たしかに私の気持ちを少し楽にしてくれました。
「そうか、私が全部を背負う必要はないんだ」と。
けれども、同時に心のどこかがザワザワしました。それって本当に割り切っていいことなんだろうか?
作り手にはきっと、何かを伝えたくてこの作品を作った気持ちがあるはず。
それを、ただ「つまらなかった」という私個人の感想で片づけてしまっていいのか。
その葛藤は、今でも私の中で燻り続けています。
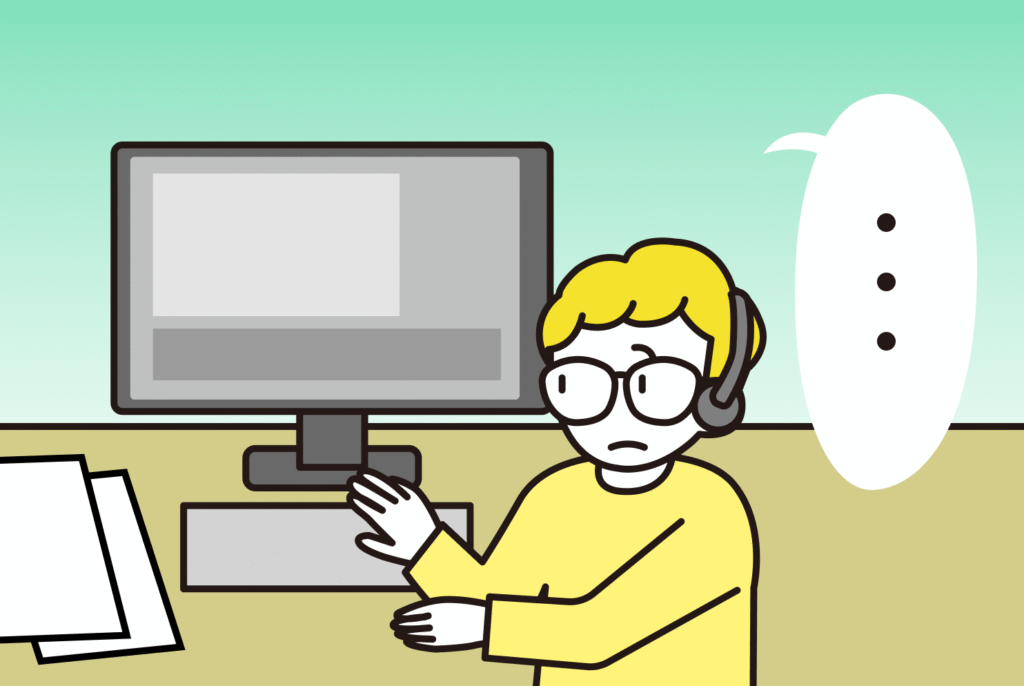
面白く“しない”覚悟
バリアフリー字幕には、絶対に越えてはいけないラインがあります。「作品を操作してはいけない」ということです。
これは法に触れてしまう恐れのある、とても大変なことなのです。
字幕をつける側が、「この作品ちょっと退屈だから、観客の笑っている音情報を足して盛り上げておこう」とか、「このセリフ、こっちの区切り方がかっこよくなるから…」と作品や作風を変えてしまうことはしてはいけません。
たとえ、ウケそうな“良い言い回し”の区切り方を思いついても、そこに字幕制作者の脚色が入ってしまったら、もうそれは“その作品”ではなくなってしまうからです。
たとえば、作中の登場人物がギャグを言って、劇中の空気が静まり返ったとします。
それは“ウケていない”ことが演出上の意味を持っているのかもしれませんし、笑っている観客がいてもあえて字幕化不要にすることで、観客自身がそのギャグにどう反応するかを自由に委ねられているのかもしれません。
しかしそこに「(笑い声)」や「(観客のざわつく声)」などと字幕で補足してしまったら、その“自由に委ねられているはずの空気”を決めつけてしまうことになります。(逆も然り)
これは音声ガイドにも共通するポイントですが、「説明しすぎることの暴力性」は映像表現の中ではとても繊細な問題です。
見えて・聞こえる人にとっては当たり前すぎて説明されない“空気”や“間”が、見えない・見えにくい人や聞こえない・聞こえにくい人には届きにくいからといって、安易に字幕や音声ガイドの「言葉」で埋めてしまえばいいわけではないのです。
だからこそ、過剰に補わず、ただそこで“鳴っていた音”や“流れていた気配”を、ありのままに伝えるようにします。
それは、“面白くする”こととは違います。“面白さを伝える”こととも、また違うかもしれません。
私たちは「面白い」という感情そのものではなく、その作品の中に“面白さを感じ取る余地があること”を、きちんと伝え・選択してもらいたいのです。
たとえその作品が、誰かにとって「つまらない」と感じられるものであっても。
それでも『伝わってほしい』と願ってしまう
操作してはいけない。盛ってはいけない。
だから、つまらない作品は、つまらないままに字幕をつける――。
頭では、よくわかっています。それがプロの仕事だとも思います。
けれども、心のどこかで私はどうしても願ってしまうのです。
「せめて、何か一つでも、伝わってくれたらいいのに」と。
セリフの中に一瞬だけ、ふとした本音が垣間見えるようなとき。
決して派手ではないけれど、俳優の吐く息や吸う息、そして間(ま)。
画面の奥で流れている音楽がシーンとリンクしているとき。
――そういう“細部”にこそ、作り手の真剣さが宿っていることがあります。
「もしかしたら、この作品を面白くないって思っているのは私だけかもしれない」そう思うこともあります。
人によっては、同じ作品を「めちゃくちゃよかった!」と感じるかもしれない。
その感性の違いを、私はどこまで自覚できているだろうか。そして、自分が感じきれなかった興味深さを、誰かに届けるための糧として本当に作れているのだろうか。
自問するたびに、底なし沼にハマってしまいます(笑)
その“感じきれなさ”の隙間にこそ、耳を澄ませられるようになりたいです。
「たとえ私にはピンとこなくても、この一言には、何か意味があるのかもしれない」そうやって、目をこらし、音を聴き、言葉と向き合い続ける。
すべての作品には、届けようとした誰かの想いがあるから。
私はその想いに寄り添い続けたいです。
全肯定はできなくても、全面的に賛同できなくても、それでも誠実でありたいと思っています。
それは「面白いかどうか」ではなく、「向き合ったかどうか」の問題なのだと思います。だからこそ、私はどんな作品に対しても、一度はちゃんと立ち止まりたいのです。
「本当に、何も伝えたいことはなかったんだろうか?」
そう問いかけることが、私にとっての字幕制作の責任であり、倫理なのだと思うようになりました。
字幕をつける
作品が「面白い」か「つまらない」か。その評価は、私の仕事の指針ではありません。
私が向き合っているのは、もっと別の場所にあるものです。
できる限り、“そこにあったもの”を“そこにあるまま”届けること。
それがバリアフリー字幕の役割であり、私自身が密かに信じているこの仕事の本質です。
たとえ、その先で「つまらなかった」と思われたとしても、その“つまらなさ”さえ自分の目で確かめられるような字幕であってほしい。
それが、「観る」という体験の自由だと、私は思います。
私たち字幕制作者は、作品の作り手ではありません。またこの仕事は、作品の魅力を操作するものではありません。
しかし、作品の持つ力を丁寧にすくい上げて、別のかたちで手渡すことはできます。
その手渡し方は、制作者の数だけの“やり方”が存在します。
そしてそれは、誰にも見えない小さな倫理と、たくさんの願いに支えられています。
字幕上映後に笑顔で出てくる人、何かを議論しながら出てくる人、眉間にシワを寄せて出てくる人、どんな表情や感想でも、私にはどれも嬉しい反応です。
その感想を生むための“素材”がしっかりと届いているから……。
劇場から出てくる皆さんの表情、それだけでこの仕事は救われるのです。