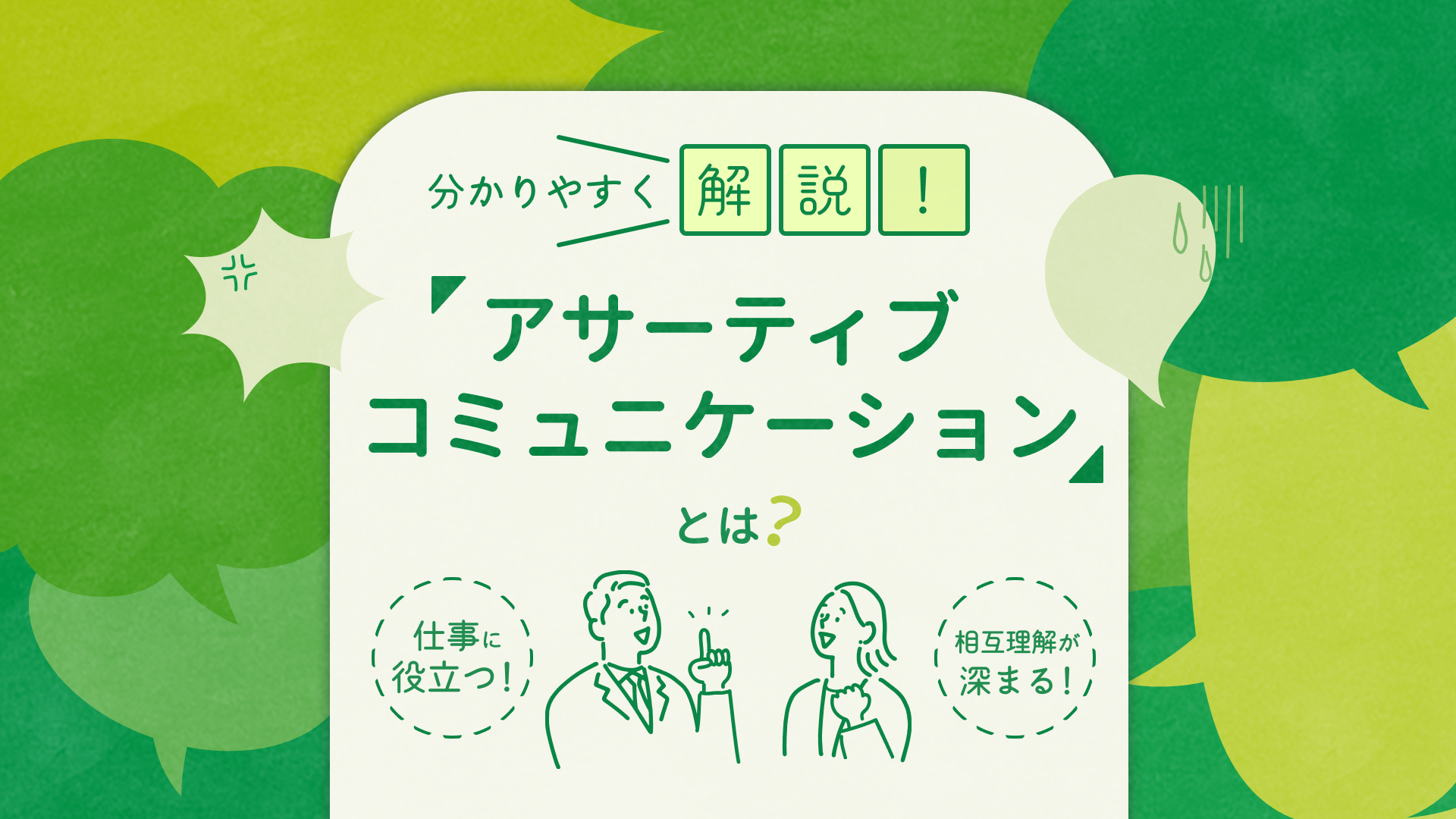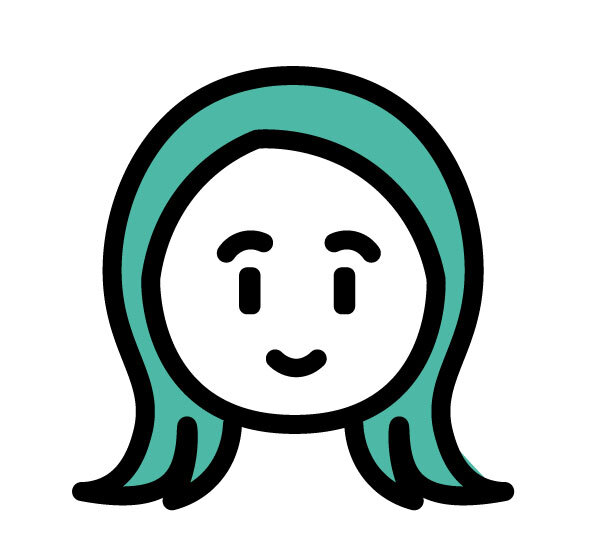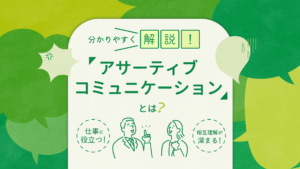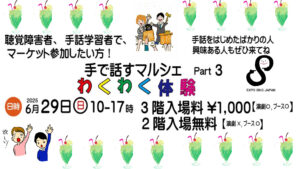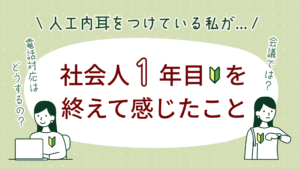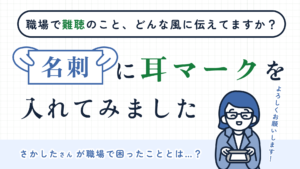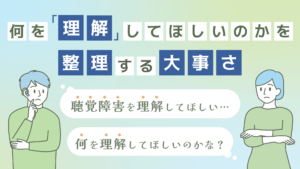皆さん、こんにちは!
皆さんは職場で上司や同僚、チームの方々と雑談も含めてお話をする機会はありますか?
忙しくてなかなかできないとか、したいけど相手が忙しそうとかさまざまな事情で十分にできていないこともあると思います。
また、自分が感じたことや提案、配慮をお願いしたいことなど、伝えたい思いがあると思います。そのためには相手とのコミュニケーションが欠かせません。
しかし、うまく伝えられなかったり、会話がかみ合わなかったり、相手の受け取り方が想定とは異なったりと誤解や行き違いが生じることもあります。職場のコミュニケーションが不足していると、モチベーションの低下や業務効率の悪化、さらには離職する人が増えることにつながってしまいます。
また、「お互いに理解し、協力しながら取り組むことが大切だ」と分かっていても、実践するのは簡単ではないですよね。
そこで、意識したいのが『アサーティブコミュニケーション』です。
これを取り入れることで、自分自身にも周囲にも良い変化がもたらされるだろうと思います。
では、アサーティブコミュニケーションとは何か、具体的にみていきましょう。
アサーティブコミュニケーションとは?
「アサーティブコミュニケーション」という言葉を聞いたことがある人もいれば、初めて知る人もいるかもしれません。
1950年頃にアメリカの心理学者が、自己表現が苦手な人や人間関係がうまくいってない人に訓練方法として取り入れたのが始まりとされています。そこから人種差別、性差別などで苦しむ人の権利を守る手段としても活用されてきました。1990年代に日本に入り、現在では企業だけでなく、医療や教育など社会的コミュニケーションスキルとして、幅広く普及しています。
まず、「アサーティブネス」とは「自己主張すること」ですが、ただ単に「自己主張すること」ではありません。自分も相手も尊重(以下、自他尊重)しながら、自分の思いや気持ちを話すことです。
そして、アサーティブコミュニケーションとは、自他尊重をしながらコミュニケーション、自分も含めて人間関係をより良く構築していく方法です。
例えば、業務で発生したトラブルや問題について、自分の感情や意見を自分自身で認識し、それを言語化するとともに、相手の考えや意見は異なるかもしれないという相違を受け入れる気持ちで、話し合いながら解決策を一緒に探していくことです。
相手を大切にすることはもちろん、自分自身も大切にすることが重要になります。
では、自己主張するときの伝え方には4つのタイプがあるとされています。それぞれの違いを見ていきましょう。
攻撃タイプ
その名のとおり、一方的に話すことです。
「負けたくない」「自分の非を認めたくない」といった自己防衛の気持ちが働くことがあります。また、「相手も自分の意見が正しいと認めるべきだ」と考え、相手の気持ちや意見を考えずに要求を押しつけるのも、このタイプの特徴です。
受身タイプ
「意見を言ったら怒られるのでは?」「生意気と思われたらどうしよう」などと考え、嫌われたくない、傷つきたくないという気持ちから、自分の意見を言えなかったり、あえて言わなかったりすることです。
また、相手の感情や意見を「正しい」「仕方ない」と受け入れてしまい、自分の考えを押し殺してしまうこともあります。「手伝ってほしい」「お願いしたい」と思っていても言い出せない、断れないといった行動もこのタイプの特徴です。
作為タイプ
表面上では相手の意見に同意しつつ、心の中では不満を抱え、第三者に不満や陰口を言ったり、遠回しな言い方で相手をコントロールしようとすることです。
また、自分の都合のいい方向へ誘導するような言動もこのタイプに当てはまります。例えば、資料作成の依頼で、「自分はやりたくない、相手がやってほしい」という気持ちがあり、「他の案件もあり、忙しいんですよね〜。」と遠回しに言うタイプです。
アサーティブタイプ
お互いの意見や考え、価値観が違いを理解し、尊重した上で、自分の意見や考えを率直に伝え、相手の意見にも聞き、より良い解決策を一緒に考えていくことです。
いかがでしょうか?自分に当てはまるタイプはありましたか?

私はどちらかというと”受身タイプ”に近いです。頼まれたことにはすべて「YES」と答え、自分の意見を言えませんでした。「わがまま」「生意気」と思われたらどうしようという不安もありました。
また、「こんなことを言ったら、相手に嫌がられるかも」「迷惑がられるかも」「この場に合っていない意見だったら…」と、考えすぎて何を言いたいのか分からなくなることもありました。恥をかきたくない、自分を傷つけたくないという気持ちから、自分を守るために意見を言わない、相手に同意することが多かったと思います。
4つのタイプを知ることで、自分がどのタイプに近いのかを見つめ直すきっかけになります。
人には喜怒哀楽という自然な感情があり、その中の「負の感情(ネガティヴ)」、例えば怒りや悲しみ、落ち込みなどを完全になくすことは不可能です。さまざまな感情があることを受け入れ、自分なりに付き合っていくことが大切でしょう。その中で、意見や価値観が違うからという理由に、自分や相手を責めるのは本末転倒です。
メリットとデメリットは?
アサーティブコミュニケーションのメリット
良好な人間関係
上司と部下などの立場に関係なく、多様な意見や考えを活発に行うことで良好な人間関係の構築につながります。
ストレスの軽減
一方的な意見や命令、負担が大きい業務などがあると、人は萎縮してしまい、それがストレスにつながります。自分の意見や相手の意見、考えを共有できるフラットな環境があれば、安心感が生まれ、ストレスも軽減されます。
視野が広がる
相手の思いや意見を知ることで、自分の知見が深まり、新たなアイデアや創造性につながります。
働きやすい職場環境
コミュニケーションが活発になることで、職場の雰囲気がフラットになり、従業員も安心・安全で働きやすくなります。さらに、トラブルや課題への対応力(解決能力)が高まり、生産性の向上や離職率の低下にもつながります。
アサーティブコミュニケーションのデメリット
「デメリット」といえるものはほとんどありませんが、アサーティブの捉え方は人それぞれ異なり、誤解が生じやすい点があります。
人によって自己主張に慣れてないこともある
受身タイプの人や自己主張に慣れていない人に対して、いきなり「意見を話して」と求めると、攻撃的な伝え方になってしまったり、過大な負担になったりすることがあります。アサーティブに取り組む際は、まず自分の感情や意見を整理し、それをどう伝えるか考える時間が必要です。自己主張に慣れている人は、強要せず、ペースに合わせて待つことも大切です。
どの場面でも必ずアサーティブが必要とは限らない
「自分はあなたを認めたのだから、あなたも自分を認めるべき」と相手に強いることは本来のアサーティブとは異なります。相手がどう受け取るかはその人次第であり、自分が決めることではありません。
また、すべての人に対してアサーティブに接する必要があるわけではなく、苦手な相手とは距離を置く選択肢もあります。上司や信頼できる人を1人に絞り、相談や意見を伝えるのも1つの方法です。
自己主張したからと要望が通るとは限らない
自分の意見や提案を率直に話すことも大切ですが、相手にも意見や考えがあり、それを尊重することが必要です。相手を否定したり、操作しようとしたりするのはアサーティブではありません。
大切なのは、意見を押し通すのではなく、どの提案が最適かを一緒に考えることです。自分の意見が正しいと一方的に主張するのではなく、「なぜそれが最適なのか」を話し合い、より良い解決策を見つけることが重要です。
アサーティブの基本となる考え方とは?
アサーティブは、基本となる考え方は4つあります。
誠実
自分にも相手にも素直でいること。
立場が違っていても、相手を尊重しているという態度を心がけ、素直に誠実なコミュニケーションを取ることが大切です。
率直
難しい言葉や遠回しな表現ではなく、相手に分かりやすい言葉で伝えること。
「他の人がそう言っていました」と第三者の発言を借りるのではなく、「私はこう思います」と、主語が「私」という自分の意見として伝えることを意識しましょう。
また、上の立場にいる人が遠回しに伝え、相手に察してもらうというやり方もありますが、多様な人がいるため、どう受け取ればよいか戸惑う人もいます。相手の気持ちを汲み取りながら、柔軟に、かつ分かりやすく伝えることが大切です。
対等
どちらかが優位に立つのではなく、対等な関係で接すること。
上司と部下などの力関係に関わらず、自分の考えや意見を伝え、相手の考えや意見も尊重することで、相互理解につながります。また、困ったときに助け合える関係にもつながります。
自己責任
「言った」「言わなかった」と相手のせいにするのではなく、自分の発言に責任を持つこと。
トラブルや課題が発生し、自分の意見が解決につながらなかったり、思わぬ結果になっても、責任を他人に押し付けたり、「本当は違う考えでした」と後から主張したりするのはアサーティブではありません。発言の結果を自分の責任として受け止めること姿勢が重要です。
4つの基本的な考え方は以下のHPから参考にしました。
詳細についてはもちろん、実践方法も分かりやすく記載されています。
聞こえない・聞こえづらい方のそれぞれの目線で、ぜひ読んでくださると嬉しいです。
また、聴者もどのように接していったら良いのか想像力をふくらませながら、読んでみてくださいね。

きこえない人とアサーティブコミュニケーション
きこえない人だけでなく、きこえる人も、きこえない人を「障害者」としてではなく、一人の人間として尊重し、その心の声に目を向けてほしいと私は思っています。
きこえない人にも、業務に関する情報、雑談や会話の内容、周囲の出来事を知る権利があります。
しかし、会議などで手話通訳者に対し、「これは言わなくていい」「知る必要はない」と指示する人がいます。
実は私の経験なのですが、会議中に上司から「冗談だから」「くだらないから」の理由で、通訳をしないよう求められたことがあります。そのとき、手話通訳者が困っている様子でしたが、私にとって通訳者は唯一の情報源です。困っている理由は分からなかったものの、その雰囲気は伝わってきました。後になって理由を知り、私はショックというより、落胆しました。直接上司に尋ねると、
「障害者には真面目な姿勢を見せないといけない。会議も真剣に進めなければならないが、場が緊張していたから和ませる目的で言っただけだ」
もちろん、会議では議題について真剣に話し合うことが重要です。しかし、発言した人のユーモアや意外な一面を共有できなかったことで、私は距離を感じました。もしその発言を知っていたら、親近感が持てたかもしれませんし、その人の考えをより深く理解できたかもしれません。それができなかったことが何よりも残念でした。
その後も、上司とのコミュニケーションは業務連絡など最低限のものにとどまり、関係性が深まることはありませんでした。
「言わなくていい」という言動自体が対等ではありません。年齢や立場、障害の有無に関係なく、相互に尊重し合うことが大切です。会議や業務連絡だけでなく、「何気ない会話」も、その人を知るきっかけになります。だからこそ、情報を共有し、対等なコミュニケーションを取ってほしいと私は思っています。
アサーティブの発祥はアメリカで、自己主張することが自然な行為とされています。一方、日本では自己主張をあまりせず、「謙虚さ」や「相手を立てること」が美徳とされる文化があります。そのため、考えがあっても言葉にせず、「暗黙の了解」や「察すること」で意思を伝える場面が多く見られます。
日本手話を使う人々は、はっきりと伝え、思ったことを言語化します。
例えば、資料作成を依頼したいとき、遠回しに「この資料を作成しないといけないようです…(=あなたに作ってほしい)」と言われると、「そうですね」と返して終わってしまうことがあります。
「この資料を作成しないといけないので、あなたに作成してほしいです」と、誰が何をするのかを明確に伝えることが重要です。
もちろん、すべてのろう者・難聴者に当てはまるわけではありません。聴者もその違いを理解し、どのように依頼すればよいかを一緒に話し合うことが大切です。そうした積み重ねが、信頼関係の構築や業務の効率向上につながります。
また、ろう者・難聴者も「はっきり伝えてくれると行動しやすい」「簡潔すぎる説明だと判断に迷うので、具体的に説明してほしい」など、自分にとって分かりやすい伝え方の提案をすることが重要です。
話し方は人それぞれ違いますが、まずはアサーティブコミュニケーションを意識することから始めてみませんか。
まとめ
聴者の多くは、ろう者や難聴者の聞こえ方について十分な知識を持っていません。「声が明瞭なら少しは聞こえるのでは?」という憶測から、大きな声で話したり、耳元に近づいて話したりすれば伝わると考える人もいるでしょう。反対に、遠慮して自分の気持ちを抑え、聴者に合わせようとするろう者や難聴者、聞こえづらい方も少なくありません。
しかし、人工内耳や補聴器をつけていても、聞こえる人と同じように聞こえるとは限りません。その違いを理解し、組織全体で適切な配慮をしていくことが必要です。
聞こえない・聞こえづらい私たちには、自分の意見や気持ち、必要な配慮について伝える権利があります。自分の聞こえのこと、バックグラウンド、意見や提案を伝えることは、とても大切な行為です。自己主張をすることで、自分を知ってもらうだけでなく、相手を知ることにもつながります。
聞こえる・聞こえないに関係なく、アサーティブコミュニケーションを意識してみてください。