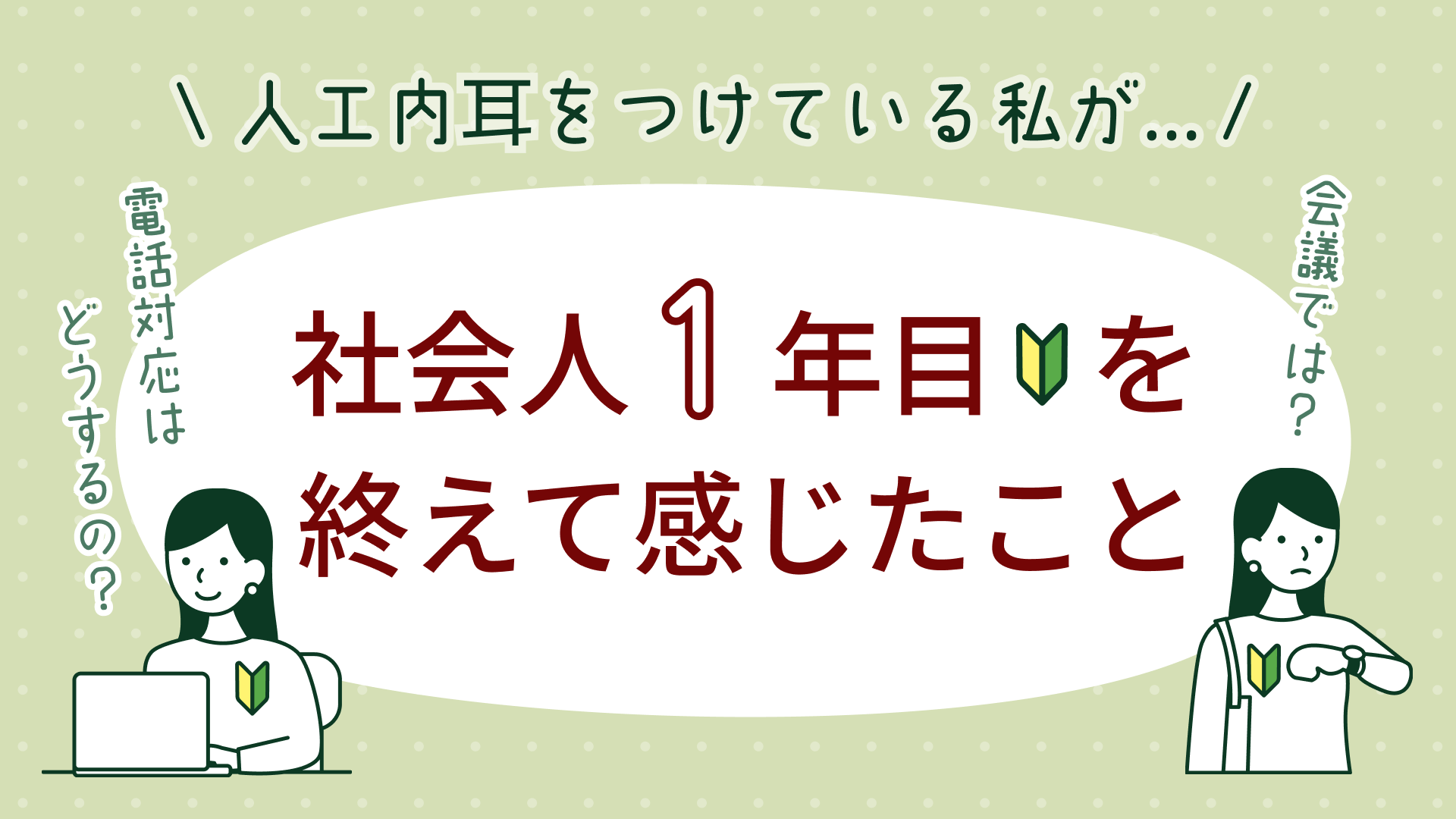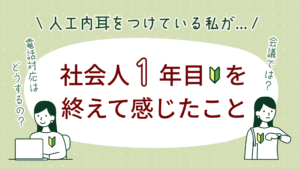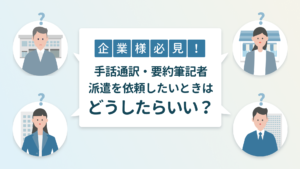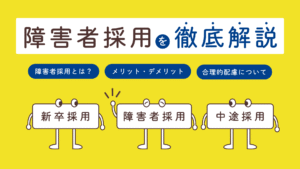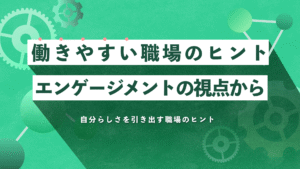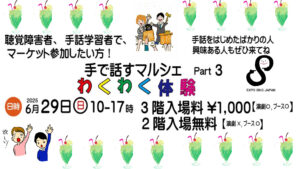みなさん、こんにちは!キコニワライターのつりざおです。去年の3月に大学を卒業し、社会人になって早1年が経ちました。早起きが苦手な私が、1年間無遅刻で出勤できたこと、そしてお弁当を作り続けられていることが驚きです・・・。
今回の記事は、私が1年間の社会人生活を通して入社後の障害に対する配慮の内容や、実際に働いてみて想定していなかったこと、そして教訓について皆様にシェア出来ればと思います。特に学生の方にとって、「こんな働き方をしている人もいるんだな」と少しでもイメージを持っていただけると幸いです。
現在の私の業務内容について軽く説明をすると、内勤のバックグラウンド業務や社内の企画を行っています。外部の方とやり取りをすることは少なく、基本的にはオフィス内で完結する業務がほとんどです。
入社前に面接で伝えていたこと
まず採用時の面接や、入社後に人事の方などにお伝えしていた配慮内容についてご紹介します。私は主に下記の3点を伝えておりました。
①電話応対は、静かな環境で、社内の人のみ可能
②対面の会議では、ロジャーマイクを使って参加する
③オンライン会議では、話し手の音声がクリアに入っていれば字幕などは不要
これらの配慮事項は、学生生活で伝えてきたことと同じですが、①の電話応対については少し工夫をしました。実は私の場合、人工内耳をつけている側の左耳を活用して電話をすることは可能です。しかし、電話では相手の口の動きが読めないことや、周囲が騒がしい環境によって聞き取りが難しくなるなど、環境によって聞こえが大きく左右されます。電話の際に自分が聞こえないことを逐一説明することも大変だと考え、聞こえにくいことによって取引先や社内にまで迷惑をかけてしまうことを懸念していました。そのため、本来なら環境によってできる電話応対ですが、あえて「社外の人は不可です」とお伝えしておりました。
社会人で想定していなかったエピソード
さて、これらの配慮事項を入社前に考えていたとしても、想定外の場面に遭遇することは多々ありました。実際に私が入社してから遭遇した想定外の場面と、その時の対処法について特に印象的だった2つのエピソードを共有いたします。
エピソード①:研修中のグループワークで発言が聞き取れない・・・!
入社して最初の1ヵ月程は新入社員研修があり、毎日のように同期とグループワークがありました。グループワークは難聴者にとって、騒がしい環境の中、話がどんどん進むため苦手意識がありますよね。(私もそうでした。)同期には最初にロジャーマイクのことを説明し、座った状態のグループワークは何とか聞き取ることができました。しかし議論が白熱し、ホワイトボードを使っての議論となると座る姿勢から立つ姿勢になり、ロジャーマイクが音声を拾えず、議論についていくことが難しくなりました。
その時、タイミングを見計らって研修を担当していた人事の方へ相談をしました。具体的にお願いしたこととして、立った時に音声が拾える位置にロジャーマイクを置くことができるようにキャスターのようなものを使いたいと申し出ました。またあえて自ら書記役を買って出ることで、文字に起こして議論についていけるようにしていました。
エピソード②:日替わりで電話当番があったこと
私が配属された部署では、部署内で毎日日替わりで得意先からの電話を取るようになっていました。この電話応対では、得意先からの問い合わせがメインで、相手が何を聞いてくるか予想しにくいという側面がありました。本来なら、静かな環境であれば電話はできなくもないのですが、相手が社外ということもあり、電話対応はできませんとお伝えしました。
ただ、業務上社内の方へ電話をかける必要性がある場合は電話を自分からかけることもあります。その際には静かな部屋に移動してから電話をかけるなど、聞こえやすい環境を自分からセッティングしていました。メールのやり取りの際にも、署名欄に「耳が聞こえにくいため電話応対が苦手です。お急ぎ以外の場合はメールかチャットにて連絡をお願いいたします。」と書いておくことで社内の人へも自然と周知を行っていました。業務上、緊急で連絡を取らないといけない時やメールの文面では伝えにくい言葉のニュアンスを伝えるためにも電話でのやりとりがここまで発生するというのは予想外でした。
自分が1年で学んだ教訓
最後に、この1年間の社会人生活を通して学んだ教訓について2つシェアしたいと思います。
①「できること」が常に「できる」とは限らない
これは、電話応対に対する姿勢を通して学んだことです。障害によっては、「できる」ことと「できない」ことの間に「できる時もあれば、できない時もある」ということがよくありますよね。その時に、私の場合は自分の障害によって相手に与える影響を考えていました。社内であれば、ある程度「あの人は聞こえにくいんだな」と認知されていますが、社外だと障害によって周囲に迷惑をかけてしまうと判断して「できません」とお伝えしていました。最初は「完全にできないわけではないのに、できないと言っていいのだろうか」と悩んでいましたが、今ではキッパリと線引きをして良かったと感じています。
②聞こえたふりにならないように「言い回し」をしていたら評価につながった
2つ目は、障害に対するリカバリーが業務上役に立ったことです。私は自分が聞こえにくいと認識しているからこそ、上司や同僚から何か言われた時には言い換えをして確認を取るようにしていました。「今〇〇とおっしゃっていたのは、・・・という認識で合っていますか?」と自分の言葉で言い換えていました。すると、後々上司から周囲の方が「しっかりと理解しようとしている」とプラスの評価を頂き、とても嬉しかったです!元々は障害に対する工夫のはずが、一般的な仕事のスキルとして役に立つこともあるんだ、と学びました。
さいごに
ここまで読んでくださった方、ありがとうございました。いかがでしたか?今の部署では比較的社外の人とコミュニケーションを取る機会が少ないため、自分の聞こえについて理解している方とのやりとりが多く、とても働きやすいです。まだまだ仕事で学ぶことは多く、今後も機会があれば記事にまとめていきたいです。
この記事を読んで、「こんな働き方をしている人もいるんだな」と皆様の参考に少しでもなれば幸いです。