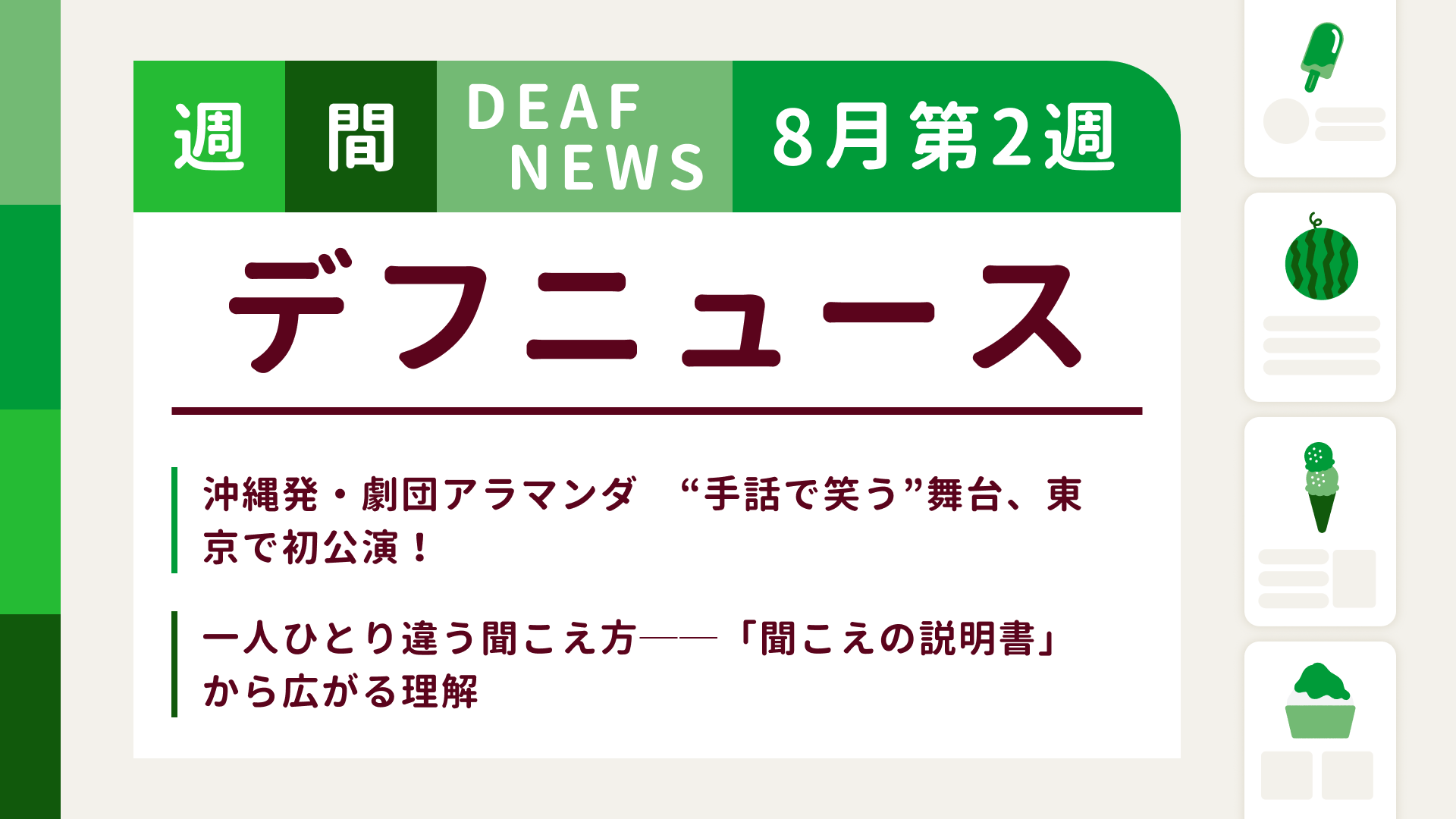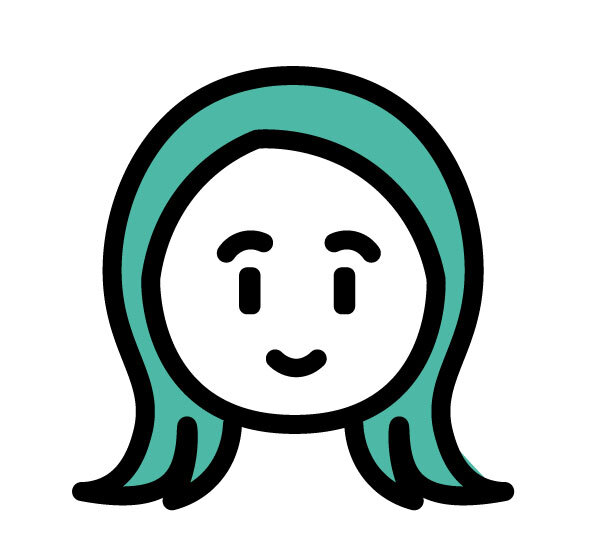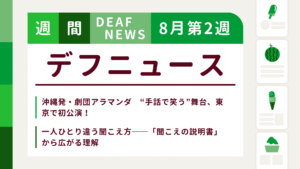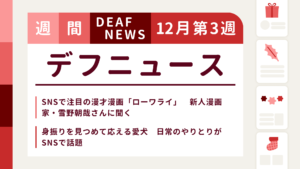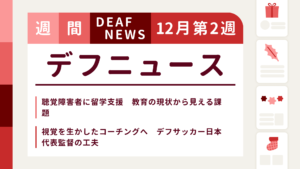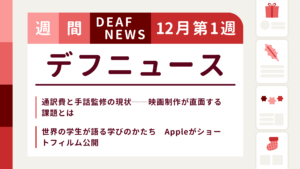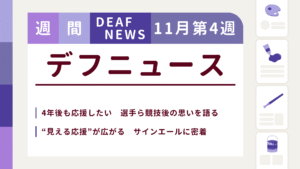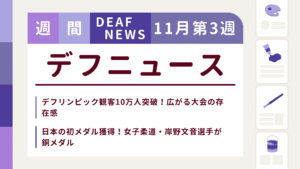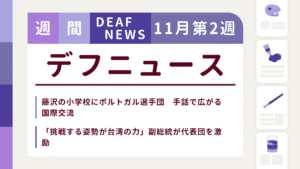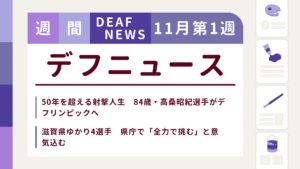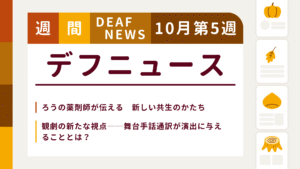こんにちは!
もうすぐお盆休みですね。皆さんはどのように過ごされる予定でしょうか?私は、家族と自宅でBBQをしながら、のんびりと過ごす予定です!お仕事の方もいらっしゃると思いますが、どうぞご無理なさらず、ゆっくり休んでくださいね🥤
さて、今週は5件のデフニュースに加え、1件のイベントなどの情報をお届けします✨
注目記事は、沖縄を拠点に活動する「劇団アラマンダ」が東京で初公演を行ったときのことを紹介した記事です。大屋さんはコーダで、ご両親が聴覚に障害のあるなかで培った経験をもとに、劇団での活動に取り組んでいます。ご自身の歩みや表現への思いが語られており、読み応えのある内容です。ぜひ、最後までご覧ください!
沖縄発・劇団アラマンダ “手話で笑う”舞台、東京で初公演!
沖縄のピン芸人・大屋あゆみが座長を務める「劇団アラマンダ」が、手話を取り入れたコメディ劇を東京で初めて上演しました。クラウドファンディングや企業協賛で実現し、ろう者や手話を勉強している人などさまざまな人が来場。多様な表現を通して、誰もが一緒に楽しめる舞台となり、観客の笑顔があふれました。


「劇団アラマンダ」は以前から観たいと思っていた劇団のひとつ。今回は残念ながら観られませんでしたが、次の機会にはコーダの子どもと一緒に観に行きたいです。再公演の実現を願っています!
一人ひとり違う聞こえ方──「聞こえの説明書」から広がる理解
聴覚障害のある人の多様な聞こえ方や課題について、武蔵野大学助教の志磨村早紀さんが、自身の経験をもとに「聞こえの説明書」の意義を語っています。社会との相互理解のため、当事者が自分の聞こえを整理・共有する工夫や支援のあり方を提案しています。


私自身も学生の頃、聞こえないと自覚していても、どう説明すればよいか分からないといった経験があります。「聞こえの説明書」を作ることは、相互理解の促進だけでなく、自分のアイデンティティを見つめるきっかけにもなりますね。
聴覚障害と社会の壁 当事者が問いかけること
毎日ユニバーサル委員会がテーマ「聴覚障害者を巡る社会的課題」について議論しました。基調講演では、演劇鑑賞や教育における支援格差、情報保障の遅れなどが語られました。委員たちは、当事者の視点で制度の見直し、技術活用の重要性を強調。共生社会へ向け、社会側の変化と発信力の必要性が示されました。


廣川さんの「乗り越えるべきなのは私たちではなく、社会の側が越えてほしい壁なのです」という言葉が印象的でした。「困難を乗り越える当事者」ではなく、社会の仕組みや意識を問い直すことが大切だと改めて感じました。
Amazon社員で元代表選手が伝える、東京デフリンピックの魅力と支援のかたち
日本で初めて開催される「東京2025デフリンピック」は、聴覚に障害のあるアスリートが世界中から集まる国際スポーツ大会です。元バレーボール日本代表の猪野康隆さんが、その魅力や応援の方法、支援のかたちについて語ります。


元日本代表ならではの経験や視点が語られていて、非常に読み応えのある内容でした。Amazonだからこそ実現できる支援のかたちも紹介されており、とても意義深い取り組みだと感じました。
デフリンピック内定選手や候補選手へのインタビュー記事をご紹介
【デフゴルフ】前島博之選手と辻結菜選手と渕暢之選手のインタビュー記事

記事の「聞こえの説明書」と「聴覚障害と社会の壁」について、少し考えてみました。
「聞こえの説明書」とは、自分の聞こえ方や必要な配慮について整理し、学校や職場などで周囲に伝えるため。また、スムーズなコミュニケーションや安心できる環境づくりに役立つものだと思います。
一方で、「聴覚障害と社会の壁」という言葉には、聴覚障害のある人がさまざまな場面にアクセスしようとするとき、音や音声を前提とした社会の仕組みが壁になってしまっている、という現実が込められています。つまり、困りごとの原因は本人ではなく、社会の側にあるということです。
「聞こえの説明書」が必要になる背景には、まだ社会の理解や配慮が十分ではないという現状があります。 裏を返せば、周囲に理解してもらうために、自分で自分のことを説明しないといけない場面が多いということでもあります。
もし、「聞こえの説明書」がなくても困らない社会になったら──きっと、もっと多くの人が、自分らしく、のびのびと暮らせるのではないかと感じています。
キコニワは11日〜17日までお盆休みです!
それでは、良い休日をお過ごしください✨
📢イベントなどの情報
【テレビ】ろう者初のラーメン店店主 毛塚和義さんが切り開いたキャリアの道
8月13日(水)20時〜NHKで放送!唯一のろう者経営ラーメン店主、毛塚和義さんの人生を描く物語。