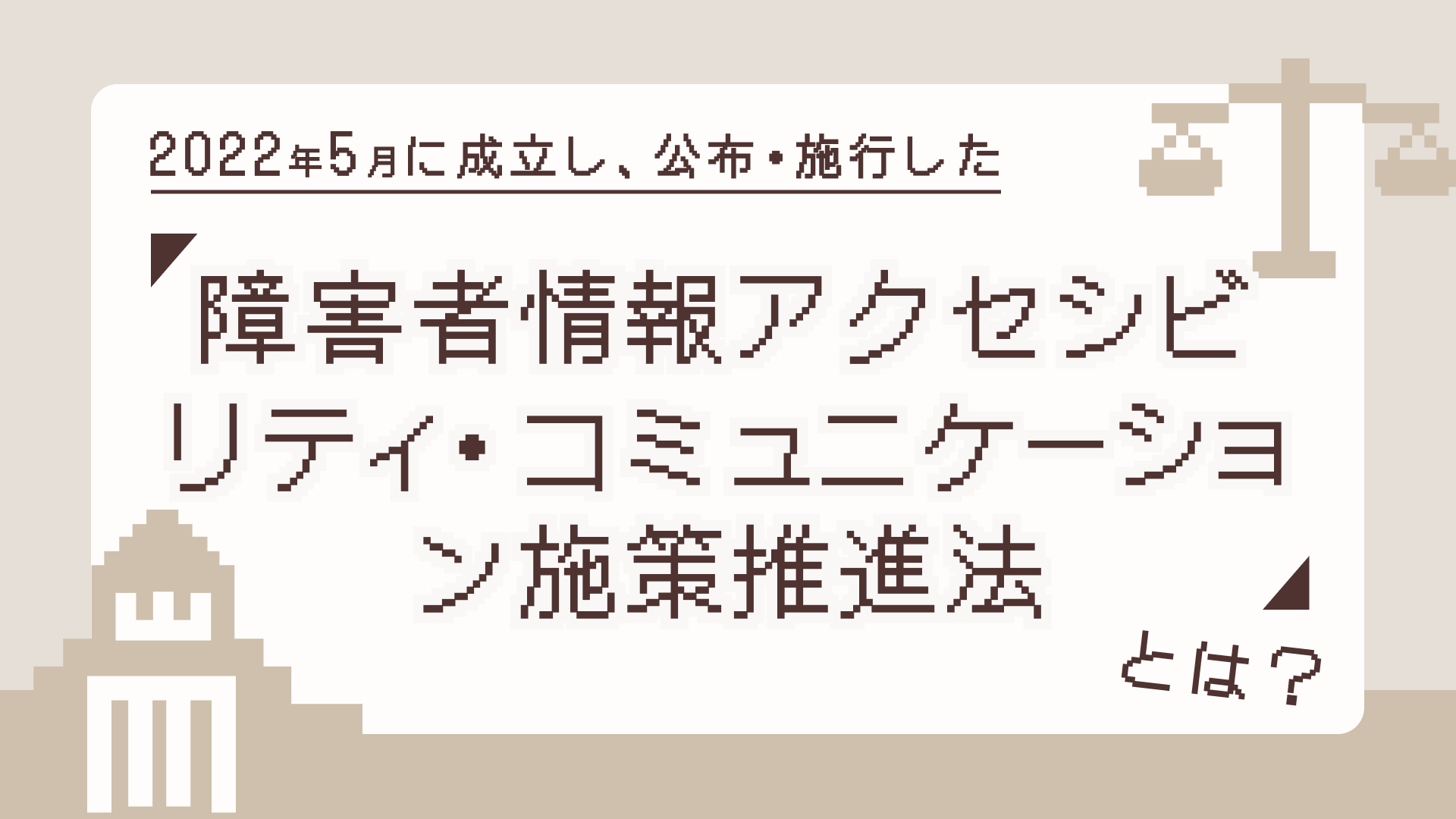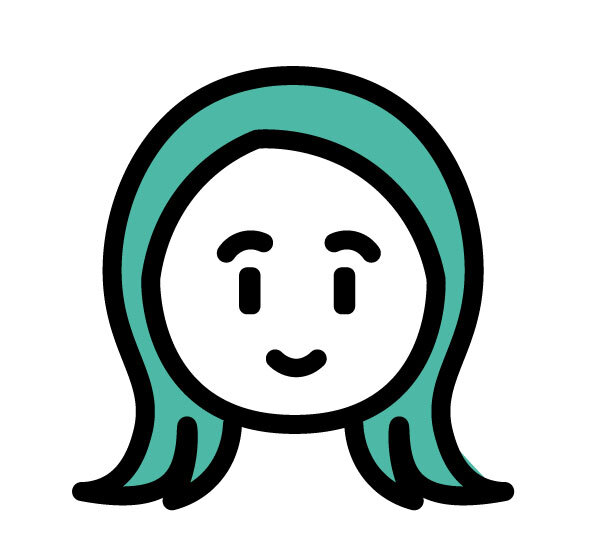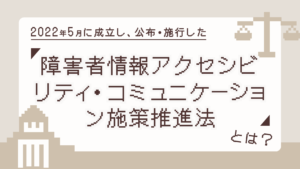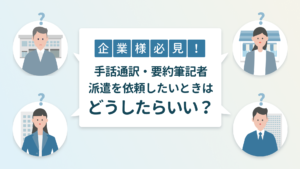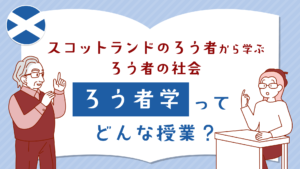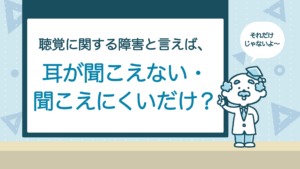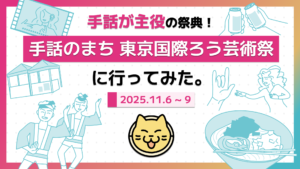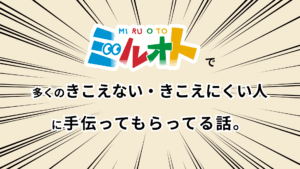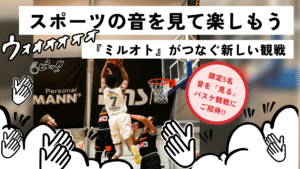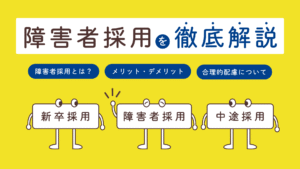※ここでは、聴力に関係なく「聞こえづらい」「聞こえない」すべての人に提供できるように、きこえに障害があるとして「聴覚障害者」と表記しています。ご了承ください。
皆さん、こんにちは!
「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」をご存知でしょうか?
3年前に施行されたこの法律は、当初はあまり知られていませんでしたが、現在は少しずつ認知が広がっています。
「アクセシビリティ」とは、障害の有無にかかわらず、誰もが平等に情報やサービス、環境を利用できる状態を指します。例えば、聴覚障害者の場合、駅の音声アナウンスを文字で表示することで情報を得られるようになります。また、段差をなくすことで、車椅子の方の移動のバリアが減ります。
音声アナウンスの文字表示は、聴覚障害者だけでなく、聞き逃した人にも役立ちますし、段差のない環境は松葉杖を使っている人や高齢者、子どもにとっても安全です。このように、 誰もが支障なくアクセスできる状態を整えること が「アクセシビリティ」なのです。
ここでは、聴覚障害者の情報アクセスについてと、情報アクセシビリティやコミュニケーションの変化について見ていきましょう。
聴覚障害者の情報アクセスとは?
聴覚障害者とは、全く聞こえない人、聞こえづらい人、片耳だけ聞こえない人、途中で聞こえなくなった人、また、聞こえ方に違いがあります。コミュニケーション方法も人によって異なり、手話、読唇、筆談などがあります。
では、情報アクセスとはどのようなことでしょうか?
聴者はテレビ、ラジオ、スーパーや電車のアナウンス、イベントや交流会など、さまざまな場面で自然と情報を得ることができます。これが情報アクセスです。
聴者が、音や音声が入りやすいように作られたものがたくさんあります。例えばスピーカー、電話などです。つまり、聴者にとって、情報がアクセスしやすい社会となっています。
聴覚障害者は聞こえないだけでなく、情報が入らない、もしくは入りにくいのです。その情報は例えば、聴者が当たり前に入ってきてる情報はもちろん、災害など命に関わる重要な情報も入りません。
東日本大震災では、地震だけでなく津波という二次災害の危険を知らず、命を落とした聴覚障害者も多くいました。また、身体に突然の痛みがきて、救急車を呼びたくても方法がない、病院に行くのも情報保障やコミュニケーションが必要なので、人によりますが、病院で事前に確認、手話通訳派遣依頼など、事前準備が要するため、すぐに病院へ受診することができないこともあるので、痛くても我慢する、手話通訳者が見つけ次第行くなど健康格差も生ずるケースもありました。
このようなことから、聴者に合わせた社会で、聴覚障害者が情報を簡単にアクセスできず、社会的障壁となっています。
情報通信技術(以下、ICT)が発展し、FAX、メール、テレビ電話、電話リレーサービス、次から次へと利便性が高くなり、現在では、命に関わる情報、災害情報を可視化し、全国規模で取り組んでいます。また、電話リレーサービスも公共インフラとして、2021年から24時間365日、緊急通報も使用でき、聴者からもかけることができるシステムになっており、聴覚障害者の自立にもつながっています。
メールも、聴覚障害者には必要なツールの一つでもありますが、聴者も欠かせないツールとなっており、双方にとって良い利益をもたらしています。
ICTの発展により、障害の有無に関わらず利便性が向上し、生活の質や選択肢も広がりました。
しかしながら、まだまだ課題はあります。
例えば、
- 全国放送のニュースで、リアルタイムに命に関わる情報や災害情報の発信はまだ弱く、字幕がついていても、遅れて表示するため、映像と字幕が一致しないので、非常に分かりにくいです。手話通訳者の配置が必要です。
- 動画配信サービスについては、ドラマもバラエティも字幕がついてないのがほとんどです。また、見逃し配信もバラエティに関しての字幕がついてないことも多いです。
- 映画館や劇場、コンサートについて、映画館では邦画(音声日本語のみ)の上映期間は最長1ヶ月、1日の上映回数も複数あります。日本語字幕上映は短くて2日間、長くて3日間しかなく、時間も1回のみで選択肢がひとつしかありません。 劇場では劇場によって異なりますが、劇場での情報保障が少ないのも現状です。一部は字幕表示の機器を使って、字幕のセリフを読みながら舞台を観る、手話通訳者をつけることもあります。 コンサートでは一部で手話通訳者が配置されることもありますが、まだまだ少ないのが現状です。
- 興味のある講座やセミナーなどへ申込みをする前に、耳が聞こえないことを伝える、手話通訳者を派遣したいと要望、など事前の説明や準備が必要になります。聞こえない方も参加する可能性を想定してないのです。
- コロナ禍によりマスク着用をする人が増え、仕事でも買い物でも、口の動きが読み取れず、話しているのか判断が難しいです。
聴者と同様に、情報を自由に入手、アクセスしたりして、行動の幅が広がる社会になるためにはどうしたらいいのか、聴覚障害者だけではなく、聴者も一緒に考える必要があると感じています。
障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法とは?
成立した背景には、前述した聴覚障害者の情報へのアクセスにも関係しています。また、他の障害者も、例えば、視覚障害者の場合はホームページの読み上げ機能が使えないことが多く、情報の格差が生じています。その結果、社会的障壁となり、平等に社会参加ができていないということで、「情報格差を解消」するためにできた法律です。
情報格差はどのようにして生じているのでしょうか?
前述の「聴覚障害者の情報アクセス」の事例の他に、以下の困難さもあります。
- 視覚障害を持つ方、発達障害の方の中には、読書(電子書籍なども含む)による視覚的情報が得られない、得にくい、または、視覚による表現の認識に困難があり、自由に見ることが難しい。
- テレビや動画配信サービスには字幕がないところもあり、自分で選んで好きなように見ることができない、また、テレビは生放送だと遅れて表示するので分かりにくい。
- ニュースや災害に関する情報を字幕だけだと危険度の理解が難しい。
- 緊急放送やアナウンスなどは音声が多いため、視覚的情報が得られない。
これらの問題は社会構造的に、聴者に合わせたシステムとなっているため、情報格差が生じてしまいます。
誰もが情報に自由にアクセスできる社会になれば、選択肢や行動の幅が広がります。
まとめ
障害者は法律で守られ、法律の力によって理解を深めていくことは、共生社会への第一歩です。しかし、それだけではなく、一人ひとりが障害者を含む多様な人の存在を知り、理解を深めていくことが、自然と多様な社会へとつながると考えます。
社会でよく言われる「一般」「普通」「平均」といった言葉は、無意識のうちに自分の価値観を基準にして分け隔てるのでは…と感じています。
障害の有無に関わらず、人は皆それぞれ異なり、考え方も違います。自分の立場や価値観だけで物事を決めることは、結果として社会全体を生きにくくしてしまうことにもつながります。
そもそも、今の社会構造は、五体満足で心身に問題のない人々を基準に作られてきました。その中で、聴覚障害者をはじめとする多くの障害者は「普通ではない」「かわいそう」と見なされることが少なくありません。しかし、「普通」とは一体何なのか、その基準は誰が決めたのか?それを改めて問い直すことは、自分自身の立ち位置を見つめ直す機会にもなるでしょう。
そして、考えるだけでなく、誰かと対話してみることも、理解を深める大きな一歩になるはずです。