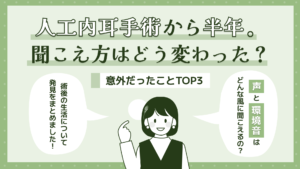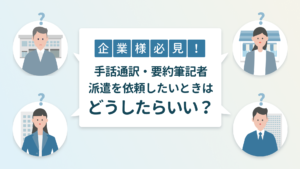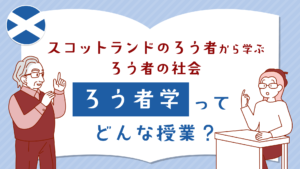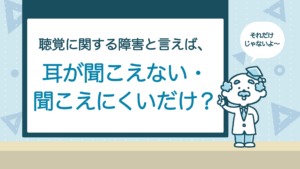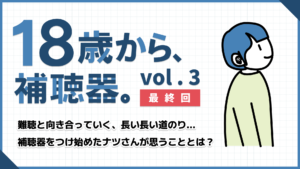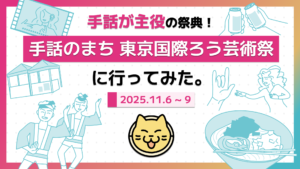はじめに
こんにちは、チョビ輔です!
だんだんと暑さが増し、晴れやかな青空が広がる季節ですね。
皆様いかがお過ごしでしょうか?
暑がりな私は、すでにクーラー必須の気温に疲弊しながら、汗だくになって遊ぶ子供たちと格闘する毎日を過ごしております。
さて今回は、前回の記事の最後に少し触れた、三重県のいなべ市にある音声オフのカフェ『桐林館喫茶室』(とうりんかんきっさしつ、以下名称は桐林館)について書きたいと思います。
↓前回の記事↓
「わたしたちに祝福を」上映会の様子
先日、横尾友美監督の映画「わたしたちに祝福を」の上映会と講演会、そして栗田一歩氏の写真展が桐林館で開催されました。
上映会のポスター
廊下から撮影した講演会の様子
写真の展示(一部)
「わたしたちに祝福を」の上映に合わせて、映画公開前に製作され、さがの映画祭で大賞を受賞した短編「わたしたちについて」も上映されました。
短編の撮影場所として桐林館も使われていましたので、映像の多くに、桐林館のさまざまなシーンが使用されており、物語の演出に良い味を出していたように思います。
短編撮影時の様子
短編撮影時の様子②
上映会では、横尾監督と写真家栗田一歩氏のトークショーとともに、短編撮影に参加した娘2人と私も、出演者として、その時の様子や感想などを少しお話させていただきました。たくさんの人前で、自分の考えや感想を話すという機会はあまりないので、娘たちにとっても良い経験になりました。
ご参加くださった皆様、ありがとうございました。
桐林館喫茶室とは
さて、この桐林館ですが、一般的なカフェや喫茶店と少し違った特徴がいくつかあります。
①建物が国登録の有形文化財
1939年に旧阿下喜小学校として建設された建物の一部をリノベーションしてカフェとして利用しています。教室や校長室が昔のまま残されており、建物の見学だけでこの場を訪れる人も多いようです。いっけん、カフェがあるとは思えない外観です。
建物の外観
正面玄関横にたたずむ二宮金次郎像
教室
校長室
②カフェ内は「音声オフ」
お客様もスタッフも、音声以外のコミュニケーション(筆談、手話、ジェスチャーなど)を使って会話を楽しむというのが、このカフェのルールです。
聴者にとっては非日常な空間に、ろう者にとっては落ち着ける居場所に。
体験型カフェという『静かでにぎやかな場所』というのが桐林館の魅力のひとつです。
入口付近の様子
③アール・ブリュットな空間
アール・ブリュットとは「自身の表現方法を自由に追求している芸術家」という解釈もありますが、ここでは「障害者の表現活動」のサポートを意味します。地域の支援施設に通いながらアート活動をしている人や、カフェのオーナーと繋がりのある障害者アート作品が、室内にたくさん飾ってあります。定期的に展示を入れ替えたり、物販販売も行っています。
やまなみ工房の正己地蔵
短編の撮影と、映画の上映会をした横尾友美監督に、桐林館の印象を聞いてみました。
 チョビ輔
チョビ輔桐林館で短編撮影と上映会をしましたが、横尾さんにとって桐林館はどのような空間でしたか?
 横尾友美監督
横尾友美監督初めて短編を撮影した場所が桐林館です。桐林館で長編映画&短編映像を上映していただき、原点に帰ったような感覚になりました。古い校舎、手話、コーヒーとパン…とても落ち着き、居心地が良いところです。店主の夏目文絵さんが取り組んでくださっているのもあり、多くのろう者に愛される喫茶店ということが伝わってきます。これからも大切にしてほしい場所です。
他にも、昨年発行された、ろう者のイラストレーター「うささ」さんのエッセイ漫画「耳がきこえないうささ ウワサのユニバーサルスポットをゆく」でも、桐林館の様子が紹介がされていますので、是非記事と合わせてご覧ください!
桐林館オーナー、夏目文絵さんへ質問
 チョビ輔
チョビ輔なぜこのようなカフェを始めようと思ったのですか?
 夏目文絵さん
夏目文絵さん2020年の8月に前のオーナーからこの店を引き継いだ時に、他のカフェと違う場所にしたいと思っていました。看護師の経験から、ろう者をはじめ当事者と関わる中で、ずっと「世間が思い描く病気や障害・福祉」と「現場で起こっている事柄」に大きなギャップを感じていました。だから、日常生活に近いところで福祉に触れる機会、ハブとなるような場所があるといいなと思っていたので、あえて「筆談カフェ」にしました。手話ができなくても、筆談でもジェスチャーでも、声以外なら何を使ってもいいですよと。誰でも入りやすくしたかったので「筆談カフェ」にしたことで間口は広がったと思います。コンセプトは「フクシはオシャレでオモシロイ」です!
 チョビ輔
チョビ輔筆談カフェ以外にも色々な活動をされていますが、他にはどんなものがあるんですか?
 夏目文絵さん
夏目文絵さんカフェ経営の他には…
一般社団法人 kinari 代表理事、看護師、コミュニティナース、地域の登録手話通訳者、教員(非常勤講師)、講演会やワークショップの開催、文字でアートな雑貨店「モジマトペ」の運営、障害者表現活動(アール・ブリュット)のサポート、福祉プロダクトの販売などなど、色々やってます👍
 チョビ輔
チョビ輔ひぇ〜!すごい!コミュニティナースというのはどんな活動ですか?
 夏目文絵さん
夏目文絵さんコミュニティナースというのは「コミュニティナーシング(地域看護)」から来ている言葉で、ナースという言葉が入っていますが職業や資格ではなく「地域で人をつないだりして、街を元気にしよう」という概念、活動の在り方です。イベントや企画、施設の訪問など人と街を元気にする活動をしています。いわばプロの健康おせっかいです(笑)
 チョビ輔
チョビ輔アール・ブリュットな空間がとても素敵だと思うのですが、展示作品はどのように選んでいるのですか?
 夏目文絵さん
夏目文絵さん地域のアーティストの方や知り合いを通じてとか、時にはSNSでスカウトすることもありますし、ビビッときた作品を選んでいます(笑)
ドリップコーヒーのパッケージデザインをしてくれた「fuco:」さんは、オープン当初からの付き合いです。桐林館でも特に大きな作品を飾っていたり、何度か特別展もして桐林館にも遊びに来てくれました。そして今や、ヘラルボニー(※)の異彩作家としても活躍しています!ヘラルボニーの契約が決まった時は、とても嬉しかったです。
※ヘラルボニー
主に知的障害のある作家さんとライセンス契約をし、それをデザインした製品をつくったり、企業とコラボしてアートイベントを展開したりしている今注目のブランド。契約している作家のことを異彩作家と呼ぶ。
fuco:さんのデザインドリップコーヒー(kinariのオリジナル商品)
 チョビ輔
チョビ輔手話との出会いは?
 夏目文絵さん
夏目文絵さん私自身は、高校生の頃から手話を始めました。看護師になりたいと思っていたので、聞こえない人が患者さんとして来たらどうしようと考えたのがきっかけです。地域の手話サークルに参加してみると、これがすごく面白かったんです。「手話は言語だし、社会に出ると聞こえないことで壁があるかもしれないけど、聞こえないこと自体は障害ではないのだな」と思いました。ろう者の皆さんとの出会いから福祉に関心が湧き、その後、看護師として児童福祉施設等で働いたりもしました。
今では配偶者がろう者なので、毎日手話で会話しています。
 チョビ輔
チョビ輔カフェの利用はどのような人が多いですか?
 夏目文絵さん
夏目文絵さんやはり他の飲食店より聴覚障害当事者の方が多いですね。2~3割が当事者の方という印象です。安心して来てくださるというか、ここを目的に来てくれる方もいて嬉しいです。あと意外にも、男性ひとりでいらっしゃるお客様も多いです。
 チョビ輔
チョビ輔お客様は、この「筆談カフェ」をどう思っているのでしょうか?
 夏目文絵さん
夏目文絵さんオープンしてからお客様が自由に書き込める筆談ノートがすでに100冊を越えたのですが、それを見ると、皆さん非日常を楽しんでいる人が多いです。スタッフへの一言、次にノートを見るお客様へのメッセージなどを残してくださる方や、そこに別のお客様が何か答えたりして、タイムラグのある筆談みたいなことが行われていたりします。文字だけではなく絵で会話していたり、絵しりとりや○×ゲームをしていたり。これは筆談の良さですし、最大の特徴ですよね。
お客様たちとの楽しい会話は財産です。
筆談ノート
 夏目文絵さん
夏目文絵さんここは「手話カフェ」ではなく、あくまでも音声以外のツール(手話、筆談、ジェスチャー、絵など)を使ってコミュニケーションをとれる場所です。ツールはどうあれ、お互いの心もち、聞きたい・知りたい気持ちと伝えたい気持ちがあれば、聞こえないことも、(声で)伝えられないことも、ここでは「障害」ではなくなる。筆談は、対面じゃなくてもタイムラグがあっても会話を楽しめる。
そういうコミュニケーションの面白さや可能性を桐林館で感じてもらえたらうれしいです。
私と桐林館の出会い
私が桐林館を知ったのは、今から4年前のことです。今5歳の娘がまだ1歳の頃。
筆談カフェとしてオープンしてからは半年程経っており、たまたまつけたテレビで桐林館の特集がされていたのを見たのがきっかけです。
特集では、当事者が集まるカフェとして、そしてオーナーを含めた3人のユニットの紹介がされていました。
その頃は、オーナーの夏目さんが桐林館を中心に筆談カフェを運営し、他の聴覚障害当事者2名(カトウシンヤさん、柴田恭兵さん)の3人で「筆談ラボ」というユニットを組んでいました。
カトウシンヤさんは難聴のイラストレーターでコミュニケーション手段は主に手話と口話、柴田さんは難聴のバリスタでコミュニケーションは主に口話です。どちらも補聴器ユーザーです。
この3人が共通してフェアにやりとりができる手段が筆談ということで、現在も「筆談を推すプロジェクトチーム」として、講演やワークショップなどの活動も行っているようです。
左から夏目文絵さん、難聴のイラストレーターカトウシンヤさん、難聴のバリスタ柴田恭兵さん
↓筆談を推すプロジェクトmojicca(モジッカ)のサイト
当時、テレビで桐林館の特集を見た私は「聴覚障害のある当事者が活動している場所がある!当事者に会って話を聞ける!」と思い、とても嬉しかったのを覚えています。
というのも、その頃はコロナ禍だったので、せっかくろう学校に通い始めたのに活動は月1回と少なく、娘とのコミュニケーションに不安を感じていた時期だったからです。
毎日、たどたどしい手話と音声で娘に話しかけながら、はじめての難聴児育児を手探りする日々が続いていました。
外出もできず、気持ちが沈んでしまうこともあり、誰かに話を聞いて欲しいと思っていたのです。
そんな時にテレビで桐林館の存在を知り、毎週通うようになったのでした。(今は引っ越ししてしまいましたが、当時は家から車で40分くらいの場所にありました)
とにかく、娘を手話のある空間に連れていきたい、自分以外の人と手話でコミュニケーションをとって欲しい、当事者と出会って交流して欲しい、という気持ちが強かったので、手話のできるオーナーの存在は大変ありがたかったです。
難聴児を育てる正解って何なのか?手話さえ覚えれば大丈夫なのか?とその頃は日々思っていましたが、手話だけでなく、指文字やひらがな(日本語)、絵やジェスチャー、携帯アプリなどさまざまなツールを使って気持ちを伝え合う方法があることや、その大切さ、コミュニケーションという本質を知る第一歩として、桐林館の存在はとても大きかったと思い、今も感謝しています。
さいごに
聴親の私にとって、耳が聞こえない子が産まれるというのは未知の世界の始まりです。
情報は色々収集するけれど、それの何が正解で何が間違っているか全く分からないまま、小さいうちは特に、漠然と将来に不安を感じていることも多いと思います。
そんな時「こんな場所があるよ!」「こんな人がいるよ!」「こんな企画があるよ!」「こんな考え方もあるよ!」と言ってもらえる人や場所との出会いはとても貴重で嬉しいものです。
桐林館に限ることではありませんが、自分と世間を、そして聞こえる世界と聞こえない世界を繋いでくれる、まさにハブ(繋ぐ)の存在になってくれる場所や人と出会うことで、難聴児育児に対する気持ちが、随分と明るくなったと思います。
私と同じように、難聴児を育てる聴者の親御さんにとっては、数ある情報の何を信じ何を選ぶかというのはとても難しい問題だとは思います。
しかし、自分の信じる人やモノ、繋がる場所を増やして、子どもの選択肢や世界を広げられる何かを見つけられると、子育てがもっと楽しくなるんだなと、自分の経験を通して感じています。
最後になりましたが、看護師、手話、福祉、アートなど多方面の知識を持ち、精力的に活動しているオーナーの夏目さん、本当にすごい人だなと思います!しかも、カフェ経営をしながら、昨年、京都芸術大学大学院を卒業し、芸術修士を取得したとのこと!
講演会やワークショップ、筆談カフェ体験イベントなども全国的に行っているようなので、今後の活動にも是非注目して頂きたいと思います。
自己紹介/夏目文絵(ぱっち)
- 三重県桑名市出身、いなべ市在住
- 配偶者はろう者
- 一般社団法人 kinari 代表理事
- 看護師/コミュニティナース
- 登録手話通訳者(桑名市・いなべ市)
- 教員(非常勤講師)
- 桐林館喫茶室「筆談カフェ」、文字でアートな雑貨店「モジマトペ」を運営
- 元地域おこし協力隊(2023年9月末で任期終了)
- この春、京都芸術大学大学院(コミュニケーションデザイン領域 )を修了し、芸術修士(MFA)取得
桐林館のイベント、講演会やワークショップのお問い合わせはコチラ↓