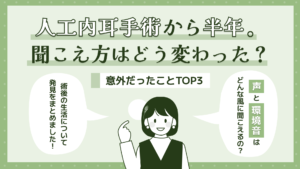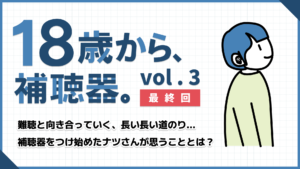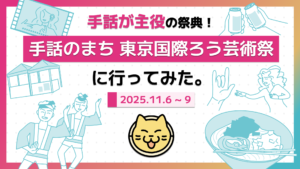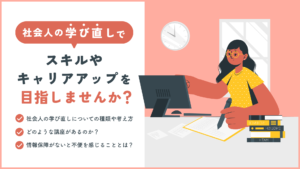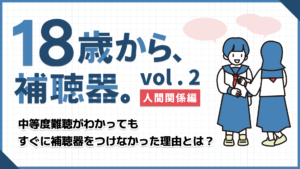おひさしぶりです、チョビ輔です。
前回の記事から、ずいぶん期間が空いてしまいました。
↓前回の記事↓
我が家は、生まれつき重度難聴の娘を手話メインで育てています。
しかし近年補助装具(人工内耳、補聴器など)の進歩により、同じ聴覚障害でも手話や音声、手指日本語、音声アプリ、筆談などさまざまな手段でコミュニケーションをとるなど、必要な保障が皆同じではないことが知られるようになってきました。
ろう・難聴児の成長が、本人の資質や環境、地域や家庭の選択によってさまざまであるということを実感するにつれ、ここで【 ろう・難聴児を育てる聞こえる親】としてどんな記事を書けばいいのか、その考え方は果たして正しいのか、他の選択をした家庭を責めることにならないか…など、考えれば考えるほど、記事のテーマの難しさに悩んでおりました。
とまあ、長い前置きになってしまいましたが…
そんな中でも我が家ならではの経験として、私と娘が挑戦したさまざまなことについて、今回は記事にしたいと思います。
ろう児キッズモデルへの挑戦
今5歳の娘が3歳の時、SNSを見ていたらキッズオーディションの広告が目に止まりました。
親のミーハーな想いも多分にあったとは思いますが、娘は鏡を見たり写真や動画を撮られるのが好きな子だったし、最終審査は東京の大きなホールでたくさんのお客さんの前でランウェイ歩くというオーディションだったので
 チョビ輔
チョビ輔よし、キッズモデルに挑戦してみよう!受からなくても応募するだけタダだし良い経験になるかも?もしかしたら東京に遊びに行けるかも…!?
と思い(不純な動機込みで)応募を決めました。
一次審査の段階で【耳が聞こえないため補聴器を装用すること】【手話が第一言語で、受け答えはすべて手話になること】を伝えました。また、昨今よく言われている「多様性が~」や「インクルーシブな面で~」といったことも書き添えました(が…これは、耳のことで落とされる心配があるかも?と思いすぎて、主語を大きくしすぎたな…と後で反省しました…笑)
無事に一次審査、二次審査(※Zoom)を通過し、その後はスタジオでの対面グループレッスンを受けることになりました。(※Zoom審査は名前の呼びかけに返事をすることや審査の意気込みを発表することでした。私が横で通訳のようなことをしましたが、娘は見事に何もせず、それでも受かったのが不思議なくらいでした。)
このオーディションでは3歳という年齢はベビー部門になるらしく、グループレッスンの内容は主にリトミック(音楽に合わせて体を動かし、表現力や感性を育てる教育法)でした。
基本的には保護者と一緒に楽しみながら講師の動きを見て真似るというレッスンが多く、音をきっかけに体を動かしたり止めたりするなど講師の指示に従うことがメインだったので、私が娘にタイミングを教えながら一緒にレッスンを受けました。
偶然の出会い
このグループレッスンで偶然の出会いがありました。同じ会場に、ろう者のママとコーダの親子がいたのです。
レッスンには手話通訳がおらず、そのママは筆談でスタッフと話をしているようでした。しかし、スタッフが慣れていないこともあり、必要な説明を飛ばしたり、見てわかる事をわざわざ書き出したり、会話のペースが合わず見ていてヤキモキしてしまいました。ありがた迷惑だったら申し訳ないなと思いつつも、私がレッスン中に音のタイミングを伝えたり簡単な通訳をしたりしました(一応相手には許可をとりました)
今回の記事作成にあたり、当時のこと改めて聞いてみました。
 チョビ輔
チョビ輔レッスンや面談の時、どのようにやり取りしていましたか?また主催者側はどのような対応をしてくれましたか?
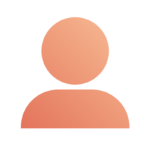 Aさん
Aさんレッスンは主に筆談してました。あとはチョビ輔さんにも通訳してもらったり(笑)Zoomでの面談は、審査員がキーボードを打ち、私は大きな紙に書いて答えていました。最終審査ではホールのロビーに少しだけ手話ができるスタッフがいましたね。
 チョビ輔
チョビ輔いましたね!でも通訳するというわけでもなく、何か聞かれたら答える程度で、あとはそばで見守ってましたね…
案内の時や、主催者が声で誘導する時など、必要な情報を得るのに、もう少しうまいやり方があるんじゃないかな?と内心思ってました。
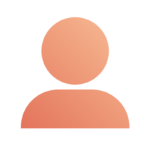 Aさん
Aさん実は、今年もオーディションを受けていて、今回は、YYProbeという音声アプリを使いました。本番では手話ができるスタッフがいなかったので、スマホに打って返事をしたりスタッフの話はYYProbeでうまく対応できました。
スタッフとのやり取りは、スマホの音声認識アプリが大活躍したようです。
この当時はまだ、障害者差別解消法が義務化されておらず、合理的配慮はありませんでしたが、今後また同じような機会があれば、どんどん声をあげていき、主催者側の対応の変化に期待したいと思います。
最終審査でランウェイ
グループレッスンが進み、最終審査の動きの確認や概要、親子での歩き方の注意点や心得などを含めた対面レッスンが何度か行われ、一次審査に応募してからようやく(約1年)最終審査でランウェイを歩くことになりました。
グループレッスンもそうでしたが、ベビー部門は基本的に保護者と一緒に行動するので、ランウェイでのスタート合図や止まる場所、決めポーズの位置・秒数などは、事前に練習もしましたが、私が娘の視界に入るように位置を意識しながら呼吸を合わせていました。緊張で表情はこわばっていましたが、なんとか歩ききり、本番は大きな問題も無く終了しました。
(ちなみに、ランウェイ中央のポーズ決め位置のステージ前では、オーディションのスタッフが、目立つウチワを持って子供の目線が分かりやすいように工夫されてました)
このオーディションは、5歳以上になると保護者と離れ、出番までの長い時間をひとりで待ち本番もすべて自分のタイミングでやらなければならないので、もし5歳以上の挑戦だったら今よりもっと大変だったと思います。挑戦するタイミングが早すぎたかなと正直思っていましたが、逆にこの時期でよかったのかもしれません。もし、今後また挑戦するとなれば、本人のセルフアドボカシー力や情報保障を主催者側へ交渉する力なども必要になってくるだろうと思いました。

結果、親子共々緊張しながら挑んだオーディションでグランプリを獲得することができ、そこから約1年間キッズモデルとして契約し、活動することになりました。
※後日談…賞金総額100万円!と銘打っているオーディションだったのでちょっとワクワクしていましたが、グランプリが約30名ほどいたため、均等に一人約3万円の賞金をいただきました(‘∀`)
はじめての仕事
「よし、頑張るぞ!」と意気込んでみたものの、実際のところ、オファーはあっても平日実施や遠距離の現場が多かったり交通費が出ないなどもあって、ようやくの初仕事は関西にあるフォトスタジオでの七五三撮影でした。
今回、審査やレッスンを通して私が意識したことは「事前にルールと目的を説明し、これからどこに行って何をするのかを伝える」ことでした。
撮影の時も、事前に写真やイラストを見せながら「今日行く場所、さまざまな衣装に着替えてメイクや髪を整えてもらい写真を撮ること、スタッフを見てポーズを真似すること」などを手話で説明しました。もともとオシャレや撮影が好きな娘なので、この説明の後は泣いたり嫌がったりすることもなく、楽しそうに撮影されていました。
また、現場のスタッフにも事前に「耳が聞こえないこと」と「手話で受け答えすること」は伝えていましたが、基本的な対応として「伝えたいことがある時は目線を合わせる」「場所やモノなどは指差しすると分かりやすい」「して欲しいポーズがあれば実際やってみせる」ということを伝えておいたためか、スムーズに撮影できていたように思います。後半になると、スタッフも自然に「かわいい」「上手」「ばっちり」などの手話を覚えて、コミュニケーションをとってくれていたのが印象的でした。


ろう児としての撮影依頼
結局、さまざまな事情からキッズモデルとしての仕事は七五三の撮影が最初で最後になってしまいました。
仕方がないとはいえ、少し残念に思っていたところ、ある日「ぜひ娘を撮影したい」という連絡をいただいたのが横尾友美さんでした。

アーティスト(写真・映像・身体表現)
ろう者。長崎県出身、京都市在住。映画『LISTEN リッスン』に出演したことがきっかけで身体表現に目覚める。映像、写真、舞台などで ろう者としての感性、アイデンティティと結ぶ身体表現の活動を行う。扱うテーマは愛、ろう高齢者、オンガク、境界線、感情、解放、身体の線、女性。
経歴: 牧原依里・雫境(DAKEI)共同監督映画『LISTEN リッスン』(2016年)出演。谷中佑輔舞台作品『空気きまぐれ』(2023年)コラボレーター・出演。短編映像『わたしたちについて』(2023年)監督・制作・出演。第20回さがの映像祭大賞受賞
横尾さんは現在、全国で上映会が続いている、ろう者をテーマにした映画「わたしたちに祝福を」の監督・出演をされています。

お声がけ頂いただいた時は2023年の春でしたが、その後、横尾さんの個展や短編映画に出演させて頂きました。さらに、その短編「わたしたちについて」がさがの映画祭で大賞を受賞したことで、イベントや舞台挨拶に呼んでいただくこともあり、2023年~2024年は挑戦という意味で大変濃い年になりました。


大変恐縮でしたが、娘に声をかけたきっかけや撮影した際の印象を横尾さんに伺ってみました。
 チョビ輔
チョビ輔撮影したいと思ったきっかけや、実際撮影してみてどうだったかなど教えてください。

SNSでの投稿を見て、親子のやり取りや表現力が素敵だと思ったことがきっかけです。撮影をしてみて、表情や身体の動きなどがともて魅力的で、作品として出来上がった後も、観客の皆さんが娘ちゃんの自然体に惹かれる様子を見て、監督としてもとても嬉しく思っています。目力がすごく、仕草一つ一つに物語があり撮るたびにワクワクさせられました。想像以上に感動しました。
映画「わたしたちに祝福を」は、今後も全国各地で上映会が企画されています。お近くで開催される際は是非足をお運びください。
また、来る4月6日(日)には、短編映画のロケ地である三重県いなべ市の桐林館喫茶室でも上映会が行われます。映画上映に合わせて、短編の上映と栗田一歩さんの写真展、横尾さんのトークショーも予定しており、私たち親子も少し挨拶することになっておりますので、この上映会のレビューは、イベント終了後にまた記事にできたらいいなと思っています。
経験を通して感じたこと
娘は今5歳。コミュニケーション方法はずっと変わらず手話です。
今は撮影時より語彙力も増え、会話やコミュニケーションもスムーズになってきましたが、その分恥ずかしがったり気分が乗らないときには目線を合わせない、分からないことはバンバン質問するなどの子供らしい面も増えています。
私自身、経験値や知識を増やすことはとても大切だと思っており、一度でもやってみたことがあるという経験や記憶は、本人のその後の自信や環境改善につながると思っています。さまざまな人に会い、自分と他人との違いを理解し、共感をしながら、娘には自分の世界を広げていってほしいなと思います。
「ろう・難聴児の聞こえる親」としてアドバイスや話を記事にするのはとても難しいですが、今私が出来ることは、子供の出会いや経験値を増やし、それを繰り返し振り返りながら親子の会話を増やすことだと思っています。そのためにも、娘との共通言語である日本手話を日々学んでいかなければ!と改めて思いました。
さいごに
今回、キッズモデルへの挑戦を記事にしようと思った時、全国にいる他のろう・難聴児たちのさまざまな挑戦をもっと知りたいと思いました。実際にメディアやモデルとして既に活躍しているろう・難聴児もいますし、スポーツや芸術、勉学などさまざまな分野で前例を作りながら挑戦しているキッズたちがたくさんいます。
記事を読んでいる方の中には、チャレンジしたいことはたくさんあるけれど方法が分からない、プロとして活躍したいわけじゃないけどさまざまなことに挑戦しているという親子や、全国のろう・難聴児がどんなことに取り組んでいてどんな工夫をしているか知りたいという人がいると思います。私も知りたいなと思っています。
「働くろう者を求めて」ならぬ「挑戦するろう・難聴キッズを探して」みたいなシリーズが今後書けたらいいなと、漠然ながら思っていますが、個人情報や写真の使用許可など、子供を取り扱う記事は色々難しそうだな…とも感じています。
ぜひ、我こそは!と思う方がおりましたら、キコニワまでご連絡ください(笑)
最後まで記事を読んでくださり、ありがとうございました!