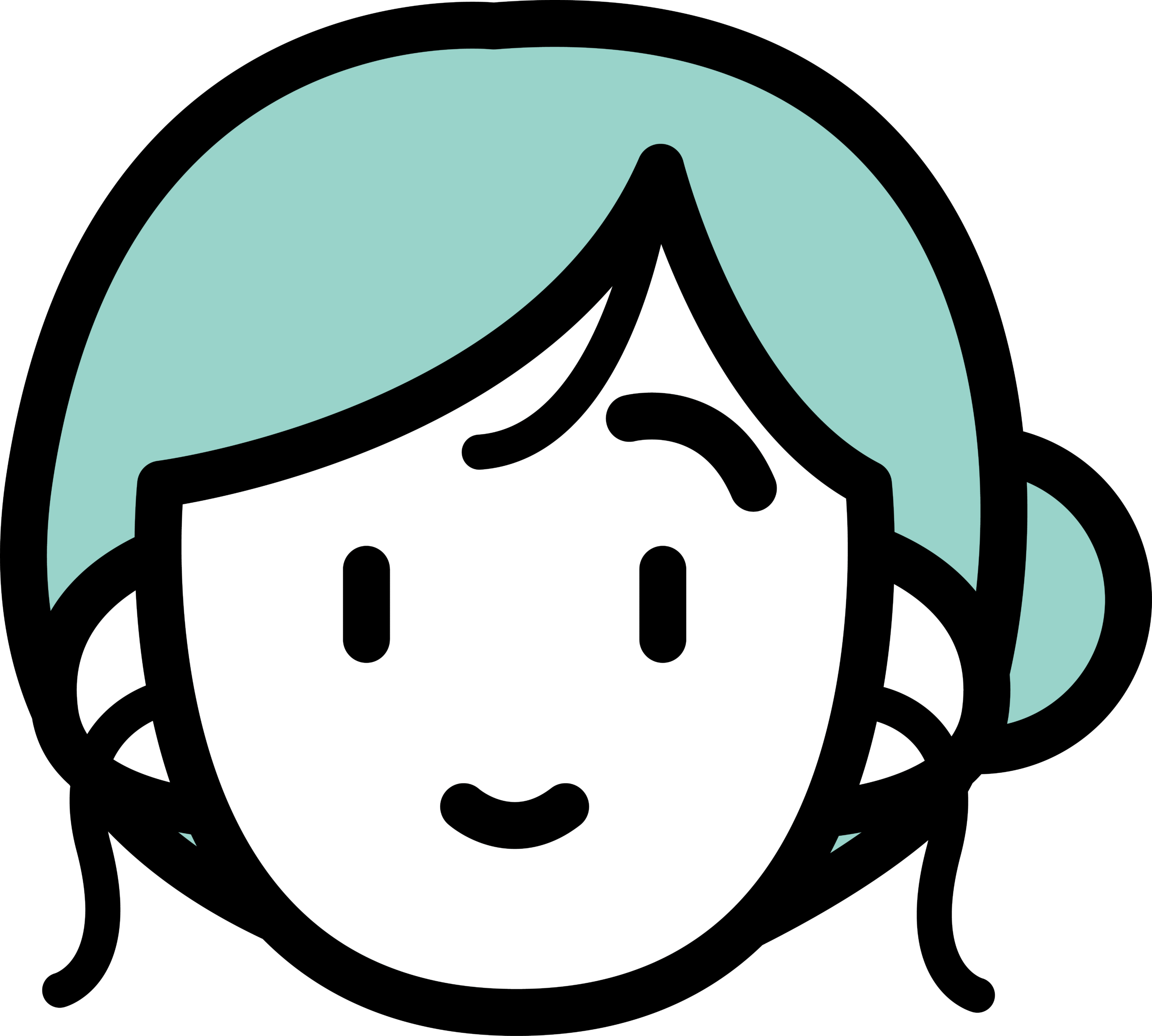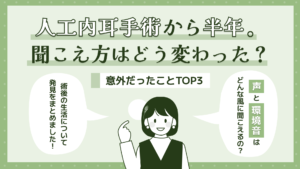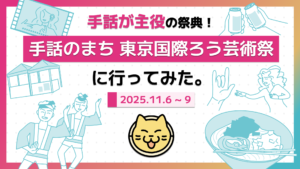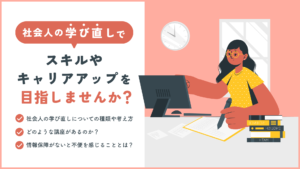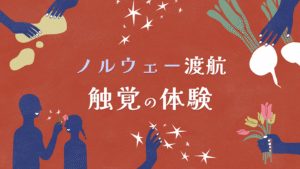今日もこのキコニワをご覧いただき、ありがとうございます。
初めまして、キコニワ新ライターのこゆんです。
今回は、私についての自己紹介を交えながら
「聴覚障害者が接客をすること」
についてお話をさせていただきます。
聴覚障害のお子様を持つご家族や、キャリアに悩む若者にとって、
視野が広がる情報になりますように。
私のこれまで
まず、私のこれまでを簡単にまとめると..。
幼少期:発達支援センターと併設された幼稚園に通う
乳幼児期:先天性の感音性難聴児として生まれる
小学生:普通学校に進学
中学生:聾学校に1年だけ在籍し、普通学校へ転校
高校生:見知らぬ土地での普通高校に進学
社会人:高卒で市役所の正職員デビュー
社会人②:3年半の勤務を経てインド渡航を機に退職し、接客業に転身
現在:紆余曲折を経て、介護職とライターでキャリア形成中
私なりに葛藤や孤独、不安、その中にある小さな喜びなど、
いろんな気持ちを感じながら進んできました。
少しずつこの一連の歴史を、
このメディアで発信させていただくことで、
「こういう人もいるんだ!」
と思ってもらえたら何よりです。
さて今日は、その中で接客業に転身した経験をお伝えします。
接客業への壁
実は、私は接客とは無縁の日々を生きていました。
私の聴力は、
・右耳は聾
・左耳の残存聴力(人の話し声が聞こえるレベル)
であり、最も特徴的なのが
「聴力のわりに、語音明瞭度が半分以下」
であることでした。
“音は聞こえるのに、何を言っているのかわからない”
という、なんとも言えないグレーゾーンの立ち位置にいます。
そしてこの中途半端さは、
私のコミュニケーションに強く影響を与え、
歯痒さがある故に
「接客」へのハードルを高くさせていました。
バイトに落ちた過去
その証拠に、私は学生の時、バイトに4回落ちた経験があります。
・ホテルの洗い場
・寿司屋の調理
・ライブ会場の設営運搬
・引っ越し
これにより、
「私はバイトにも合格できないんだ」と、そんな思い込みが生まれました。
面接の際に自分の障害のことを伝えた際は、
「あーー。うちって、けっこうコミュニケーション取るんですよ。
だから正直いうと難しいんじゃないかなって。
周りとの関係性もあるし。
「引っ越しバイトだとチームプレーが大事なんです。
危険性もあるし、効率の良さが求められるので….」
こんな感じで言われ、その瞬間に
「もう検討される余地もないんだな」と、傷ついたことは今でも覚えています。
退職への葛藤
こんな経験があったので、当時、
高卒で受かった市役所を退職するか否かの分岐点だった私は、
頭を悩ませました。
「私が働ける場所は今の場所しかない。公務員じゃないと、自分は生きられない。」
本気でそう思っていたので、
公務員という身分からバイト生活への転身には
かなりの勇気が必要でした。
しかもその時は
退職した後の働き先も見つかっていません。
さらに、今では
・前向き
・フレンドリー
・コミュ力が高い
なんてことも言われますが、昔はそうではなかったんです。
ものすごく根暗で、
特にいじめられているワケでもないのに、
「みんな私と話したくないんだと思う」
と、感じていたぐらいでした。
友人の紹介
私は、そんな状態の自分の今後に苦しんでいることを、
高校の親友に打ち明けたのです。
すると、その友人はじっと話を聞いてくれたあと
こう言いました。
「もうこゆんの中で結論は出てるんじゃない?」
「今月末で市役所やめよっか」
「辞めたら、〇〇で働く?」
そう、その友人は
私の背中を押して、バイト先を紹介してくれたのでした。
そこはレストラン。
「私にできるのかな?」
そう自信なさげに言う私に、彼女は
「外国人たくさんいて、話通じない人ばっかりだよ」
「外国人のバイトの人と話通じないこと多いけど、なんとかみんな頑張ってる」
「接客」
ここでこれまで無縁だった「接客」が
急に身近なものになりました。
身近になった途端、
自分の中でこんな思いが湧き上がったのです。
「接客、やってみたい。」
ついに初めての…
接客に挑戦してみたい旨をはっきり伝えると、
彼女はすぐに
そのバイト先に連絡をとってくれました。
そうしてそのお店と繋がり、
責任者から来たメッセージは…
「接客をやりたいならそれを尊重します。
間違いはしょうがないから、そこは支える。
君がどうやれば馴染むか?できるようになるか取り組もう」
ここで、今までの私の概念が崩れました。
「あぁ。こんなこと言ってくれる人、いるんだ。」
その安堵感は今でも忘れられません。
ただ、そこでも不安はありました。
「聞こえないっていうと、印象悪くなるんじゃないかな?」
そう彼女に聞くと、
「いや言葉通じない外国人が働いてて、こゆんが働けないことなくない?」
「確かにそうか…」
そう納得し、レストランの副支配人と面接を行った結果…
「うちに来ていいよ、いつから来れるの?」
と、お言葉をいただくことができたのでした。
接客時に工夫していたこと
ここからは、私が接客時に工夫していたことをお伝えします。
①難聴バッジをつける
②補聴器を目立たせる
③メニューは指差しで注文してもらう
④配膳のベルは聞こえないことを周知する
⑤面接時に「自分の耳について」をまとめたパンフレットを渡す
これらを踏まえたうえで、あとは見えてくる課題に対しての
検証と実践の繰り返しです。
課題は以下のとおりでした。
・オーダーを料理人に口頭でしっかり伝えることが難しい
・耳が悪い分、お客さんの動きに常に目を配っているために、疲れやすい
・従業員同士のちょっとした雑談が聞き取れず、リフレッシュしづらい
・後ろから呼ばれていることに気づかず、お客さんを不愉快にさせてしまった
それぞれの対策を、これから細かくお伝えします。
【オーダーを料理人に口頭でしっかり伝えることが難しい】
→比較的余裕のある時間なら、しっかり自分で伝えていました。
料理人たちがピリピリしていたり、回転率がめぐるましい時間帯は
別のスタッフにお願いして、バッシング(※)を積極的にやるなどしていました。
※お客様が食事を終えた後のテーブルを片付け、次のお客様を迎えられる状態に整える作業のこと
忙しさに合わせて、
・自分で伝えてもいい時
・代わりにスタッフにお願いする時
を使い分けて、全体の流れを滞らせないように意識していたつもりです。
【耳が悪い分、お客さんの動きに常に目を配っているため、疲れやすい】
→これは私の体力の問題です。帰宅してからの過ごし方に気を使っていました。
できるだけその日のうちに疲労を解消できるようにし、
毎日をリセットする習慣は今でも続いています。
【従業員同士のちょっとした雑談が聞き取れず、リフレッシュしづらい】
→自分にとって会話しやすい環境の時に、
周りのスタッフとの関係性を縮めることに注力していました。
料理を厨房から受け取りに行く時の、ちょっとしたスタッフ同士のおしゃべり。
バッシング中のちょっとした会話。
私の場合、手を止めてしっかり顔を見合わせないと話が理解できません。
そのため、休憩時間や閑古鳥が鳴いている時間帯など、
落ち着いている環境の時に、積極的に周りに話しかけていました。
その結果、人間関係で悩むことはなかったと思います。
一方で、
自分にとって弱い環境にいる時は
無理に関わろうとせず、大人しく静かに過ごす
ことで、自分のバランスをとっていました。
逆に関係性が縮まると、こんなことがあります。
自分が苦手な環境でも、相手側からなんとか伝えようと、
一生懸命話してくれる人が現れてくるんです。
【後ろから呼ばれていることに気づかず、お客さんを不愉快にさせてしまった】
→その状況に気づき、代わりに対応してくれたスタッフに感謝の気持ちを伝える
ありがたいことに、スタッフが代わりに
お客さんと話してくれていました。
そこで大事なのは、
そのスタッフに感謝の気持ちを伝えることです。
もしくは、周りのスタッフが自分に目線が集まったことを合図に、
「あ、今お客さんに呼ばれてるのか」
と、受け取って行くこともありました。
そのお客さんに1番近いスタッフが私でなのかどうか、
フロア内の縮図をイメージして、
「今自分はどの位置にいて、他のスタッフはどんな位置にいるのか?」
をかなり想像しながら、周りを見ていました。
さらには、周りの目の動きにも敏感に察知していたんです。
自分の視界内にいるスタッフの目線が、
自分の見えていない方向へと動いた瞬間を捉え、
「後ろから誰か呼んでるのかも」と想像することも意識していました。
仕事の見つけ方
この接客業への転身を踏まえ、
私の中で、聴覚障害者がいい仕事を見つけるためのコツが見つかりました。
あくまで私のやり方なので、
自分なりの見つけ方を模索してください。
- 柔軟性のある職場
- 「人」を通した紹介
- 「体験」から始めてみる
- 自分なりの自己表現の仕方を持つ
- 自分の取り扱い説明書を分厚くする
この5つさえあれば、
キャリア形成に対する悩みはだいぶ解消されると思っています。
①柔軟性のある職場
具体的には、
・先入観なく、フラットな視点であること
・なんでも面白がれること
・新しい情報を取り込める余裕があること
を指します。ハンデがあるゆえの工夫を編み出しやすい環境になるため、
とても安心して仕事ができるはずです。
②人を通した紹介
私の場合、大学にいかなかったことや自身の昔の消極的な性格により
幅広い人との交流は少ないタイプでした。
しかし今回のように、友人の紹介のおかげで
「自分を知ってもらう」
手間のハードルが下がったんです。
「紹介できる人」になれる自分になることで、
「聞こえない人」としてではなく、
「あの人が紹介した人」とみなされる
ことは大きい要素です。
紹介されるに値する人間性を磨く
ことも大事だと気づきました。
そうすれば声はかかるし、仕事は舞い降りてくるはずです。
③「体験」から初めてみる
ここはまた別の記事で詳しく紹介しますが、
スキマバイトアプリ「タイミー」で職業経験を積むこともいいかも知れません。
自分も働いてみて良さそうだと感じたら、
そこの責任者と話して雇用の話を聞くのがおすすめです。
④自分の取り扱い説明書を分厚くする
自分はどういう時にききづらく、
どんな発言がききにくいのか。
男性の声と女性の声、
どっちがききとりやすいのか。
今の自分の気力や体力はどれぐらいか。
それに応じて、どう耳を使うか。
など細かく細かく、分析していきましょう。
⑤自分なりの自己表現を持つ
ここは、今も模索中ですが、
私の場合は、文字や芸術での表現が最も適していると感じています。
もし自分の言葉がうまく伝わらないと感じているなら
それは単純に、イラストや動画などの視覚で伝えるのが
向いているだけかもしれません。
中には、聞こえない人でも
とても話すのが上手な人もいますから。
自分にあった表現の仕方で、キャリアをつくりましょう。
その魅力に必ず気づいてくれる場所があります。
まとめ
以上が、私が接客業への転身を踏まえての経験です。
・言いたいことがうまく伝わらずにイライラさせてしまうこと
・「大した話じゃないから聞かなくて大丈夫」と言われた時の孤独感
・周りの話が分からずに、ひっそりと自分が透明人間になる感覚
様々なことがありました。
しかし、そうした経験があったからこそ得られるものは大きいです。
それは、
「人として強くなれるチャンスがあること」
「ちょっとやそっとじゃ倒れない、考え方や工夫を編み出せること」
でした。
自分のキャリア形成にどんどん挑戦し、自分の可能性を信じてみてください!