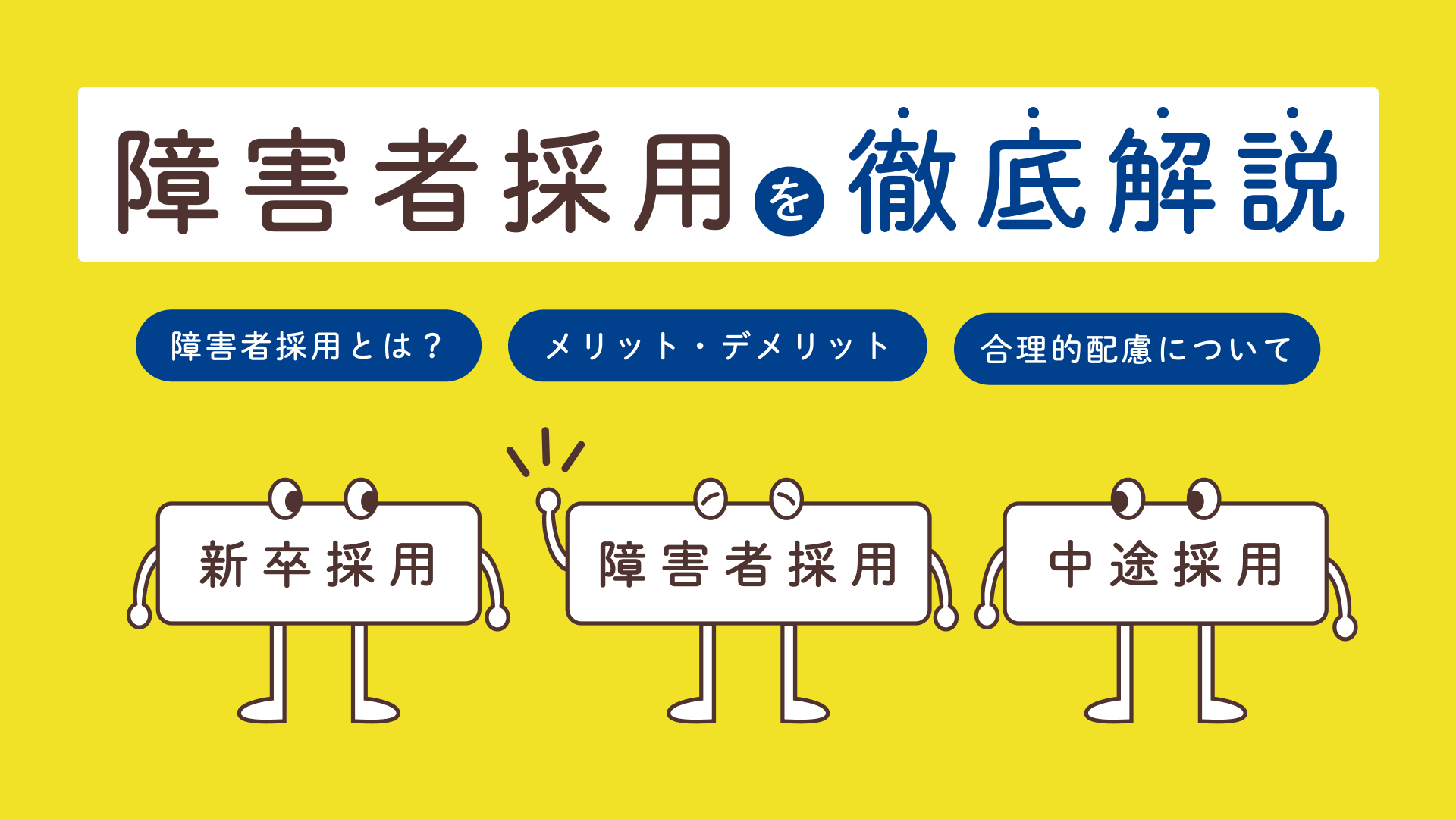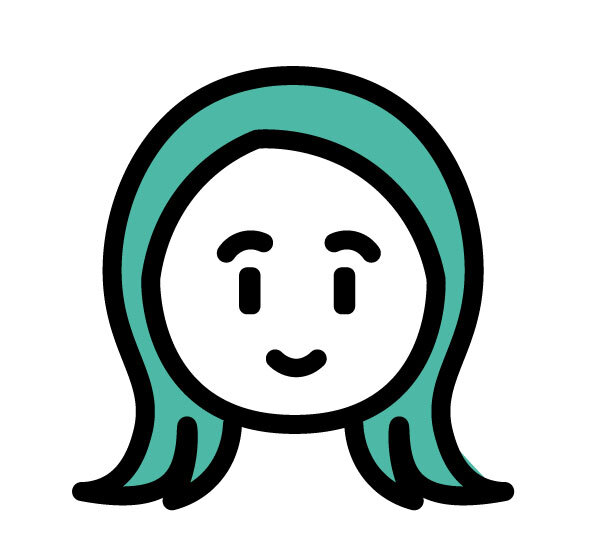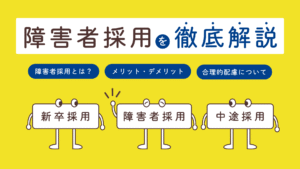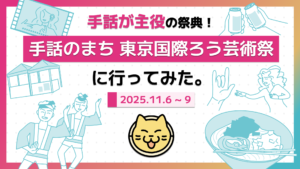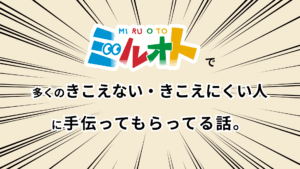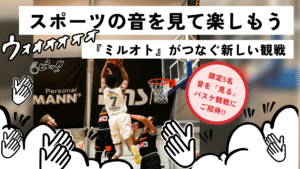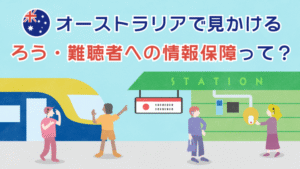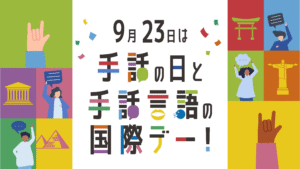こんにちは!
転職などで働きたいと思ったとき、企業の採用情報や求人サイトを見ると思います。その中で、『新卒採用』『中途採用』のほかに『障害者採用』という枠もあります。
障害者採用とは、障害者雇用促進法に基づき、企業が法定雇用率を満たすために設けられている採用枠です。これにより、多くの企業が障害のある人を雇用し、職場での理解や対応が進んできました。
働きやすい環境を選ぶことは、もちろん就活の重要なポイントです。
ここでは、障害者採用や合理的配慮の基本を理解して、安心して働ける職場探しの参考にしましょう。
障害者採用と一般採用との違い
1. 障害者手帳の所持が必要
障害者採用は「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」を持っている方のみ応募できます。
聴覚障害の場合は「身体障害者手帳」が必要です。軽度・中度の難聴や片耳難聴で手帳を取得していない場合は、障害者採用に応募できません。
2. 採用の判断基準が多い
能力や経験、学歴に加え、障害の特性や必要な支援についても考慮されます。
聴覚障害者の場合、聞こえの程度(例:全く聞こえない/補聴器で会話可能など)、コミュニケーション手段(手話、筆談、読唇、音声認識アプリなど)、会議や電話対応で必要な配慮を自分で説明できるかが重視されます。
3. アクセシビリティの整備
聴覚障害者が働きやすいように、以下のような配慮が求められます。
- 会議での手話通訳、音声認識アプリ
- チャットツールやメールなど文字ベースの環境
- 緊急時の視覚的な警報装置(パトランプなど)
- オンライン会議での字幕機能
障害者採用のメリット
配慮を受けながら働ける
電話対応業務の免除、会議での手話通訳や音声認識アプリの導入、重要な連絡の文字共有など、特性に応じた配慮を受けられます。転職サイトやハローワークを通して入社すると入社後もジョブコーチなどのサポートを受けられる場合があります。
多様な視点で組織に貢献できる
聴覚障害者は音声情報だけに依存せず、視覚的な情報伝達を重視する経験から、資料の見やすさや業務フローの整理などに貢献できることがあります。こうした取り組みは職場全体の情報共有を改善し、組織の多様性や創造性を高める効果があります。
障害者採用枠の存在
大手企業を含む多くの企業で障害者採用の枠が設けられています。専用の選考ルートが用意されている場合もあり、一般採用とは異なる評価基準で選考される機会があります。
障害者採用のデメリット
一般採用より求人数が少ない
正社員募集は一般採用に比べて少なく、契約社員からのスタートが多い傾向にあります。ただし近年では、ITエンジニア、デザイナー、Webディレクター、経理、人事など専門職の求人が増えています。特にIT業界は人材不足が続いており、障害者採用でも専門職募集が活発です。
一方で、営業職やカスタマーサポートなど電話対応が主要業務の職種は応募が難しい場合があります。ただし、チャットやメールでの対応を導入する企業も増えており、そうした企業を選ぶことで選択肢が広がります。
2つの合理的配慮
障害者差別解消法(社会全体)
教育、就労、生活など社会のあらゆる場面で差別を禁止し、「共生社会」を目指す法律です。2024年4月から、事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました。
聴覚障害者への配慮例:
- 駅での遅延情報を電光掲示板などで配信
- 店舗やレストランでの呼び出しを番号表示で可視化、振動ベルで対応
- 窓口などで指さしシートを配置
- 医療機関での診察呼出を番号表示で行う
障害者雇用促進法(職場)
職場での差別を禁止し、働きやすい環境を整備する法律です。
聴覚障害者への配慮例:
- 会議で手話通訳や音声認識アプリを導入
- 重要な連絡は口頭だけでなくメールやチャットでも共有
- 電話業務の免除や代替手段の提供
- 緊急時の視覚的警報装置の設置
- 従業員向けの理解促進研修
配慮導入の準備期間
企業によっては、配慮の導入や従業員研修に時間がかかる場合があります。自分のことを書かれている“トリセツ”を渡す、緊急時の視覚的な装置(パトランプ)の設置が難しければ、肩をたたくなど工夫するのもひとつの方法です。
障害者手帳を所持しない方への配慮
軽度・中度の難聴や片耳難聴など、障害者手帳を持たない場合でも、一般採用で合理的配慮を求めることができます。障害者差別解消法は手帳の有無に関係なく適用されるため、会議での議事録作成、重要な連絡の文字共有、1対1での面談設定などを相談できます。
柔軟な働き方の広がり
2025年10月からは育児・介護休業法の改正により、3歳以上の子を育てる親や家族を介護する労働者に対して、テレワークや時差出勤など柔軟な働き方働き方を柔軟に整える義務があります。
この改正は障害の有無に関わらず適用され、社会全体で柔軟な働き方が広がることが期待されます。
まとめ
聴覚障害者の就職活動では、障害者採用と一般採用のどちらを選ぶかが重要です。
障害者採用のポイント:
- 配慮を受けながら働ける
- 手話通訳や字幕、文字ベースのコミュニケーション環境が整う
- ITや専門職の求人が増加中
- テレワーク普及で環境が改善しつつある
聴覚障害の特性や状況は一人ひとり異なります。聞こえにくい、片耳のみ聞こえる、途中で失聴した、全く聞こえないなど多様です。コミュニケーション方法も手話、読唇、筆談など人によって異なります。
就職活動では、自分の聞こえの状態や必要な配慮を明確に伝えることが成功の鍵です。
- どんな会社で働きたいか
- 自分がやりたいことは何か
- その会社で何を実現したいのか
こうした自己分析を丁寧に行い、自分に合った職場を選ぶことで、自分らしく働ける環境を見つけることができます。