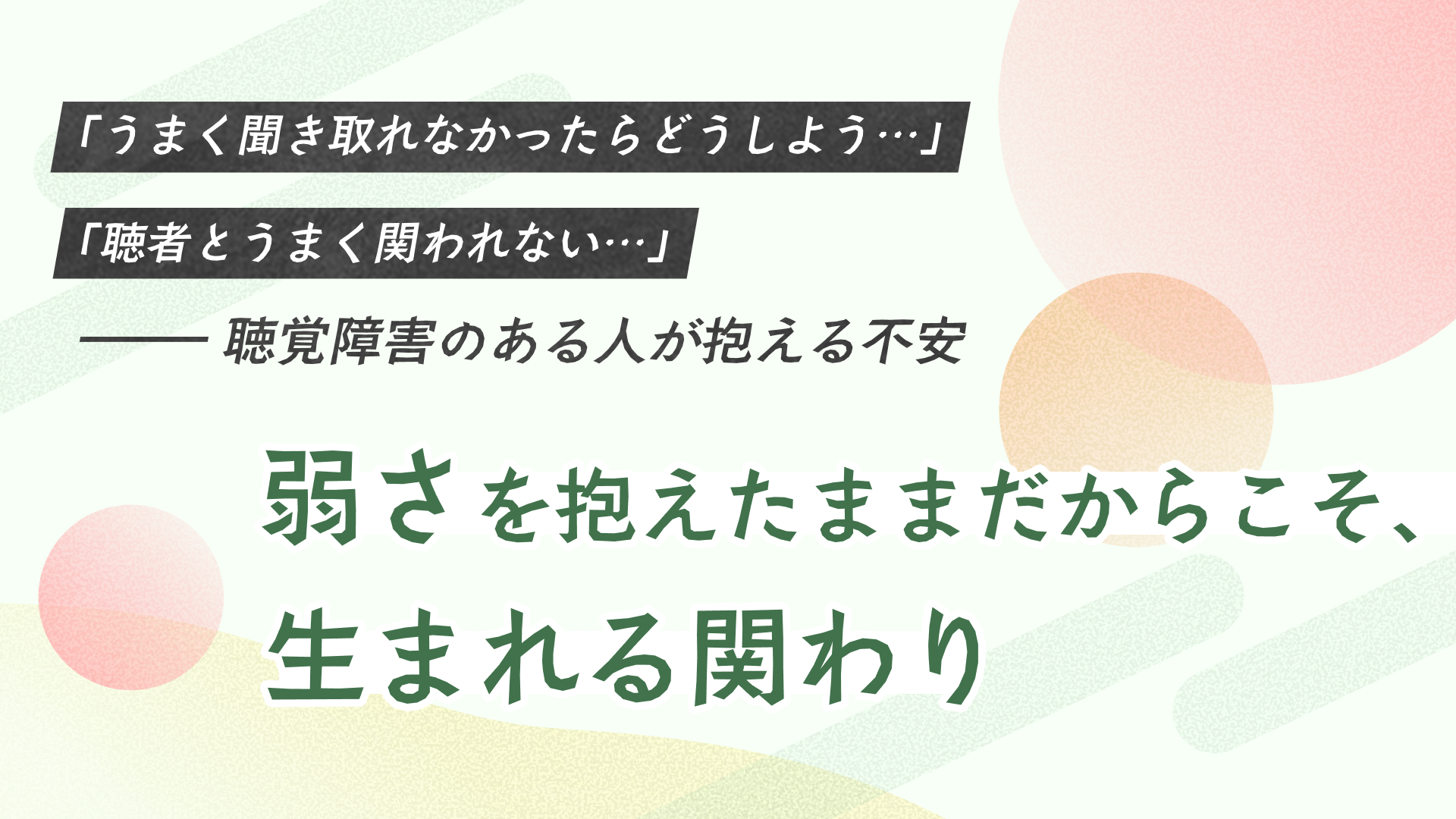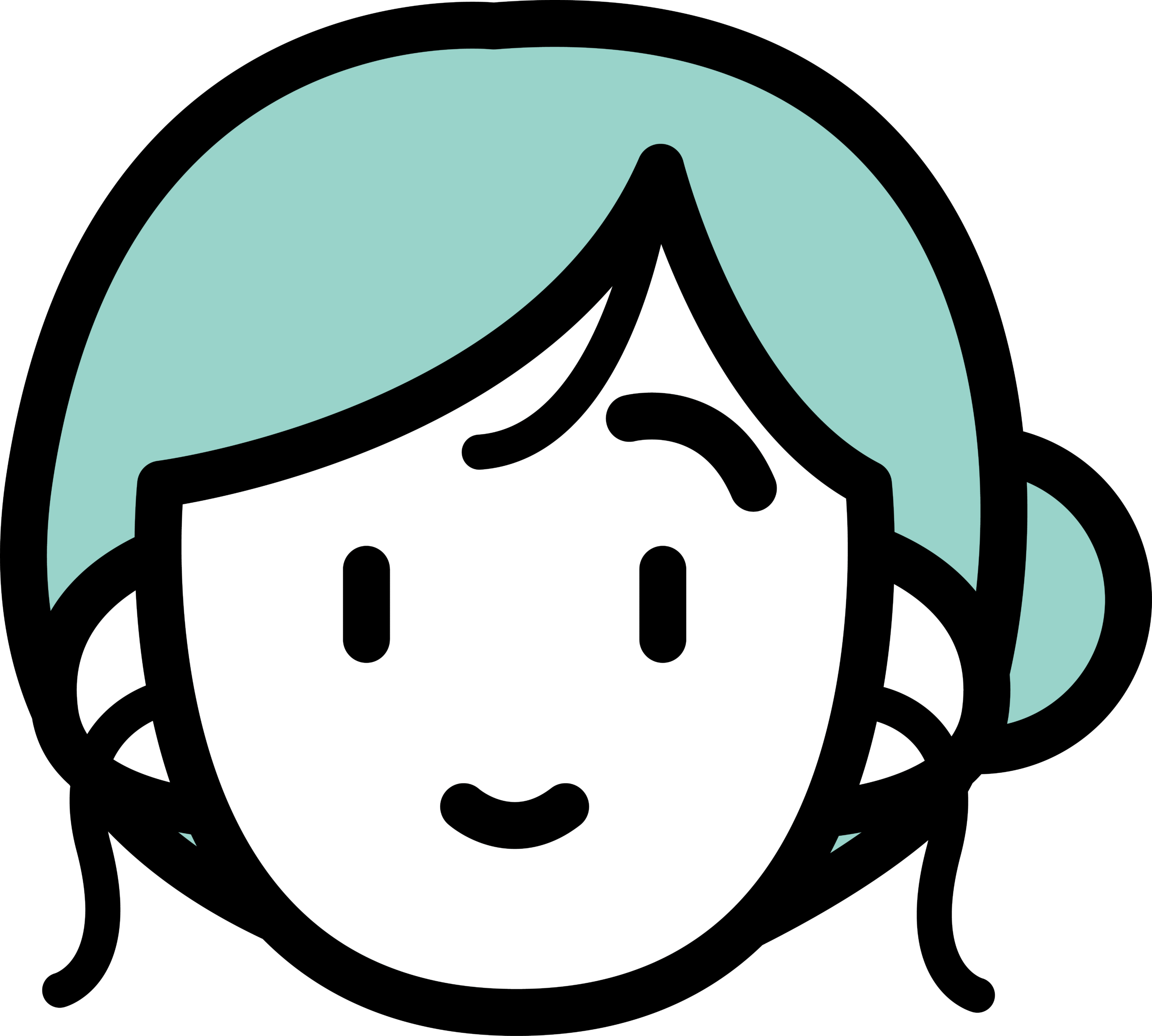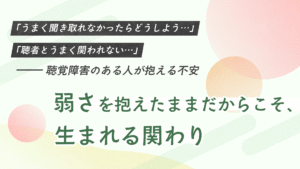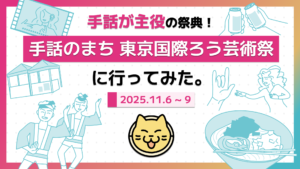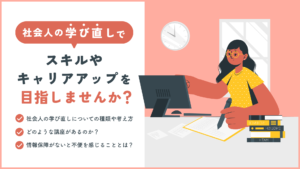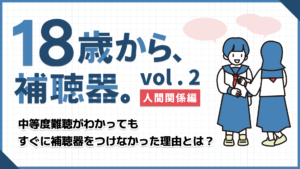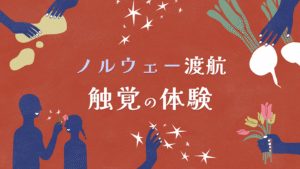今日もキコニワの世界に入っていただき、
ありがとうございます。
ライターのこゆんです。
さて、実は前回の初回記事を読んでくださった方から
こんな質問がありました。
「人に対して警戒心が強く人見知りだったこゆんさん。
そんな人がなぜ、フレンドリーで気さくと言われるまでになったのですか?」
自覚はないのですが、どうやら私には
「明るくてフレンドリー」とみなされていた時があったようです。
そこに焦点を当てた経験談を交えながら、今回は
をお伝えさせていただきます。
こゆんの歴史
幼少期:母の背中に隠れていた私
小さい頃の私は、
とにかく母の背中にぴったりとくっついている子どもでした。
特に、スーパーでレジに並んでいるとき。
店員さんに自分の補聴器を見られるのが
嫌でたまりませんでした。
小学生:関わりたいけど動けなかった
でも心の奥には、
・もっと人と仲良くなりたい
・輪の中に入りたい
こんな気持ちが確かにありました。
友達が楽しそうに遊ぶ姿を遠くから見ていて、

「私も入りたいなぁ」
そう思っても、
勇気が出なくて動けなかったのです。
遊ぶときは
- 2~3人
- マンツーマン
- 大勢の年下の1.2年生
がお決まりでした。
また、祖父母の家に帰省し、
従姉妹たちがワイワイ遊んでいる時のことです。
そこでも私は
- 母の近くにいる
- 黙々と1人で本を読む/勉強をする
ような子でした。
年末年始の親戚の集まりでさえ、
にぎやかな環境に居心地が悪くて仕方なかったのです。
今思えば
「自分が聞こえにくいことを認めざるを得ない環境」
否応なく、心がえぐられます。
だからこそ、1人になることを自ら望んでいたのでしょう。
つまり、私は
自分が聞こえづらいことを受け入れたくなかったのです。
そのため、周りからは
「大人しいよね」
「人見知りだよね」
とよく言われ、
私自身も

「自分は人と関わるのが得意じゃない」
と、思い込むようになっていきました。
- 仲良くなりたい気持ち
- 1人を望む自分
このギャップに
もどかしさを抱えていたのです。
「関わりたいけど不安…」
という感覚──
これは、聴覚障害のある方が
聴者と接するときの気持ちと重なる部分があると思います。
「うまく聞き取れなかったらどうしよう」
「誤解されて気まずくならないかな」
「場の空気感を壊さないかな」
──そういう不安が先に立って、
一歩が踏み出しにくいのではないでしょうか。
中学生:小さな応答から広がる関わり
中学生になっても、
その状況は大きく変わりませんでした。
当時は、通常学級とほかに
特別学級にも在籍していました。
不本意ですが、1人ぽつんと
特別学級にいる時間も多かったのです。

それもあってか、内心では
「もっと人と関わりたい」
という気持ちがどんどん大きくなっていきました。
そうして、文化祭や委員会活動など、
人と協力する機会が増えるにつれ、こんな変化がありました。

声をかけられたときに、
精一杯それに応えようとし始めたのです。
これは、聴覚障害のある方が
人と関わるときにも大切なポイントだと思います。
最初から完璧に理解し合おうとしなくてもいい
・まずは声をかけられたことに応じる
・自分のわかる範囲で関わってみる
そんな小さな一歩が次の会話につながっていくのです。
人と協力して達成する経験は少しずつ、
「関わるのも悪くない」、そんな実感を与えてくれました。
※それでも、自分から積極的に人の輪へ入るのはまだ難しく
「仲良くなりたいけど勇気が出ない…」
そんなジレンマを抱えていました。
高校:変わらなきゃ終わっちゃう
大きな転機は高校時代に訪れました。
知らない土地で生活することになり、
高校生活が始まったのです。
「このままじゃ3年間ずっと1人で高校生活が終わってしまう…」
強い危機感と焦り。
これを入学式でひしひしと感じました。
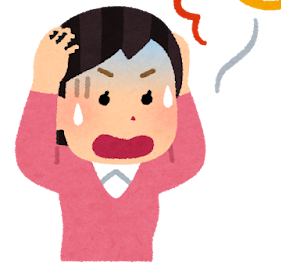
知り合い0の環境で、1学年240人です。
毎年のクラス替えでは、
新しい人間関係を都度築かなければいけません。
さらに、
- これまで自分を気にかけてくれていた友人
- 情報保障をしてくれるサポーターの先生
が全くいない環境に置かれたことで、
「自分から行動しなければ何も変わらない」
「自分から情報を取りに行かないといけない」
という現実を、周りから突きつけられました。
そこで、私は小さな挑戦を重ねていきました。
- 隣の席の人に「この授業難しすぎない?」と声をかける
- 「先生、何言っているか聞き取れないです」と発言する
- グループ活動のときに一言だけでも意見を言ってみる
- とにかく、先入観なしに誰とでも気さくに話してみる
ドキドキだらけの行動でしたが、それを積み重ねることで
少しずつ人との距離が縮まりました。
「とりあえず、仲良くなっておく」

このスタンスは、自分にとって
「情報保障」の土台となりました。
聴覚障害者にとっての「小さな挑戦」
聴覚にハンデのある方は、聴者との関わりの中で
似たような壁に直面するかもしれません。
「聞き取れなかったことをもう一度言ってもらうのは悪いかな」
「話を途中で遮って、聞き返したら嫌な気持ちになるかな」
「たいした発言できないのに、輪に入っていいのかな」
など、不安は尽きないはずです。
けれど、小さな挑戦──例えば
「もう一度言ってもらえますか?」と伝えてみる
「口元を見せてもらえると助かります」とお願いしてみる
──それが相手との距離を近づけるきっかけになります。
ポイントは
相手側に「あなたに協力してあげたい」「配慮したくなる」
そう思わせられる自分になることです。
気づき:「見られ方」より「安心感」
「自分をどう見られるか」を気にするより、
「相手に安心してもらうこと」の方が大切
これが、高校時代に学んだことでした。
聴者と接するときにも、
同じことが言えるのではないでしょうか。
相手に「どう思われるか」を気にするよりも、
「どうすればお互いに安心できるか」を考えて伝える
その姿勢が、結果的に
「話しやすい人だなぁ」
「関わりやすいなぁ」
と、思ってもらえることにつながるのだと思います。
社会人:共感力が強みになる瞬間
社会人になってからも、
この考え方は私の人との向き合い方の軸になりました。
旅を通し、

公務員として、
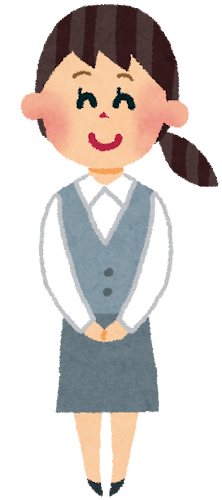
ホールスタッフや介護士として


多くの人と関わり続けてくると、
相手に安心感を与えることが
一番大切だと感じてきました。
聴覚障害のある方が聴者と接するときは、
まずは相手に安心してもらう工夫が大切です。
こちらが構えていると、相手も構えてしまいます。
だからこそ
- 「私はこういう配慮があると助かる」と素直に伝えること
- 「自分はこういう人です」と表現する手段を持つ
これは、相手にとっても安心材料になるのです。
今の私:弱みを力に変える
明るくて気さくな性格になった=
人見知りの自分を克服した
ではありません。

むしろ
「人見知りな自分」を否定せず、
相手との距離感に敏感な自分
を活かしてきた結果だと思います。
これは、聴覚障害者が聴者と関わるときにも
大事にできる視点です。
弱みだと思っていた
は、
に変えていけるからです。
まとめ:安心感を与え合う関わりへ
振り返ってみると、人見知りの私に変化ができたのは、
小さな挑戦と小さな意識が積み重なったから
でした。
聴覚障害のある方が、聴者と関わるときに大切なのは
「完璧に聞き取ろうとしないこと」
「少しずつ自分のやり方を伝えていくこと」
だと思います。

「人見知り=弱み」ではなく
「人を大切にできる力」に変わったように、
「聞き取りにくさ」も
「お互いの理解を深めるきっかけ」になり得ます。

母の背中に隠れていて警戒心ビンビンだった子が、
こうして人と関われるようになったのですから。
不安を抱えながらも一歩ずつ進んでいけば、
人と関わることは案外怖くありません。
そして、誠実に接することを忘れないことです。
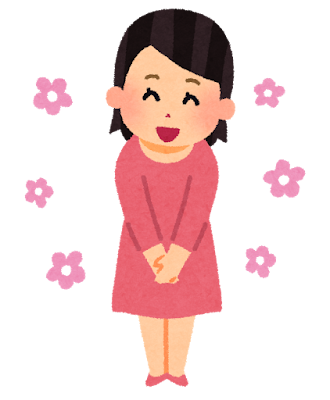
そうすれば社会、すなわち人との関わりは
きっと温かく豊かなものに変わっていくと信じています。
これからも私は、自分の過去を糧にして
「安心感を与えられる人」であり続けたいです。
また、
これらを、今後も多くの出会いや経験を通して
意識していきます。
みなさんも、不安と一緒に
小さな挑戦を続けていけますように。