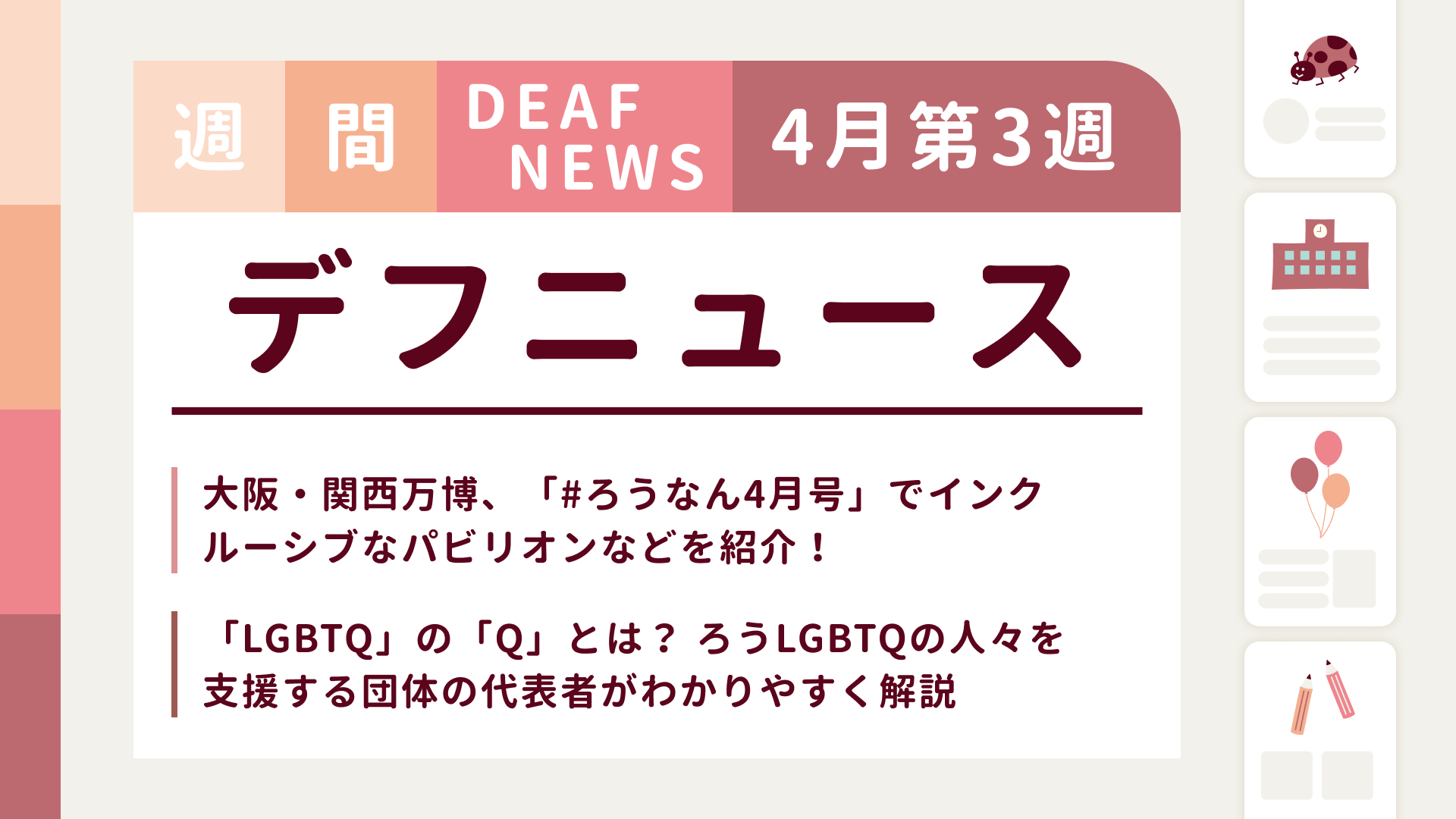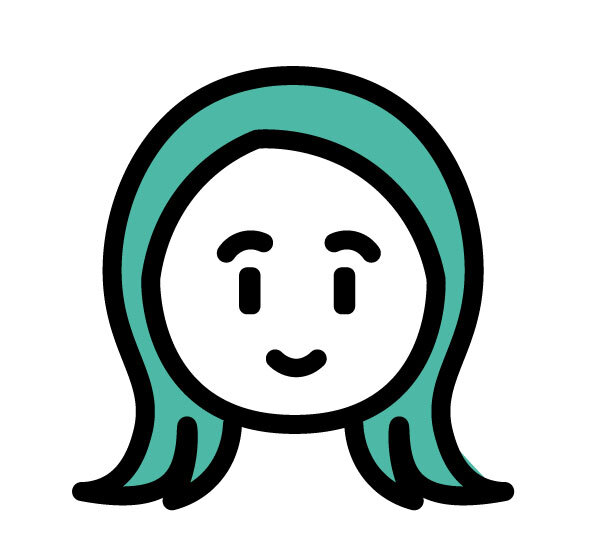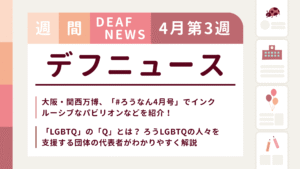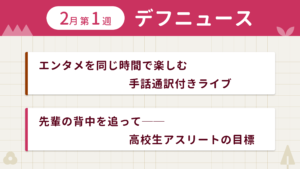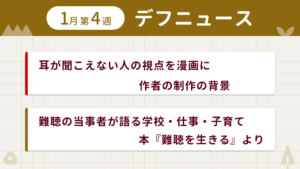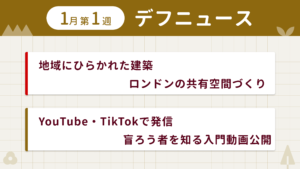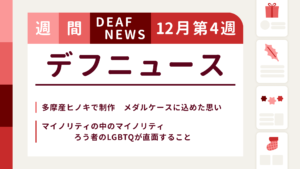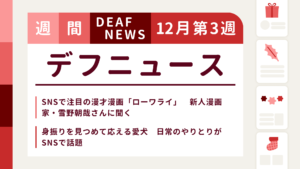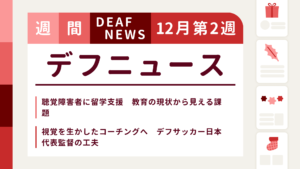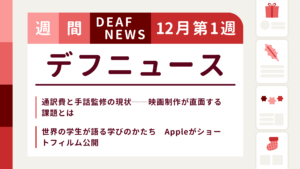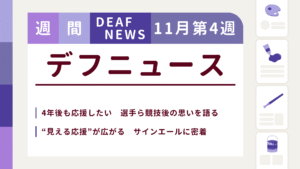こんにちは🌸
大阪・関西万博が始まりましたね!もう行きましたか?さまざまな国や地域の文化に触れたり、未来の技術に出会えたりするのが万博の魅力!行く予定のある方も、楽しみですね✨
さて、今週のニュースは7つご紹介します!
大阪・関西万博、「#ろうなん4月号」でインクルーシブなパビリオンなどを紹介!
開催中の大阪・関西万博について、NHKの「#ろうなん4月号」が放送されました。その放送内容を記事で紹介しています。開催する前に、誰でも楽しめるインクルーシブを目指して、聴覚障害者や視覚障害者と議論を重ねて作られたパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」。他に、音声アナウンスの文字化、案内のときの新しい支援ツールも導入されています。


聞こえない子どもから大人まで楽しめる工夫が満載とのこと。このときは開催前の情報でしたが、さまざまな意見を取り入れて、さらにパワーアップしていることでしょう。行く予定のある方は、ぜひ楽しんできてください!
「LGBTQ」の「Q」とは? ろうLGBTQの人々を支援する団体の代表者がわかりやすく解説
ろうLGBTQを支援する団体・「Deaf LGBTQ Center」代表の山本芙由美さんが、LGBTQについて、4つの性だけでなく、もっとさまざまな分類があること、それを示すのがLGBTQという「Q」を加えた表現と解説しています。また、LGBTQの関連用語やそれ以外の用語、課題や取り組みも紹介しています。


「LGBTQ」については知っていましたが、「Q」が何を示すのかはこの記事を通して初めて理解できました。世界のさまざまな取り組みも紹介されていて、背景や困難さについても知ることができました。
東京都、区報の特集で”手話と生きる”ろう者の1日の生活を紹介
東京都目黒区は手話言語条例が令和7年度4月1日に施行しました。目黒区の広報では、特集「手話と生きる」手話を第一言語とするろう者、佐藤八寿子さんの日常生活を紹介しています。また、活用しているサービスも紹介しています。編集後記もあわせてご覧ください。
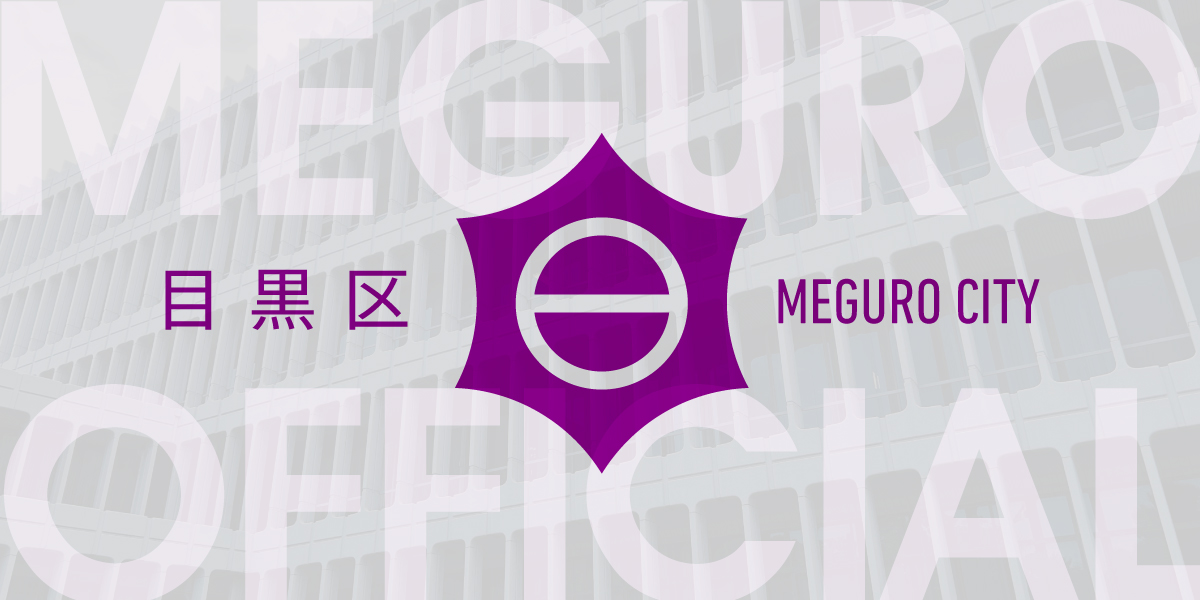

素敵に紹介されていて、魅力を感じました!編集後記にあった「交流しようとする気持ちが大事」という言葉が印象的でした。私も、聴者の方が手話が分からなくても「お話したい」「交流したい」と声かけてくださることがあり、その気持ちがいつも嬉しいです!
「特別な配慮ではなく、当たり前の基準へ」映画のバリアフリー上映
バリアフリー上映は増加傾向にありますが、対応作品はまだ少ないということが分かりました。資本力の大きい大手(東宝、東映、松竹、KADOKAWA、日活)は50%以上対応しているが、それ以外では14%程度にとどまっています。支援制度の活用や「当たり前」とする意識改革が課題とされています。


記事では円グラフが使われており、とても分かりやすく解説されていました。何より驚いたのは、映画作品の数が非常に多い一方で、バリアフリー上映がごくわずかしかないという現状です。
NHK、「手話で楽しむ✖️探検ファクトリー」放送
4月23日(水)20時から「手話で楽しむ✖️探検ファクトリー」が放送されます。漫才コンビ”中川家”とお笑い芸人”すっちー”が、兵庫県伊丹市にある畳工場を探検!最新技術と職人技を融合した畳づくりの現場を、手話で紹介します。


1300年前から続く畳文化。時代の変化に合わせて新たな技術を取り入れつつ、職人技にもこだわる姿勢が魅力的ですね!見逃し配信では「お札工場」(4/23まで)も紹介されています。ぜひご覧ください!
本「だいじょうぶ! ― 勇気を出せば、世界はもっと広がる ―」出版、”自分らしさを大切に”
4月25日に本「だいじょうぶ!-勇気を出せば、世界はもっと広がる-」が発売されます。自己肯定感を高め、言葉の力とリスペクトを大切にする方法を紹介しています。自分らしさを大切にし、多様性を尊重することで人間関係を豊かにするヒントが詰まった一冊です。


NPO法人インフォメーションギャップバスターの理事長であり、「マイノリティ・マーケティング」などの著者である伊藤芳浩さんの新しい本です。この本から自分にとってプラスになると思うと、楽しみですね!
オンラインイベント、「ろう者でもできる!Yes, Deaf Can!-ろう者のビジネスリーダーが活躍する共生社会へ」
5月29日(木)18時半から20時までオンラインイベントを行います。開発途上国のろう者の自立支援やマイクロファイナンスに取り組む団体・特定非営利活動法人Yes, Deaf Can!の代表らが登壇し、活動を紹介します。

オンラインイベントのほか、5月3日(土)〜30日(金)の期間中には、写真やパネルなどの展示も行われます。ご興味のある方は、ぜひ足を運んでみてください!
バリアフリー上映について、改めて考えることがありました。
私は、映画作品情報について「自分が見えていること」しか見ていなかったことに気づきました。本当はもっと多くの作品があること、そしてそもそもバリアフリー環境が整っていない作品がとても多いことに、正直驚きました。
映画館での「当たり前」は、実は人によって大きく異なるということ。聞こえる人が無意識に享受している「体験」を、誰かが体験したくてもできないとしたら…そのことに目を向けるだけでも、社会の見え方が変わってくるように思います。
それも踏まえて、キコニワライターのみかんさんが発信している「知っているようで知らない!?バリアフリー日本語字幕の世界」の対談記事を読むと、より深く知ることができました。
多くの方に読んでいただけたら嬉しいです。
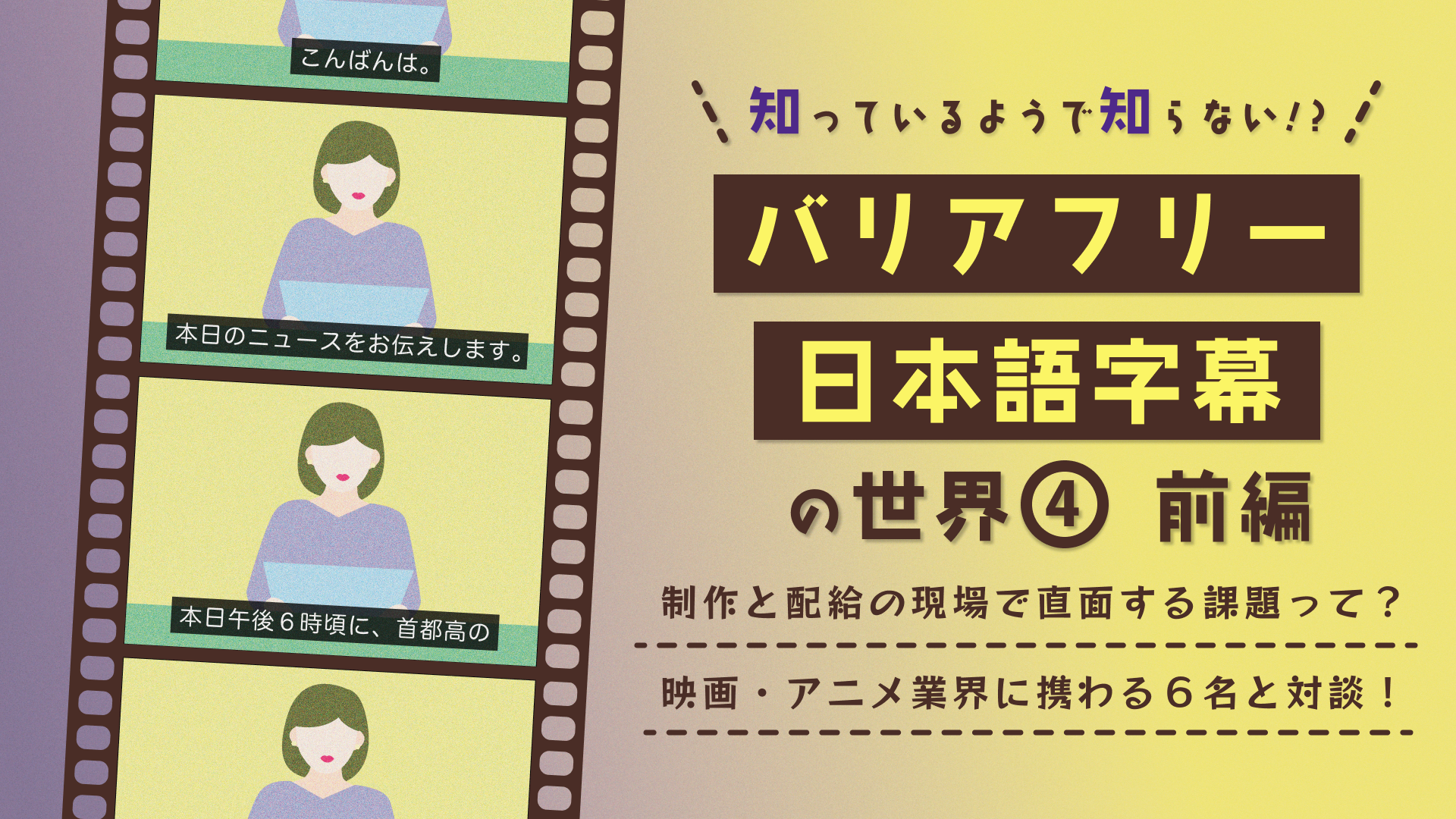
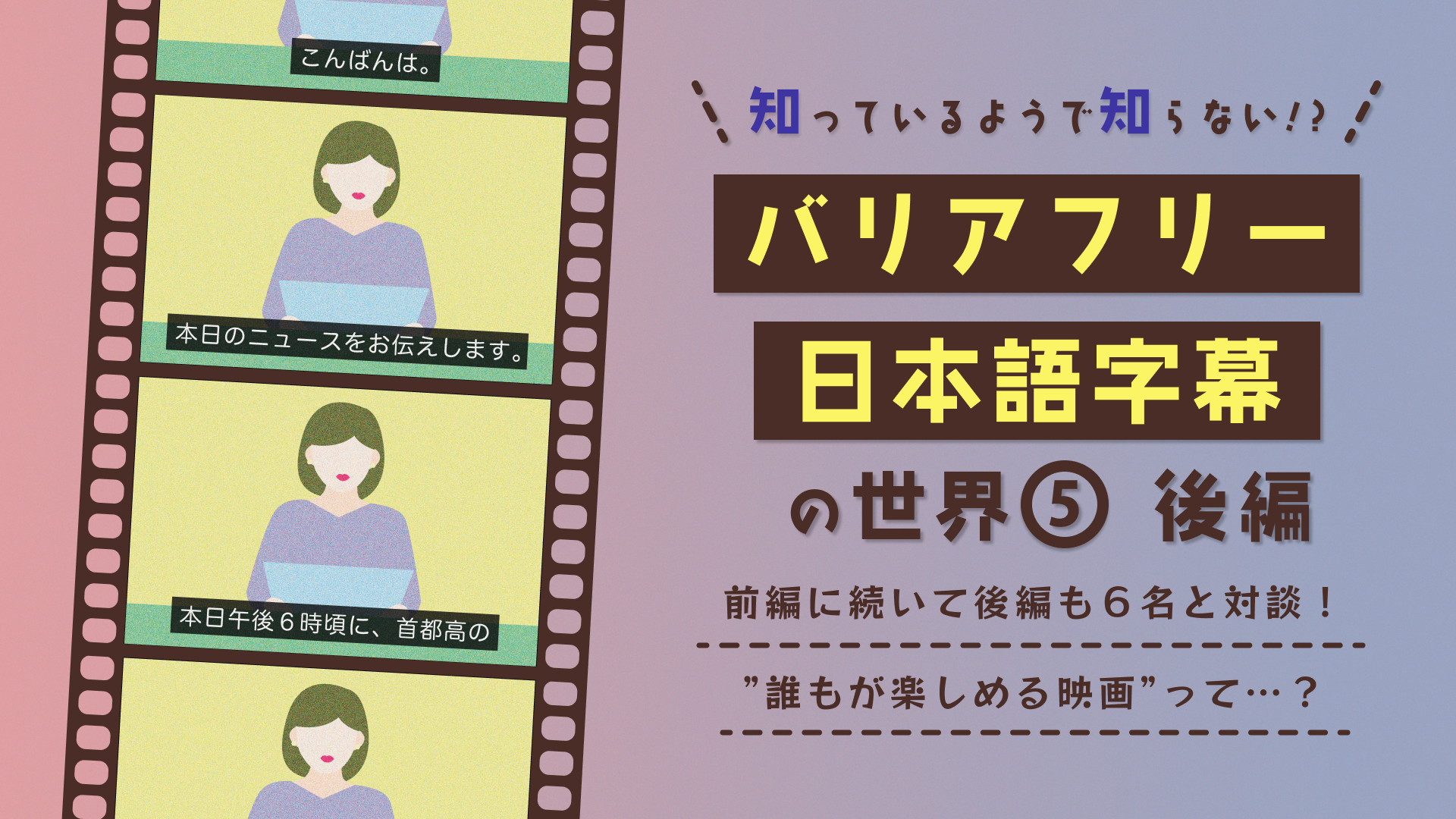
上記の記事にある「業界全体に字幕を”標準装備”という意識が広まれば…」という言葉の通り、バリアフリーという言葉は「特別なこと」ではなく、「当たり前=標準」として、もっと日常に溶け込んでいくべきだと感じました。
また、私は映画や舞台が好きで、字幕上映があるたびに観に行っていますが、少なさに「残念」と思うだけではなく、「もっと増やして」「当たり前のこととして定着させてほしい」と声をあげていくことも大切だと実感しました。
それでは、素敵な週末をお過ごしください✨