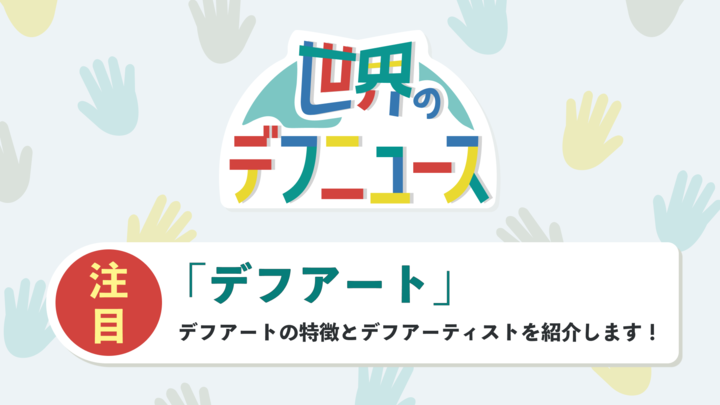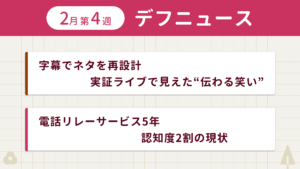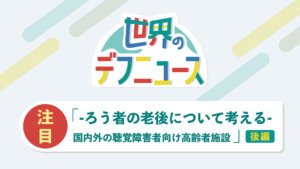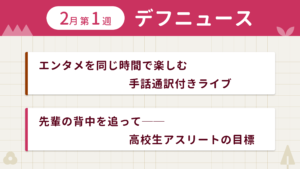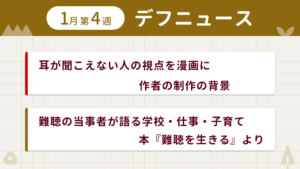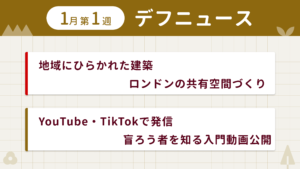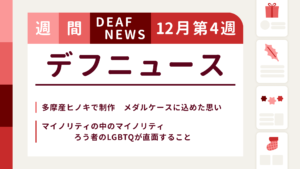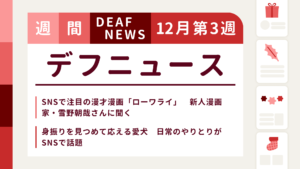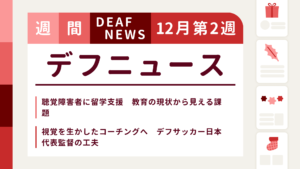こんにちは!
いつも読んでいただきありがとうございます。
3月に入り、寒さの中にも春の気配が感じられるようになってきましたね。
心が弾む季節、皆さんはいかがお過ごしでしょうか?🌸
さて、今回の『世界のデフニュース』のテーマは『デフアート』です。
みなさんは『デフアート』と聞いてどんなイメージが湧くでしょうか?
『デフアート』とは、”deaf art”をカタカナにした言葉で、「ろう者の芸術」という意味です。
ろう者が制作した彫刻、絵画、写真、動画などの作品で、ろう者の行動様式、歴史、文化、手話などが表現された芸術のことを指します。
日本でデフアートが広まり始めたきっかけの一つに、乗富秀人氏の存在があります。
日本におけるデフアートの第一人者として知られる彼の作品や活動は、デフアートの認知度を高め、多くの人々がその魅力に触れるきっかけとなりました。

現在は販売されておりませんが、乗富秀人氏はデフアート絵本を出版された過去があります。
また、デフアートは欧米ではすでに広く知られているため、その影響を受けて日本でも次第に関心が高まっていきました。こうした海外からの流れは、日本におけるデフアートの普及を後押しする大きな要素となりました。
さらに、デフアートは単なる芸術表現にとどまらず、ろう者の文化的アイデンティティを示す重要な手段でもあります。
手話文化や歴史、さらには「音のない世界」をテーマにしたデフアートは、ろう者自身の想いや経験を伝える貴重な表現方法として注目されるようになりました。
さらに、乗富秀人氏の個展をはじめとする展覧会が開催され、多くの人がデフアートに触れる機会が増えたことも、日本での広がりを後押ししました。
こうしたさまざまな要因が重なり、デフアートは日本でも少しずつ広がりを見せていったのです。
日本では、2019年に聞こえないアーティストの作品を集めた展覧会「デフアート展2019」が開催されました。
デフアートの特徴
1)ろう文化の表現
デフアートは、ろう者としての経験や手話を中心としたコミュニケーションの重要性を描くことが多いです。
作品には、手話の動きやろう者の生活を象徴するモチーフがよく使われます。
2)視覚的要素の強調
ろう者は視覚的な情報を重視するため、デフアートの作品も色彩、コントラスト、動きの表現が豊かであることが多いです。
3)社会的メッセージの発信
デフアートの多くは、ろう者の社会的な課題や誤解を解消するためのメッセージを含んでいます。ろう者の歴史や権利運動に関連するテーマもよく取り上げられます。
有名なデフアーティスト
デフアートの分野では、世界中に多くのアーティストが活躍しています。
チャック・バイアーズ(Chuck Baird):デフアートの先駆者であり、手話の動きを取り入れた作品で知られています

ナンシー・ルース(Nancy Rourke): ろう文化やアイデンティティを強調する作品を制作。

エレン・マンスフィールド(Ellen Mansfield): ビジュアル的な手話表現を取り入れた作風が特徴。

ご本人のインスタグラムでも魅力的な作品が見れます。
Instagram(@_ellen_mansfield_artist)
日本では「デフアート」の普及はまだ進行中かもしれませんが、近年では、演劇・映画・美術などの分野で人材育成を行い、ろう者や難聴者が表現者として活躍するための学びの場を提供している「育成✖️手話✖️芸術プロジェクト」が大変興味深いです。

私はろう者ですが、子供の頃に「デフアート」について知る機会はありませんでした。手話を使っていたにも関わらず、手話をモチーフにした絵を描くという発想は全くなかったのです。初めて手や手話をモチーフにした絵を見たのは、大人になってからだったと記憶しています。
もし、聞こえない子供たちが学校の美術や図工の時間にデフアートについて学ぶ機会があったら、きっと素晴らしいだろうと思います。デフアートを知ることで、聞こえない人が自分を表現する新しい方法に気づくきっかけになるかもしれません。
子供たちが「自分の世界をアートで表現する楽しさ」を知る場が、もっと広がることを願っています。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
参考文献
https://creativewell.rekibun.or.jp/activity/detail/summersession2023_talksession2/ https://www.kwansei.ac.jp/c_shuwa/news/detail/50 https://deaf-art.org/deaf-art/https://www.museumofdeaf.org/de-via
https://skemman.is/bitstream/1946/40956/5/BA lokaverkefni.pdfhttps://nagish.com/post/deaf-culture-arthttps://www.kwansei.ac.jp/c_shuwa/news/detail/50