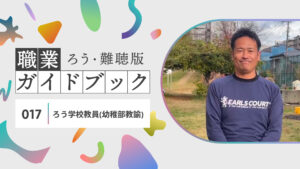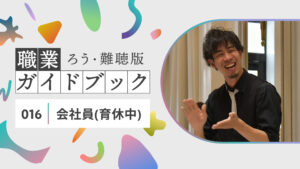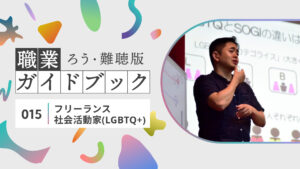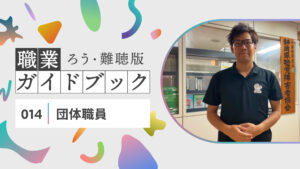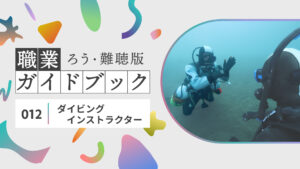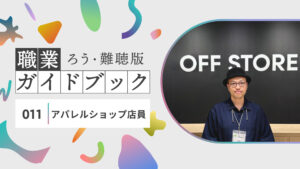キコニワから未来を生きるろう・難聴に送る、
ろう者・難聴者版の職業図鑑。
あなたの目指す働き方のヒントに。
さまざまな職種のろう、難聴者にインタビューを行い
職業紹介の記事を連載します。
#ろう #難聴 #聴覚障害 #仕事 #職業 #就活 #新卒 #転職
喫茶店経営
笠井 賢一郎さん
‐ 兵庫県出身
きこえについて
生まれつき耳がきこえない。(先天性感音性難聴両耳)
ろう学校幼稚部と地域の保育園の双方に通い、小・中・高は地域の学校に通う。
中学1年生の時、手話に出会う。それまでは口話のみで生活していた。
普段のコミュニケーションは手話やスマホの音声認識、筆談を活用して行っている。

基本情報
芦屋川手話cafe & BAR〈Knot〉店主
兵庫県芦屋川でカフェ&バーの店舗を経営する。
(主な業務)
・食材、日本酒の仕入れ
・提供する食べ物の仕込み
・接客
・売上、経費の管理
・スタッフ採用、育成
・交流会の顔出し、サポート
 笠井
笠井2020年に開業して5年目!4年の間借り営業を経て独立しました。
1日の流れ

 笠井
笠井在庫切れになれば、帰宅後にコーヒー豆の焙煎をしてから寝ることもあります。
喫茶店店主・経営者になるには
一般的なケース
① 個人経営で喫茶店を開業する。
自宅の一部を活用、間借りカフェ、週末カフェ、
不定期カフェなどの方法で開業。
② チェーン店の店長候補として働く
笠井さんの場合
大学生の頃、ろう・難聴の子ども向け学習塾で指導し、勉強だけでなく社会経験の大切さを実感。
社会経験を積む学習の一環として企画した「手話カフェ」をきっかけに、本格的に手話で交流できる場づくりを目指す。
大阪・中崎町で手話カフェの企画を立ち上げ、協賛を募る中で「協力するので手話を教えてほしい」という声があり、交流の場の重要性をさらに実感。以後、関西各地で店舗を借りて手話カフェを開催し、3年間活動を続ける。
薬剤師として働きながら活動を続けていたが、コロナ禍で店舗開催が困難になる。そんな中、偶然訪れたビール専門店の店主が「平日は誰かにお店を使ってほしい」と考えていたことを知り、間借りで手話カフェを再開。その経験を経て、独立開業を果たす。

こんな人が向いている!
① 会話が好き
お客様の中には店内で会話を楽しみたい方もいれば、静かに過ごしたい方もいます。
その見極めが難しいですが、会話が好きな人はその見極めが得意な傾向があるように思います。
お客様の小さな変化。機微を捉えられる人も会話が好きな人に多い気がします。
② もてなすことに喜びを見出すことができる
初めは緊張していたお客様が、帰る頃にはリラックスして会話を楽しんでいる。
そんな接客ができたときに喜びを感じられる人は、この仕事を長く続けられるでしょう。
③ 言葉に対して興味が人一倍ある
会話には、言葉の選び方や相手の反応を読む力が不可欠です。
難しい言葉を知っていることよりも、その場に適した言葉を選び、機転を利かせて話せる人が求められます。
言葉の使い方に敏感な人は、喫茶店だけでなく、あらゆる場面で強みを発揮できるでしょう。
求められるスキル、必要な知識
① 基礎体力
身体が資本です。立ち仕事が中心のため、身体的・精神的な持久力が欠かせません。
② 義務教育レベルの基礎知識
お金の計算やお客様との円滑な会話には、基本的な計算力や言語能力が必要です。
③ 情報収集力
喫茶店だからといってコーヒーの知識だけに留まらず、お客様との会話を盛り上げるため、
幅広い話題に対応できるよう、常に情報を収集し、学ぶ姿勢を持つことが大切です。
④ 対人力(コミュニケーション力、察する力)
お客様の気持ちを察し、適切に対応する力が重要です。時には意見の違いを乗り越える対応力も求められます。
言葉を知ることで、より深いコミュニケーションが可能になります。
 笠井
笠井多様なスキルが必要です。お客様との会話を大切にし、心地よい空間を提供できるよう努めています。
スキルアップのためにしていること
❏ 読書
❏ 映画鑑賞
❏ 交流の場に飛び込む
❏ 手話に関する情報の収集
❏ いろんなお店を回る
 笠井
笠井上記で挙げた必要な知識、スキルを養うことに繋がります。

教えて!センパイの経験談
この仕事を始めたきっかけ
きっかけは手話カフェ
――喫茶店を始めたきっかけを教えてください。
 笠井
笠井一応、手話カフェの活動の中でというのがきっかけになりますね。
手話講座だけでなく交流の場をより増やしたいと思っていたことと、昔からお店をやってみたい想いもありました。
フリースクール、塾講師を経て
――”一応”というと他にもあるのでしょうか。
 笠井
笠井中学1年生のとき、フリースクールをきっかけに手話を知りました。
その代表とは長い付き合いがあり、大学2年生のときに塾を立ち上げた際、声をかけていただき、塾講師として働くことになりました。
指導の一環で生徒たちの社会経験の場として「手話カフェ」を企画したことをきっかけに、活動を続けていきたいと思うようになりました。
振り返ると「無駄」がない
――過去の経験が喫茶店経営に繋がっているのですね。
 笠井
笠井そうですね。
中学1年生からの経験が一つひとつ数珠つなぎのように結びついて今に至っています。だからこそ、少しでも興味のあることにはチャレンジするのが大事だと思います。
「それって意味あるの?」と聞かれることもありました。
塾講師を始めるときも、親に「今やる意味があるのか?」と止められましたが、「意味があると思う」答えて、続けた結果、今の喫茶店経営につながっています。
今では親も何も言えなくなっています(笑)
異分野でも役立つ「分析力」
――薬剤師としてのキャリアをお持ちの笠井さんですが、その経験が活きていることはありますか。
 笠井
笠井理系の学びが活かされていますね。
薬学は「なぜ?」という分析をとことん求められる学問で、疑問を追求することが覚えるための鍵でした。
その「なぜ?」を深掘りしていく学びのアプローチが、今ではお客様の言動に対しても活かされています。なぜそのような言動を取るのかを分析し、お客様のニーズに応じた対応を心がけています。
薬剤師と喫茶店の店主という、全く異なる分野ではあるものの、ベースは同じですね。
楽しい瞬間
カウンターの陰から
――仕事で楽しいと思う瞬間はありますか。
 笠井
笠井常連のお客さんと初めてのお客さんがいるとき、最初は私が間に入って3人で会話をします。
でも、時間が経つにつれ、自然と2人の会話が弾んで行った時、私はそっと引いていく。もちろん、完全に放置するわけではなく、見守りながら。
そんなふうに、お客さん同士がつながっていく瞬間を見届けるのが楽しいですね。店がただの空間ではなく、人と人を結ぶ場になっていると実感できるんです。
人と人をつなぐ
――店名のとおりのKnotが実現できた時ですね。
 笠井
笠井そうなんです。
ただ、人との繋がりを求めていない人もいるので、その判断が非常に難しいです。ニーズに合った判断ができて、人と人を繋ぐことに成功した時は、お店をやっていてよかったなと思いますね。
悩んだこと、悩んでいること
経営をしていくために
――仕事をしていくうえでの悩みはありますか。
 笠井
笠井経営を維持していくために、回転率を考慮しなければならないことが悩みですね。
このお店は回転を目的としていませんので、本来の目的である交流がしやすい環境は整っているものの、経営面を考えると悩ましい部分もあります。
うまくバランスを取るためには、どのように工夫していけばよいかが課題ですね。
柔軟な発想が鍵
――経営を維持していくためには、利益も必要ですよね。
 笠井
笠井その通りです。回転率を上げなくても、1人のお客様からの注文を増やすという考え方もありますので、メニューの開発などの努力も必要です。
コーヒーだけでは限界があるので、メニューの充実を図るなど、経営において工夫を凝らす必要があると考えています。
きこえる人との協働の仕方
手話もあわせて教える
――きこえる人と働くときはどういった工夫をされていますか?
 笠井
笠井Knotでは店主の私と聴者スタッフ1名。また、土日にボランティアでお手伝いさんに協力していただいて経営しています。
この聴者スタッフは、最初は手話がわからなかったので、筆談に手話を交えて教えていましたが、次第に手話だけでコミュニケーションが取れるようになりました。
ですので、特別に私が苦労したわけではなく、むしろ助けられています。
手話が必要な場合は、筆談と一緒に手話も教えると良いのではないかなと思います。
ビジネスパートナーは目の人
――その方を雇った理由をお尋ねしてもよいでしょうか。
 笠井
笠井この聴者スタッフはなんというか…。特殊なんです。
最初は手話を知らなかったのですが、何度かKnotに来るうちに手話を習得し、その上達の早さが驚くほどでした。
そのタイミングで前の仕事を辞めることを考えていたようので、スカウトしたところ、入ってくれました。
Knotには多くのろう者が来店されますので、さらに手話を習得していきました。そんな流れです。
そのスタッフは元々”目の人”(視覚を使ったコミュニケーションが主体の人)だったのではないかと思っています。声を使うことに抵抗があり、手話の方が自分の考えやイメージを伝えやすいと本人が言っていました。
生活に手話が必要だと感じていたからこそ、手話の習得もスムーズだったのだと思います。
使えるものはフル活用
――お客様の対応はどういった工夫をされていますか?
 笠井
笠井手話で対応していますが、もちろん手話の分からないお客様もいらっしゃいます。以前は筆談を使用していましたが、現在ではYYProbe(音声認識アプリ)を活用することで、お客様とのやり取りが格段にスムーズになりました。
簡単な会話は指差しで済ませることもできますが、より細かい要求や会話が必要な場合にはYYProbeを使っています。
お客様に寄り添う
――会話になると筆談は限界がありますよね。
 笠井
笠井そうなんです。
例えば、日本酒を好まれるお客様が「辛い」「甘い」「すっきり」「青森のお酒」など、特定の要望をお持ちの場合、筆談では限界があります。
そのため、筆談に慣れていないお客様も多く、しばしば「おまかせで」となってしまうことがありましたが、YYProbeを活用することで、できる限りお客様の要望に応えるよう心がけています。

学生時代の印象的な出来事
人に無関心だった少年時代
――13歳の頃の性格や印象に残っているできごとはありますか?
 笠井
笠井口話中心の環境で育ち、手話を主とするろう者に出会ったのは中学1年の終わり頃でした。それまでは無口で他人に無関心、人との交流よりゲームを好む性格でした。
しかし、中学2年生からろう児・難聴児向けのフリースクールやキャンプに参加するようになり、人との交流の面白さに気づきました。ゲームは結果が決まっていますが、人との関わりは予測できないからこそ楽しいと感じるようになったのです。
高校入学時にはゲームを手放し、積極的に人と関わるようになりました。
それまでは人付き合いが苦手で消極的でしたが、高校からは誰とでも話せる明るい性格に変わったなと感じています。
人生の糧となる出来事
――フリースクールで印象に残っている出来事はありますか。
 笠井
笠井屋久島へ行ったことですね。縄文杉を見に行ったのですが、当時の私は今の倍近く体重があり、中学3年生の頃には100kgを超えていたと思います。
そのため、他の子どもたちに大きく遅れをとり、ろう者の大学生スタッフと一緒にゆっくり歩きました。
ほとんどの子が往復6時間で登りきる中、私は10時間かけてゴールしました。その達成感は今でも忘れられません。
苦しみを耐え抜き、困難を乗り越えた先にある達成感を知ることができた、貴重な経験でした。

 笠井
笠井実は、この喫茶店はコロナ禍にオープンし、赤字が続く厳しいスタートでした。2年目でようやく客足が安定したことを思うと、 ふと、屋久島での体験を思い出します。
あの時、時間はかかっても前に進めば必ずゴールできると実感したように、 困難はきっと乗り越えられると信じて続けることができたのだと思います。
学生時代にしておくべきこと
直感と感性を大切に
――笠井さんが思う、学生時代にしておくべきことは何でしょうか。
 笠井
笠井自分の興味のあるもの、直感が働いたものにチャレンジすること
損得勘定は置いておいて、まずは自分の直感や感性を大切にして欲しいです。変化が著しい時代だからこそ、瞬発力も必要なのでその場で決断し、行動に移すことが求められます。
スマホで調べてからお店に行くのもいいですが、たまにはスマホを置いて、気の向くままに散策し、目を引くお店に立ち寄ってみたり、自分の感性を楽しむこともオススメですね。

さいごに…
座右の銘
日ごろから心に留めている言葉を聞くことで
その人となりや、その人の歩んできた道が
垣間見えると思い、聞いてみました!
“The only thing that interferes with my learning is my education.”
Albert Einstein
私の学習を妨げる唯一のものは、私が受けた教育である
アインシュタイン
――最後に座右の銘を聞かせてください!
 笠井
笠井アインシュタインの「私の学習を妨げる唯一のものは、私が受けた教育である」です。
――その言葉にはどんな意味が込められているのでしょうか?
 笠井
笠井お客様に勧められて観た映画の最後に印象に残ったフレーズがあり、選びました。
これまでの教育が間違いだという意味ではなく、 アインシュタインが伝えたかったのは「その真実は本当か?」という疑問を持つことの重要性ではないかと感じたのです。
受けた教育や情報をそのまま信じるのではなく、他の視点を持つことが大切だと思います。 疑問を持ち、分析や発見を通じて学び続けることこそが、本当の学びだということを言いたいのだと思っています。
喫茶店経営においても、日々のお客様との交流の中で、いつもと違う話や反応に気づくことが大切です。
微妙な変化、機微を感じとることで、お客様との距離がぐっと縮められるのではないかなと常々考えています。
そのため、自己を疑う力を養うことの大切さを忘れないようにしたいと思い、この言葉を選びました。

喫茶店経営を目指しているあなたへ
これからAIなど機械が台頭する時代がやってきます。機械にできないことが大切にされる時代にもなります。
その大切なことはなにか。喫茶店の仕事にはそれが詰まっていると思います。それは何か、考えてみてね◎




![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3d56913d.8b604fb3.3d56913e.086948e9/?me_id=1213310&item_id=20876620&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3829%2F9784827213829_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3d56913d.8b604fb3.3d56913e.086948e9/?me_id=1213310&item_id=19382570&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1831%2F9784802611831.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3d56913d.8b604fb3.3d56913e.086948e9/?me_id=1213310&item_id=11985524&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6238%2F9784413036238_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)