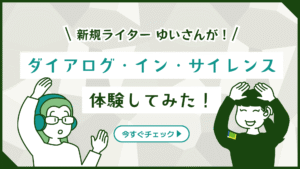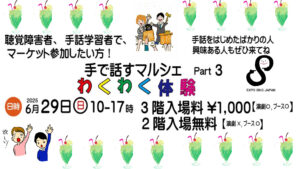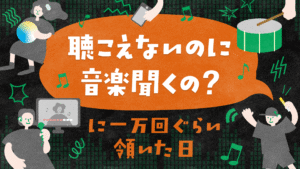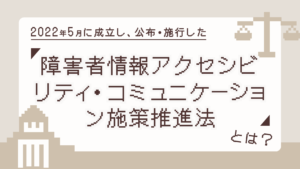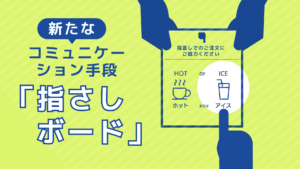Deafセラピストのまとんです!
NPO法人「手話で育てる親の会」の代表であるみつえさんにインタビューしました。
みつえさんは、ろう・難聴児の子育てを通じて、「日本手話」での教育の大事さを発信し、2024年7月にNPO法人「手話で育てる親の会」を設立しました。
「日本手話」での教育ってどんなことだろう?と、みつえさんに色々聞きました!
 まとん
まとん「手話で育てる親の会」(以下、手話親会)を設立したきっかけを教えてください。
 みつえさん
みつえさん自分はデフファミリーとして育ちました。そして、子どもが生まれ、親として、また当事者としてろう学校の教育を目の当たりにし、「なんか違う!」と違和感を強く感じました。その「違和感」は何なのかを、子育てをしながら10年以上、経験や勉強をして手探り、やっと分かったのが、言語である「日本手話」でした。
当時のろう学校の教育ではなかなか理解してもらえなかったのですが、同じく「日本手話」の必要性を感じていた同志を見つけ、さらに、「早期教育のパブリックコメント」を見て、自分たちの考えは間違っていない!と確信し、言語である「日本手話」の必要性を広めるために、「手話で育てたい親の会」として活動をスタートしました。
 まとん
まとん言語である「日本手話」というのを具体的に教えてください。
 みつえさん
みつえさんろう・難聴児の教育で大事なことは、「ことばを身につける」ことです。今も昔もですが、ろう学校での教育は、日本語からくる視覚的情報や日本語のツール、つまりキュード、指文字、日本語対応手話、音声日本語と、色んな教育が混ざっています。それらを否定はしていませんが、それが手話のひとつだと子どもが混乱して、うまく言語を身に着けられない状態です。例えば、まだ小さい子どもが授業中に、英語・中国語・日本語を一気に教育されているイメージです。3つの言語が頭の中でごちゃ混ぜになってしまいますよね。それが当然だと思い込んでしまいます。聴者の子どもたちは、自然な母語で話すのに、ろう・難聴児の子どもはそうではありません。それは果たしていいことだろうか、と思います。
また、ろうの脳は、耳が聞こえない分、目から情報を得るため、情報が「絵」や「写真」として、生まれつき脳にあります。それを聴力も音声も関係なく生まれた時から手話で親子で話し、その土台があれば、わざわざ絵を使わなくても、日本語と日本手話が結びついて「ことば」として理解します。
ろう学校で使われている日本語だけでは、細かい表現までは伝えにくいのが現状です。例えば、朝顔が咲く様子を日本語で説明すると、「咲く」だけですよね。「つぼみの捻じれている部分が広がりながら咲く」という風に、細かく表現をするときに、CL(※1)が必要なんです。花の開き具合も日本語では説明しにくいはずです。子どもによってイメージも違うのですから。
ですから、早期教育として、0~3歳のろう児に、まず日本手話を言語として教育し、「言語意識」を育てるのが一番大事です。ここでどれだけ手話を身につけるかどうかで、後の成長過程が決まります。「言語意識」は「ことばの準備」であり、物事を考える力にもつながります。
幼稚園の年齢(4~6歳)で、ことばの教育を受け、日本手話と日本語を繋げます。小学校に入ったら、さらに抽象的な部分や、細かい部分を学習できるので、きこえるこどもと同じプロセスとして成長できます。
日本手話と日本語の2つの言語を育てる「バイリンガル・バイカルチュラル教育」(※2)をすることで、ろう児が「ことば」をしっかり取得できるので、これを広めたいと思って活動しています。
ちなみに、この早期教育をしているのは、東京にある「明晴学園」の一校だけです。
(※1 CL…Classifier(クラシファイアー)の略で、代名詞としてものそのもののイメージを伝えること。例えば、木でも、太い木、細い木、葉っぱがたくさんついている木、枯れかけの木など、様々な木があるので、それをイメージとして伝える)
(※2 バイカルチュラル…2つの文化という意味であり、ろう者と聴者の2つの文化を指す。)
 まとん
まとん手話親会の活動内容を教えてください。
 みつえさん
みつえさん①日本手話で育てる親への情報提供
②子育ての資源をつくる
③社会への発信活動 の3つを中心に活動しています。今後は、親子コミュニケーションのための手話指導、ワークショップ、知識を得るための講演会、日本手話からの教材販売を予定しています。12月22日に「しゅわっち学校コラボ保護者講演会」を開催します。
ろう・難聴児の教育には、親子の関係が非常に大事です。まず、ろう児を育てる保護者に、必要性を知ってもらうために、情報提供をしています。また、ろう学校やろう児に関わる教員、言語研究者にも情報提供をし、ろう教育を変えていきたいです。

 まとん
まとんみつえさんのお子さんへの教育で、印象に残っていることを教えてください。
 みつえさん
みつえさん自分の子どもは3人ともろうですが、まず日本手話で子どものレベルに合わせながら会話を育て、成長する過程で日本語を教えていきました。手話が伸びている分、日本語も自然に伸びていくのが分かります。日本手話を第一言語としている子どもが小学1年生の時、作文を一気に3枚書きましたが、日本語を第一言語としている子どもたちは、ことばの力が弱く、作文がなかなか書けないというのを目の当たりにし、やはり「日本手話」の必要性を痛感しました。
また、末っ子は中度難聴なので、日本語も耳から入ってきますが、意味は理解していないことが多いです。中度難聴や人工内耳の子どもでも日本手話は絶対に必要だと感じました。

 まとん
まとん早期教育で「ことば」を身につけることで、考える力、表現する力がつくことをお話しされましたが、その他に身につくことはなんでしょうか?
 みつえさん
みつえさんろう者としてのアイデンティティとろう文化(異文化)ですね。みんな当たり前のように言う、社会で共に生きていけるように“口話”中心に、聴者についていけるように教えられました。それが決して良いとは限らないです。聴者についていくこと、合わせること、それが“当たり前”だと無意識のうちに抑圧しているので、「自分」というものをうまく出せていない人が多いです。その反面、ろう学校で育った子どもは、子ども同士によってろう文化を自然に学んでいるので、ろう者としてのアイデンティティが確立されていて、のびのびと育っている印象を受けました。自分の意見をはっきりと言える子どもが多いですね。共通言語を持つことはとても大切です。
 まとん
まとん手話親会の最終的なビジョンを教えてください。
 みつえさん
みつえさん手話親会としては、ろう教育を変えること、手話で育てたい親が増えて、ろう教育を変えていくような活動をしたいです。そして、個人的には最終的に、関西の「明晴学園」を作りたいです。社会的人権として、ろう者として生きるために、バイリンガル教育を広めたいという想いをもって活動していきたいです。
みつえさん、ありがとうございました。
私は、ろう学校の幼稚部を卒業してからずっと地域の学校で育ち、手話と出会ったのは高校2年生のときでした。
ろう者が身近にいない環境で育ったので、ろうの文化を知ったときは、「カルチャーショック」を受けました。もっと自分を出していいんだと、ろう者のアイデンティティが確立される良いきっかけになりました。
みつえさんは、InstagramやYouTubeで発信していますので、ぜひ見てみてくださいね!
みつえさんのInstagram
https://www.instagram.com/mitsue_deaf
みつえさんのYouTube(3人のお子さんも出ています!)
https://www.youtube.com/channel/UC454o5PQ04OR3smu0u5_3DA
手話親会のInstagram
https://www.instagram.com/syuwaoya
12月22日に開催される「しゅわっち×手話親会」コラボ企画(申し込みは終了しています)