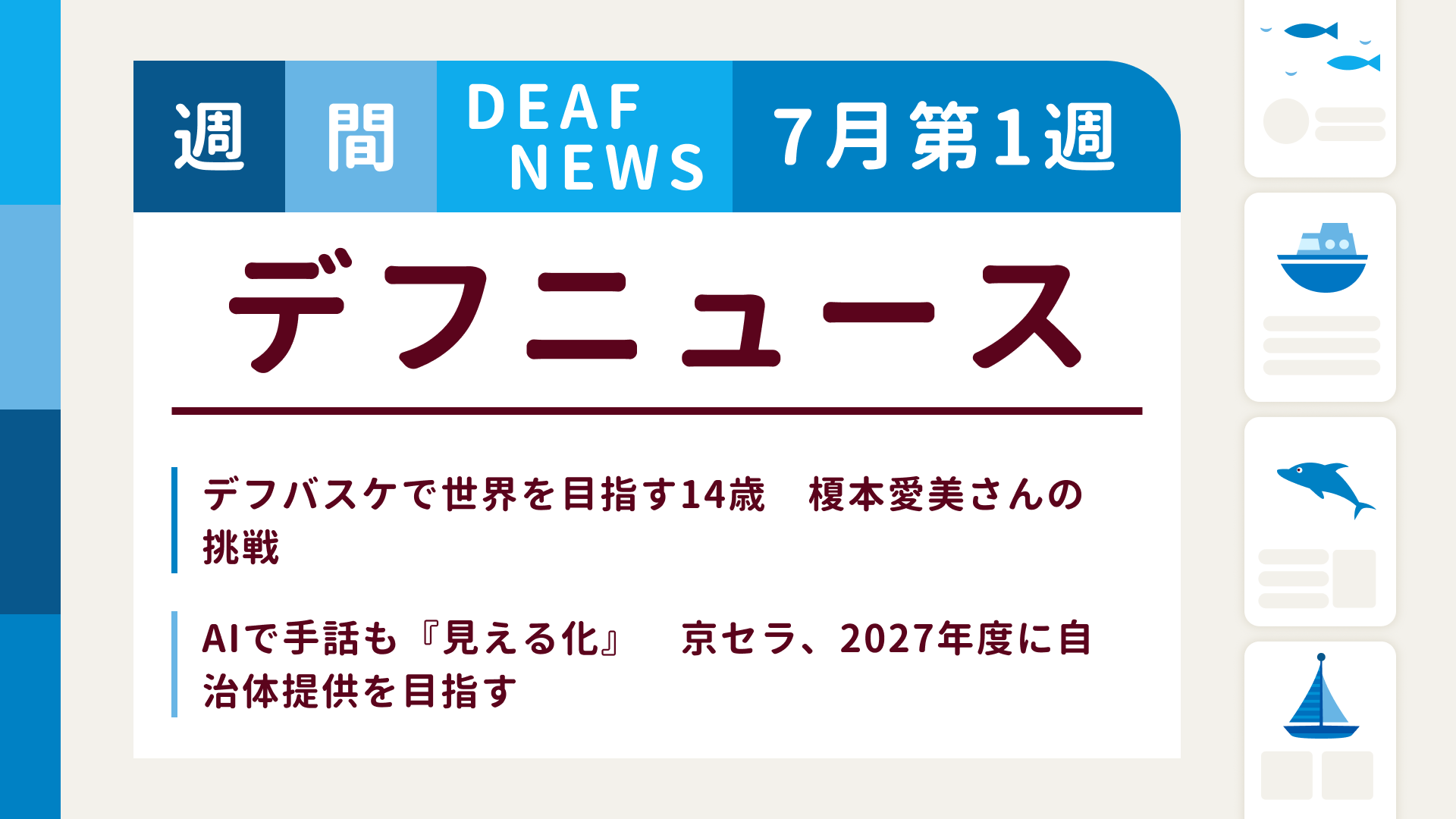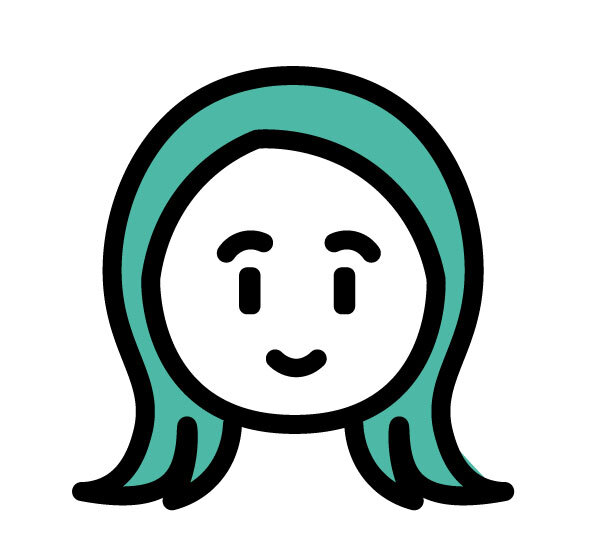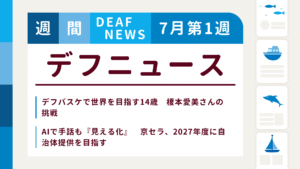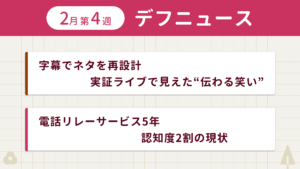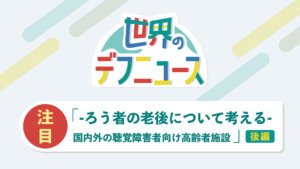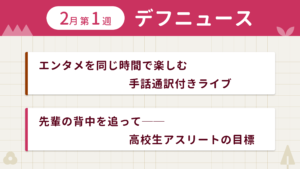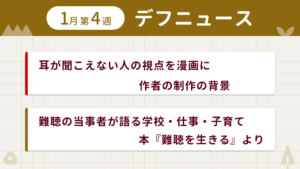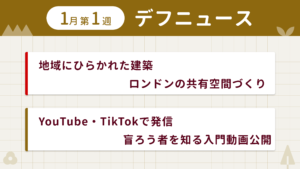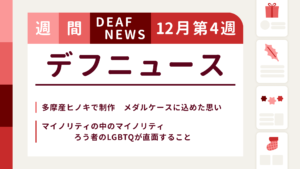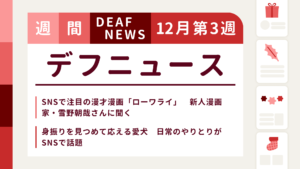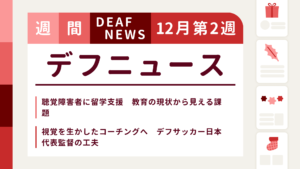こんにちは!
7月に入り、まだまだ暑さが続くかと思うと、ちょっと気が遠くなりますね…。
そんな中、私の子どもは「暑いけど、もっと楽しみなことがあるよ!」とニコニコ。何だろうと思って聞いてみると、「もうすぐ夏休みだから!」とのこと。あと2週間ほどで夏休み…早いですね〜😳
さて、今週は6つのデフニュースをお届けします✨
注目は、デフバスケで活躍し、国際合宿でMVPにも選ばれた中学3年生・榎本愛美さんの挑戦と日々の努力を紹介している記事です。バスケが大好きな子どもたちにとって、きっと憧れの存在になるでしょう。読めば「私も頑張ろう」と前向きな気持ちになれる内容です。
デフバスケで世界を目指す14歳 榎本愛美さんの挑戦
感音性難聴の中学3年生・榎本愛美さんは、デフバスケットボール日本代表を目指し日々練習に励んでいます。兄の影響でバスケを始め、聞こえる人のクラブでの経験を通じて仲間との交流やコミュニケーションの難しさも経験しました。デフバスケとの出会いが転機となり、国際合宿ではMVPにも選出。将来は世界で活躍する日本代表選手を目指し、競技の魅力を広めたいと語っています。

デフバスケとの出会いを通して自分らしさを見出した愛美さんの姿に、心を動かされました。国際合宿でMVPに選ばれたことも素晴らしく、それでもさらなる成長を目指して体幹トレーニングにも励んでいるとのこと。今後の活躍がとても楽しみです。
AIで手話も『見える化』 京セラ、2027年度に自治体提供を目指す
京セラは、AIで手話を文字に変換する技術を開発しています。手や指の動きを読み取り、自治体の窓口などで日本語表示する仕組みで、2027年度の提供を目指しています。日本手話に対応し、認識精度は9割超。既存の多言語文字起こしシステム「コトパット」と併用すれば、職員が手話を使えなくても円滑な対話が可能となります。


音声に話し方のクセがあるように、手話にも個々の表現の違いがありますが、認識精度は9割超とのこと。「コトパット」はすでに300件以上導入の実績があり、さらなる活用の広がりに期待が高まりますね。
夜間中学校で手話と聴覚障害について学ぶ 理解深まる授業
姫路市立あかつき中学校の夜間中学で、聴覚障害への理解を深める手話の授業が行われました。講師は姫路ろうあ協会の村上佳史会長で、手話や筆談などの伝え方や聴覚障害について紹介。生徒ら約40人が参加し、「楽しい」との声もあり、学びと交流のある時間となりました。


生徒の中には外国籍をもつ方もおり、「もっと覚えたい」と話していたのが印象的でした。言語や文化の違いを超えて学び合う、意義のある取り組みだと感じました。
デフサッカー男子日本代表監督が退任 パワハラ行為を受け体制見直しへ
日本ろう者サッカー協会は、デフサッカー男子日本代表の吉田匡良監督がパワーハラスメントに該当する行為が確認されたとして、6月29日付で退任したと発表。外部調査を受けた結果を踏まえ、協会はスタッフ体制を変更し、再発防止や相談体制の強化などに取り組むとしています。デフリンピック直前の指揮官交代となりました。

デフリンピックを前に、このような事態が起きたことは残念ですが、体制が見直されることで、安心してより良いチームづくりにつながることを願っています。新しい監督はどなたになるのか、今後の動向にも注目したいですね!
手話施策推進法、15年越しに成立——「ここからが本当のスタート」
2006年の国連障害者権利条約を受け、全日本ろうあ連盟が法制化を目指してきた「手話施策推進法」が、15年の運動を経て成立されました。全国の条例制定や意見書の採択が後押しに。法律上「手話言語」の明記は実現しなかったものの、今後は施策の具体化と実効性が問われます。連盟は「ここからがスタート」と意気込みを新たにしています。


長い年月をかけて、手話に関する法律が成立したことに深い意義を感じます。決して平坦ではない道のりの中で、一つ一つ丁寧に理解を得ながら進めてきた努力が、ようやく形になったのだと感じました。
芸術文化に“誰もがアクセスできる東京”へ──『オールウェルカムTOKYO』が秋に始動
東京都立文化施設では、誰もが芸術文化に親しめるよう、手話・筆談対応やバリアフリールート整備などアクセシビリティの充実を図っています。2025年の秋には、世界陸上・デフリンピックを契機に『オールウェルカムTOKYO』キャンペーンを実施。文化施設と連携し、多様な人々の参加を促進します。


誰でも楽しめるようにアクセシビリティが整っているのは、とても嬉しいですね!中には触って楽しめる展示もあるそうで、触覚を通じた体験も楽しめられますね!ますます行ってみたくなりました。以下の『オールウェルカムTOKYO』の公式サイトでは、芸術文化施設やイベント情報が紹介されています。ぜひチェックして、足を運んでみてください!
オールウェルカムTOKYO
『手話施策推進法』が6月19日に成立し、私も含め、手話を使う人たちにとってとても喜ばしいことだと実感しています。
以下の記事では、法案成立の報告会の様子が紹介されており、これまでの運動の歩みを記録した動画も掲載されています。

多くの方々が「手話は言語である」と訴え、長年にわたり取り組んできたことに、改めて感謝の気持ちでいっぱいになりました。
私自身、子どもの頃には「手話は口話の妨げになる」と先生や親から言われ、自然とそう思い込んでいました。
聞こえない友達と話すときも、声を出さず口だけを動かすことが多く、それも先生や親に「声を出しなさい」と注意された記憶があります。
「ただおしゃべりしていただけなのに、なぜ声を出さなきゃいけないの?」と心の奥で違和感を抱きつつ、その気持ちは長い間しまい込んでいました。
手話と出会ったことで、それまで緊張しながら口の動きを読み取っていた自分が、少しずつほどけていきました。
今回の法律成立は、「ここからが本当のスタート」と言われているように、ろう者やろうの子どもたちひとりひとりが、自分らしくいられる社会へとつながっていく大きな一歩です。私も一人のろう者として、その変化を後押しできるよう、できることから行動していきたいと改めて思いました。
それでは、良い週末をお過ごしください☺︎