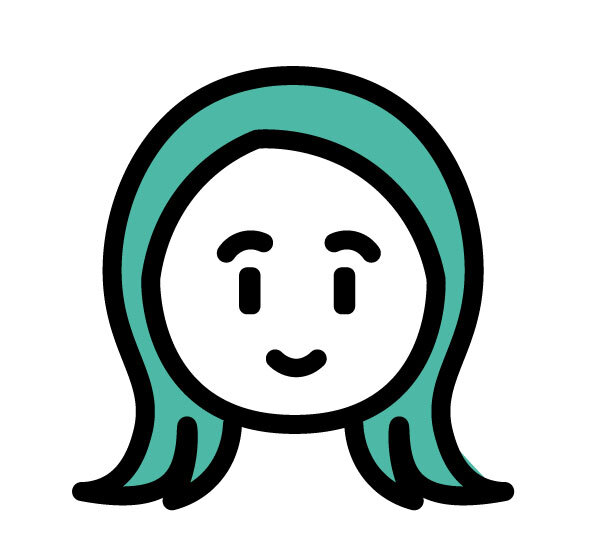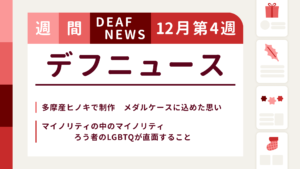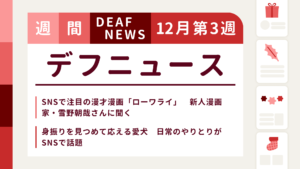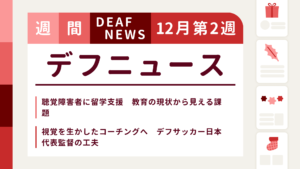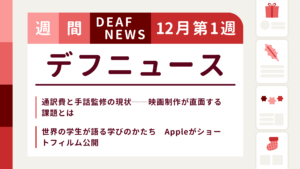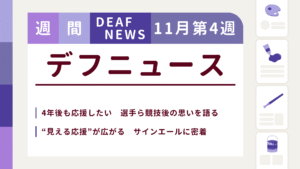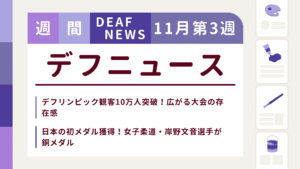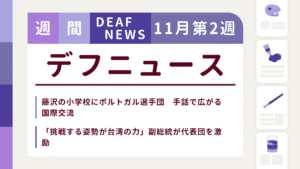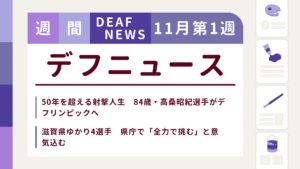皆さん、こんにちは!編集長のAkkoです。
今日も雲ひとつない空が真夏だなと感じさせられます。洗濯物がすぐ乾いて助かりますね。気温もぐんぐんと上がり、暑くなりそうなので、水分補給も忘れずに過ごしてくださいね!
さて、今週もデフニュースを紹介します。
聴覚障害者はコミュニケーションに制限があるので、聴者と同等な収入は厳しい?
6年前交通事故に遭い、お亡くなりになった井出安優香さんの将来得るべきだった収入について、障害を理由に賠償額を減額されたことに対し、見直しを求めて遺族が裁判を起こしました。その中で証人として、聴覚障害を持つ大学教授が「働く条件は聞こえる聞こえない関係なく、同等である」と述べました。
また、裁判ではコミュニケーションに制限があるので、労働能力にもつながると判断しており、それに対して音声を文字化するなどあらゆるツールを活用することで、労働能力に差異はないと指摘しました。


逸失利益とは、交通事故などに遭わなければ、将来収入を得ることができたのに、交通事故などでお亡くなりになる、働けない体になってしまったために将来得られるべきの収入が失われた時の損害の請求をするということです。しかし、聴覚に障害がある故にコミュニケーションが難しいという判断に聴覚障害を持つ大学教授が文字化するツール、手話などがあると指摘しました。AIなどテクノロジーの進歩、社会からの理解、時代の変化を見据えて障害者が働きやすい環境が増えていくと私は思います。皆さんはどう思いますか?
和歌山県、全国ろうあ者大会で手話劇・ロシア喜劇を公演
2024年6月6日〜9日に第72回全国ろうあ者大会は和歌山で開催されました。全国のろう者や関係者が2500人集まり、手話言語やデフスポーツなどをテーマにした研究分科会で講演を行う、意見交換などをしました。そこで、40年以上の歴史を持つ「岐阜ろう劇団いぶき」と「奈良ろう者劇団大仏も笑う会」が手話劇・ロシア喜劇を披露しました。手話が分からない人のための配慮、声の振り替えや字幕も付き、皆一緒に楽しんだようです。


毎年開催される全国ろうあ者大会、今年は和歌山県で開催されましたね。皆さんは参加しましたか?研究分科会では色々なテーマで学習、情報や意見交換など知識の研鑽を積み、観光でも楽しめたかと思います。その中で、2つのろう劇団、岐阜ろう劇団いぶきと奈良ろう者劇団大仏も笑う会によるロシア喜劇も行われ、手話が分からなくても面白い動きもあり会場に笑いが響きました。

奈良ろう者劇団 大仏も笑う会
@smile_daibutsu
京都府、同志社大学の手話サークル『もみの木』について
大学での手話サークルの取り組みについて、前編では『もみの木』の活動で、手話だけじゃなくろう者の背景や文化を学び、後編ではメンバーとして活動中のお二人にインタビューという記事になっています。”ランチタイム手話”を設けたり、全国手話検定試験に向けて対策をしたり、学校行事を主に通訳を担ったりなど幅広く活動しています。またメンバーお二人の手話との出会いやきっかけ、手話によって得られたこと、今後のことも語っています。

記事にもある通り、「ゆびさきと恋々」というアニメがあるのですが、ご存知でしょうか?主人公たちが通う大学のモデルが同志社大学だそうです。私はこの記事で初めて知ったのですが、自分の通う大学がモデルとしてこのように使われるのは大変嬉しいですね。手話サークル『もみの木』の活動は手話、ろう者の背景や文化、歴史を知り学ぶことで知らない世界を広げながら取り組んでいるように感じました。
三重県、聴覚障害者も人助けできる『救命カード』、実用化へ
5月30日に大阪府で開催された全国消防職員意見発表会で三重県志摩市の消防本部、消防士・丸山莉奈さんが聴覚障害者の知人から「自分も手助けしたい」という言葉、救命学習での情報保障の課題などから、障害のあるなし関係なく、居合わせた時に協力しやすいように対応できないか考えました。カードを使って救命活動ができるよう『救命カード』を発案、意見発表会で提案し、最優秀賞を受賞しました。そのカードを実用化していくため、準備を進めていると話しています。

全国消防職員意見発表会という存在は初めて知りましたが、全国9支部から10人の職員が選ばれ、業務についての課題や意見、取り組むべきことなどを発表し、意識を高めていくことを目的としているそうです。また、毎年開かれており、今年の最優秀賞は聴覚障害者も人助けできる『救命カード』を活用することで、緊急要請を依頼したり、救命措置をしたりなど活動につなげることができるそうです。カードには「救急車を呼んでください」など文章や絵が載っており、裏面には50音表が載っています。実用化した際は、全国でも広まるといいですね。
福井県、鯖江市役所の窓口に多言語・手話映像通訳サービスを導入
4月から多言語・手話映像通訳サービスが導入され、6月6日に市の職員がこのサービスを使ってデモンストレーション(実演)を行いました。これまでは翻訳機や筆談で対応してきましたが、このサービスと導入したことによって、細かいニュアンスなどが伝わりやすくなり、手続き、困っていることなどの解決につながっています。鯖江市ではこのサービスを活用することで、手話や外国語が必要な方が安心して住みやすい場所になってほしいと話しています。


多言語の中に手話通訳サービスが導入、それぞれ言語や文化の違いをよく知る通訳者を通して、聞きたいことや困ったことなどを職員にしっかり伝えて解決につながっていくことは安心して暮らすことにつながりますよね。全国各地では、ろうあ者相談員の配置、または手話通訳者の配置、以上の記事のような遠隔手話通訳サービスの導入など、それぞれ対応方法を提供していて、参考になりますね!
役所などの地方公共団体について、皆さんの住んでいる地域ではどのような対応をしているのでしょうか?
私の住む地域の役所では、手話通訳者が1人配置されています。ろう者が多く住んでいる地域でもあって、1人では足りない現状ですが、他の職員が自発的に手話を覚えて、諸々の手続きの場合は職員が、相談や他の課での通訳は手話通訳者が担当するというような感じです。私は相談や他の課での手続きをしたい時の通訳は手話通訳者に在席しているか確認をしてから行きます。また、遠隔手話通訳サービスも導入しており、それも手話通訳者が対応しています。役所に行けない時、逆に手話通訳者が質問や確認がしたい時に活用しており、利便性が高いと実感しています。
また、子育てや生活に関して聞きたい時、役所では聴覚障害者情報提供センターへの紹介、またはこの地域に住むろう者、もちろんお互いの了承を得た上でつなぐという聞こえない方々と手話通訳者とのネットワークがあり、また、時代の変化とともにオンラインなどの普及に合わせて手話通訳遠隔サービスを取り入れ、通訳だけではなく相談も活用され、柔軟に対応をしているので、安心と共に選択肢も広がったように思います。
では、良い週末をお過ごしくださいね