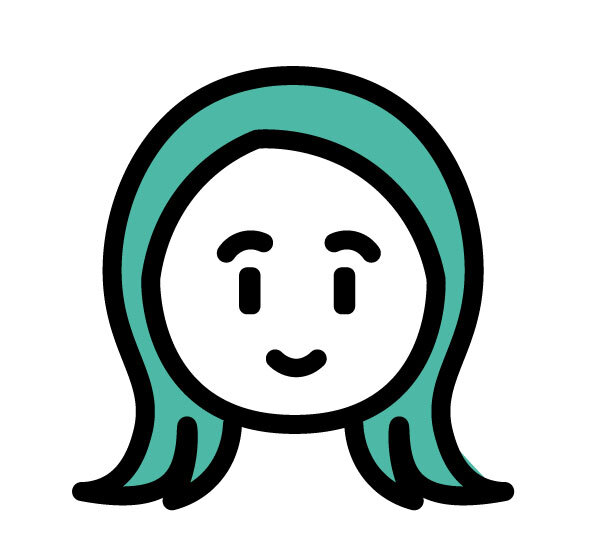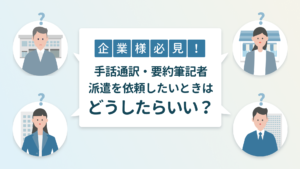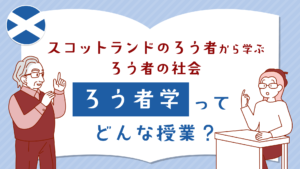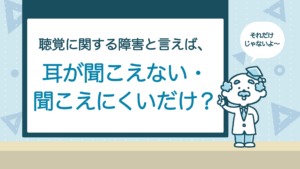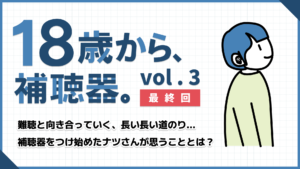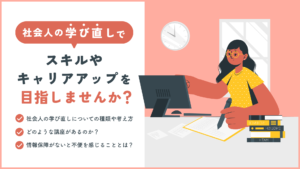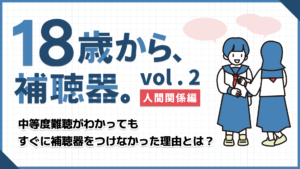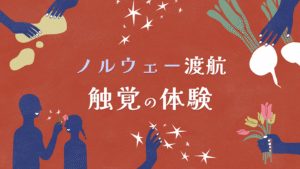いよいよ、デフリンピックが日本で初めて開催されます。
「聞こえない人たちのオリンピック」とも呼ばれるこの大会には、世界中のろう者アスリートたちが集い、競技に挑みます。
今回、デフリンピックに向けて、ろう者であり、応援アンバサダーとして活躍する川俣郁美さんにお話を伺いました。
笑顔が印象的で、ひとつひとつの言葉に想いを込めて語る川俣さん。
デフスポーツの魅力や、社会へのメッセージをまっすぐに伝えてくれました。
きっと、デフリンピックがより身近に感じられるはずです。
川俣 郁美(かわまた いくみ)
東京2025デフリンピック応援アンバサダー
ギャロデット大学ソーシャルワーク学部 卒業
同大学院行政・国際開発専攻修士課程 修了
現在、公益財団法人日本財団 特定事業部 所属
1人のろう者として、伝えたい想い
- はじめに、お仕事でのご活動なども含めて、自己紹介をお願いします。
-
東京2025デフリンピック応援アンバサダーを務めております、川俣郁美と申します。
現在は、公益財団法人日本財団の特定事業部に所属しており、主にASEAN(東南アジア諸国連合)地域におけるろう教育や手話学習などの環境整備の支援に取り組んでいます。例えば、手話で教えることのできる教員やろう当事者リーダー育成、教材の作成など、持続可能な仕組みづくりに加えて、手話の普及のため、手話辞書や教材の開発、手話教師の育成にも支援しています。
日本財団は、こうした社会課題解決の取り組みへ助成を行っており、団体からの申請書の確認をしたうえで、理念や目標が一致していれば審査を経て助成を行います。助成開始後も、進捗状況の確認を継続的に行います。助成終了後は現地の人が運営していくため、現地の人々自身が主体となった支援を心がけて進めております。
また、アジア各地にある日本財団のような財団やフィランソロピーセクターと連携しながら、共通の課題に取り組むネットワークづくりも担当しています。
そして、こうした国際的な支援活動と並行して、2年前からデフリンピック応援アンバサダーとしての活動も任されています。
- 応援アンバサダーとして活動を始めたきっかけを教えてください。
-
デフリンピックが日本で開催されると知ったとき、本当に嬉しくて、「何かしら関わることができたら」と思っていました。
私は以前から国際手話通訳として活動する機会がありましたので、そういった面から関われたらと考えていたところ、東京都の関係者から「デフリンピック応援アンバサダーをお願いしたい」とお声がけをいただいたのです。
他にアンバサダーは3人いらっしゃってて、いずれも聴者の方。
「デフリンピックでは、どんな人が活躍するのか」…
オリンピックやパラリンピックの認知度は、100%近いという非常に高い一方で、デフリンピックの認知度は2021年時点でわずか16.3%…多くの方に知ってもらいたいという思いが強くなりました。同時に、ろう者としての視点から社会に発信していく役割が求められていると感じました。
正直言いますと、「私で大丈夫なのかな…」と不安がありました。
しかし、関係者の方から「聞こえる子どもがいる学校に通っている聞こえない子どもたちは、ろう学校に通う子どもたちと比べて、大人のろう者と出会う機会が少ない。だからこそ、あなたのような存在を必要としている」と言われました。私自身も、高校まではろう学校ではなく、聞こえる子どもたちと一緒に学ぶ学校に通っていました。そうした経緯のなかでも、手話を獲得し、ろう者としてのアイデンティティを育んできた経験が、今の子どもたちやその家族にとってひとつの参考やロールモデルになれればと思ったのです。
また、目指すべきは「共生社会」です。私自身も決して完璧な存在ではなく、ろう者の中にもさまざまな人がいることを知ってほしい。だからこそ、私ひとりだけではなくデフアスリートや他のろう者のロールモデルも紹介し、互いに支え合い頼りあいながら、多様なろう者の姿や生き方を伝える「橋渡し」ができればと考え、引き受けることにしました。私ひとりではなく、ろう者の皆さんと一緒にこの活動を盛り上げていきたいと取り組んでおります。
- 「ろう者の皆さんと一緒に盛り上げていく」とは、具体的にどのようなことでしょうか?
-
私はデフスポーツを紹介することはできますが、デフアスリートではありませんので、選手の皆さんが語る言葉のほうが説得力があります。そのため、デフリンピック関連のイベントでは、アスリートやスタッフも一緒に登壇していただき、多様なろう者の存在を知っていただく機会を増やしています。
例えば、アスリートはもちろん、「サインエール」という新しい応援スタイルを考案したスタッフの方々など、さまざまなろう者が登場することで、子どもたちに多様なロールモデルを紹介することができます。また、参加者の方々にも「ろう者」をひとくくりにせず、「いろいろな人がいるんだ」と感じていただけるのではないかと思っています。そうした出会いが、新たな関心や応援の気持ちへとつながっていくと信じています。
トルコのデフリンピックで見えた、世界のろう者のつながり
- アンバサダーに就任される前から、スポーツに関心はありましたか?
-
中学・高校の6年間ソフトテニス部に所属していました。大学ではスポーツはしておらず、主に学業に集中していましたが、その合間に大学のスポーツ部の試合やプロ野球、プロバスケの試合観戦に行っていたので、スポーツを観て楽しむことは好きです。
大学卒業後に帰国し、2017年にトルコで開催されたデフリンピックには、日本選手団のスタッフとして参加する機会をいただきました。
- 2017年トルコのサムスンデフリンピックへ、日本選手団のスタッフとして渡航したきっかけは?
-
もともと大学への留学経験があり、英語と国際手話の両方ができたことから、お声がけをいただいたのだと思います。私自身もその経験を活かして関われるのではと思い、ぜひ行きたいという気持ちから参加を決めました。
参加するにあたっては、世界のデフスポーツについても知識を深めたいと思い、勉強も始めました。例えば、「デフリンピックとは何か」「出場のための条件」「各競技の選考方法」「21競技それぞれの特徴や魅力」など、幅広く学びました。 - トルコのサムスンデフリンピックに参加して印象に残っていることや、驚いたことなどがあれば教えてください。
-
選手はもちろん、観客や関係者が世界中から集まっており、その中で特に印象に残っているのは、ろう者同士の情報交換の活発さです。
例えば「あなたの国にはろう学校はいくつあるの?」「就職先として多い職種は何?」「金メダルなど取ったら報奨はある?」といった、インターネットではなかなか得られないリアルな情報を、直接会って質問し合うんです。
そうした対話を通じて、他国の状況と自国を比較したり、良い事例があれば持ち帰って提案したりすることもできます。選手同士でも、「練習環境はどう?」「仕事の一部として練習しているの?」なども交わされていました。
デフリンピックは世界スポーツ大会であると同時に、ろう者の国際的な交流の場でもあり、多くの学びと気づきがあると感じました。
- なるほど…!そうした情報交換は、選手にとっても関係者にとっても非常に貴重なのですね。
-
本当にそう思います。例えば、日本では手話通訳士などの資格制度が整っていますが、まだ資格制度がない国もあります。ある国では、ろう協会が「この人は手話が上手」と判断すれば、資格がなくても通訳として活動できることもあるんです。
また、通訳者の派遣制度の有無や、通訳料を誰が負担するのかなど、国によって状況はさまざまです。そうした細かな違いを知ることも、新しい発見につながります。
それに、各国の手話の違いを学ぶのも面白いです。例えば、日本の「東京」や「京都」といった地名や、「ありがとう」の手話などを紹介したり、逆に他国の手話を教えてもらったりと、文化交流もありました。
ろう者の視点から伝える、“見て楽しむ”こと
- デフリンピック応援アンバサダーとして、どのように情報を発信していますか?また、伝える際に心がけていることがあれば教えてください。
-
さまざまな形で発信していますが、特に多いのは、デフリンピック啓発イベントへの登壇です。関東を中心に、全国各地で行われるイベントに参加しています。また、デフリンピック啓発がメインでない一般のイベントにも、積極的に参加しています。例えば、最近では聴者の陸上大会で、PRの時間をいただいてデフリンピックについて紹介をしました。そのほかにも、テレビ番組への出演、新聞やメディアの取材、小学校での出前授業など、さまざまな形で伝えています。小学校では「デフリンピックって何?」「手話って何?」というお話をしたり、実際に子どもたちに手話を教えたりもします。
まだまだ、社会には「障害者=かわいそう」「聞こえない=大変」といったイメージを持っている方が多いと感じます。なので、まずは「それは違うよ」と伝えることから始めています。「大変」「かわいそう」とされる状況は、聞こえない私たち自身に原因があるわけではなく、社会の仕組みや環境が、聞こえる人に合わせて作られていることから生まれているものです。そうした構造の中で、障害者やろう者が取り残されてしまっている現状がある。でも、それらのバリアは、工夫次第で取り除くことができ、対等に生きていくことが可能なんだということを伝えたいです。
スポーツの世界でも同じです。スタートの合図が音であっても、光に変えるなどの工夫で、ろう者も同じ条件で競技に参加できます。観客も、そうした工夫によって一緒に楽しむことができます。「聞こえなくてもできることはたくさんある」「聞こえないからこそ気づけること、楽しいこともたくさんある」「また違った世界、面白さも豊かさもある」私はろう者の自分を誇りに思っています。そんな思いや経験が、デフリンピックを通して、「聞こえないこと」や「障害」に対する見方を少しでも前向きに感じてもらえるきっかけになればと思い、日々活動をしています。
- 「聞こえない」ことを前向きに感じてほしいという思いで活動されているなかで、印象に残ったことありますか?
-
たくさんありますが、特に印象に残っているのは、小学校での出前授業のときの2つです。
1つ目は、授業の最後に感想を聞いたとき、小学生が
「聞こえないのは苦しくて大変だと思っていたけど、楽しいこともいっぱいあると知って驚きました」
と話してくれたことです。
また、手話も大切ですが、「話したい」「伝えたい」という気持ちが一番大切であること、ジェスチャーなどでもコミュニケーションがとれることも伝えているのですが、
「皆さん、楽しかったですか?」と聞いたときに、子どもたちが両手で大きな「○」を作って笑顔で答えてくれたことも、本当に嬉しい瞬間でした。
2つ目は、「好きな色は何?」と聞かれたこと。
一見、何気ない質問に思えるかもしれませんが、私にとっては「ろう者だから」というより、「川俣さんという1人の人として話したい」「もっと知りたい」という気持ちで接してくれたことが何より嬉しかったんです。その問いかけの中に対等な関わりの姿勢が伝わってきました。
- デフリンピック開催中はどのような活動をされる予定ですか?
-
実は、まだ詳細はわかっていないんです(笑)。すべての会場に行きたいと思っています。もし会場で私を見かけたら、ぜひ手をふったり、肩をたたいて声をかけてくれたりしたら嬉しいです〜!(笑顔)

提供:東京都
日本人選手が全競技に出場!デフスポーツの見どころと楽しみ方
- デフリンピック競技の中で、特に注目してほしいポイントはどこですか?
-
すべての競技をぜひ観ていただきたいです〜!
今回のデフリンピックでは、初めて21競技すべてに日本人選手が出場します!
過去の大会では、日本から選手が出場していなかった競技もあり、それがハンドボール、テコンドー、レスリング、射撃の4つです。
今回は、トライアウトを通じて新しい選手が多く発掘され、すべての競技に日本選手が出場することが決まりました!それらも含めて、ぜひ注目してもらいたいと思っています。デフスポーツは、基本的なルールは聴者のスポーツとほぼ同じですが、聞こえない選手が参加するためのさまざまな工夫がなされています。
例えば…- 陸上では、スタートの合図を音ではなくライト(スタートランプ)にする。
- 空手では、「止め」の合図は音声と共にランプの点灯。
- テコンドーでは、星野萌選手によると、『プムセ』と呼ばれる型を競う競技では、審判が選手の視界に入るように移動しながら合図を出す。
- バレーボールでは、審判が選手を呼ぶときはネットを揺らす。
- バトミントンの混合ダブルスでは、夫婦で選手としてご活躍している沼倉千紘選手から聞いた話によると、聞こえる選手は足音で後ろにいるペアの位置や打球音で打球の種類を判断しているが、沼倉選手の場合は、対戦相手の前衛選手の目線の方向から、後ろのペアの位置を判断したり、相手の構えるタイミングからペアが打つタイミングを予測したりするのだそう。視覚的な情報に置き換えている。
- 卓球では、亀澤理穂選手によると、卓球台の下やラケットで手話を隠しながらコミュニケーションを取ったり、逆に「向こうに打つよ」とわざと手話を見せて違う方向に打つフェイントを使うなど、視覚を利用した戦略もある。
- バスケットボールでもフォーメーションやサインを事前に確認・共有して、試合で活用する。
視覚で得る情報や工夫がとても多く、観ていて「なるほど!」と思う瞬間がたくさんあります。音の代わりに目で判断し、コミュニケーションやプレーの方法を工夫する。そういった違いや工夫を知ることで、スポーツの楽しみ方が広がると思います。
もちろん、初めての方や手話がわからない方も、選手の動きや表情、ジェスチャーからあふれる闘志がありますし、ルールがわからなくても、視覚的な情報だけでも十分に楽しめます!ほか、会場にも注目です!
- マラソンは、東京の中心部にある『KK線』という高速道路の廃線跡を活用し、ビル街を駆け抜けるという、これまでにない風景が見られる。
- オリエンテーリングは、壮大な自然の中で競うので、誰が一番早くゴールに着くのかドキドキワクワクが増す。
「耳ではなく目で観る」ことを意識すると、デフリンピックの魅力がぐっと深まります。
そしてもうひとつ、ぜひ注目していただきたいのが「サインエール」です。
これは、手話をベースとした新しい応援のかたちで、声が届かない選手たちに“見える応援”を届けようというものです。例えば、
- 両手をひらひらさせる「拍手」に「一生懸命/頑張れ」
頑張れー!という意味が込められています。 - 右手から「できる」+「勝つ」→左手「できる」+「勝つ」
大丈夫!勝つ!といった意味が込められています。
このように意味を込めた動きを加えて、一体感を持って応援できるように工夫されています。
日本は団結して応援する文化がありますし、こうした応援スタイルが世界にも広がっていくと嬉しいですね。開発には、ろうの俳優やアーティストの皆さんが集まり、シンプルで伝わりやすい動きを考案したそうです。
以下のホームページにも掲載されていますので、観客の皆さんにも覚えていただき、一緒に応援してもらえると嬉しいです!
Tokyo Foward 2025 デフアスリートに届ける新しい応援スタイル『サインエール』 | TOKYO FORWARD 2025 拍手。声援。応援歌。 応援に、音は欠かせない。 では、デフスポーツではどうだろう。 アスリートたちに、 その応援は届いているのだろうか。 『サインエール』 それは、...
デフアスリートに届ける新しい応援スタイル『サインエール』 | TOKYO FORWARD 2025 拍手。声援。応援歌。 応援に、音は欠かせない。 では、デフスポーツではどうだろう。 アスリートたちに、 その応援は届いているのだろうか。 『サインエール』 それは、...
私は、私。ありのままを大切にできる社会へ
- デフリンピックをきっかけに、どのような社会の変化を期待していますか?また、聞こえる人たちに「知ってほしいこと」「伝えたいこと」があれば、教えてください。
-
スポーツの世界でも、ろう者はマイノリティ、聴者はマジョリティという構図が続いています。
これまでは、聴者の大会にろう者が出場しようとすると、ピストルや音声による合図など音を基準にしたルールが多く、ろう者にとってはどうしても周囲の様子や音に集中するなどで、自分の力を思うように発揮しにくい現実がありました。その結果、対等な環境ではない中で「自分はダメなんだ」と感じたり、悩んだりすることもあります。
私自身も、聞こえる人が通う学校の部活動で、音声によるコミュニケーションにズレを感じたり、うまくいかなくて落ち込んだりした経験があります。しかし、デフリンピックのような「自分に合った環境」があれば、聞こえなくても思いきり力を発揮できる。環境を整備することで、誰もが対等に楽しめる、挑戦できる世界はつくれるのです。これはスポーツに限らず、学校、仕事、娯楽の場でも広がっていってほしいと思っています。
また、障害者少数派であることから、「対応はあとで考える」「予算に余裕があれば検討する」といった“後回し”が、残念ながら今も多くあります。でも、それは大きな間違いです。最初から一緒に考えていくことで、例えば初めはマイノリティの声だったとしても、結果的には社会全体にとって役に立つケースもたくさんあるのです。
例えば字幕。
最初は聞こえない人のために求められたものでしたが、今では多くの人が使っています。電車の中、赤ちゃんが寝ている家庭、日本語を学んでいる外国の方など、「音なしでも見える情報」として役立っています。分かりやすい例がスロープ。車いすや足が不自由な方だけでなく、ベビーカーや台車など、誰もが便利に使っていますよね。そういうふうに、聞こえない人のための“見える工夫”が、実はすべての人にとって新しい発見や利便性につながることがある。そのような新たな発見が、デフリンピックを通してたくさん生まれてほしいと願っています。
そして、デフリンピックは、私たちにとって『居場所』でもあるのです。その大切な場所を、これからも守り続けたいと思っています。
私自身、聴者に囲まれて育つ中で「聞こえない自分がいけないんだ」「聞こえない自分は好きになれない」と思っていた時期がありました。しかし、大学生になって、ろう者の仲間やロールモデルと出会い、デフリンピックの存在を知り、スタッフとして関わるようになって、環境が変われば、聞こえなくてもできることがたくさんあると実感しました。手話があることで、文化があることを知り、自分にとって新しい発見でもあり嬉しい発見でもありました。
聴者の世界、ろう者の世界、どちらも魅力的で大切な世界だと思っています。もしろう者の世界を無くして、聴者の世界だけを良しとする価値観だけになってしまえば、もう一方の世界の良さを見失い、自分らしさやアイデンティティーを見つけられなくなってしまいます。そうなれば、きっと今もろう者の自分に自信をもてず不安を抱えながらさまよっていただろう。
大事なのは、世界を分断するのではなく、それぞれの世界──例えば聴者、ろう者、盲ろう者、女性だったりと、それぞれの世界があって、自分にとって心地よい居場所から新しい世界を見るためには、自分も含め、それぞれの世界を尊重したうえで、いろいろな世界に行き来できるようにすること。そして、自分にとっての『心地よい居場所』があるからこそ、「私は私」「私はできる」と自信を持って他の世界とも、ありのままの私で関わることができます。
デフリンピックという場所は、私にとっても、多くの人にとっても大切な居場所。そこから新しい出会いや発見、交流が生まれ、お互いの違いを認め合うきっかけになると信じています。
観戦に訪れた人が、「自分と同じ聞こえない選手やスタッフがいる」「海外にもろう者の仲間がいる」と知ることで、「自分は聞こえなくてもいいんだ」「ありのままでいいんだ」と。本人だけでなく、家族や周囲の人も同じです。「かわいそうだから支える」ではなく、「対等にできる、楽しめる方法を一緒に考えていく」。そうした関わり方が広がっていく社会へと、デフリンピックをきっかけに目指していけたらと思います。
- 最後にデフリンピック開催に向けてのメッセージをお願いします。
-
デフリンピックが初めて開催されたのは1924年。2025年の東京大会は、ちょうど100周年という大きな節目となる大会になります!その記念すべき大会が、日本で開催されることを、とても誇りに思っています。
世界中から集まるトップレベルのデフアスリートたちが、真剣に競技に臨む姿、そして、「サインエール」での応援が会場全体をひとつにする様子。この大会は、きっと一生に一度の特別な機会になると思います。
ぜひ、会場に足を運んで、生の迫力と感動を体感してほしいです!
選手たちのかっこよさ、スタッフや関係者の支え、そして“見えるスポーツ”ならではの面白さをたくさんの人に感じてもらえたら嬉しいです!
「聞こえない=かわいそう」とされてしまう現状や、
社会の構造が聞こえる人に合わせてつくられていること──
それらは、私自身もずっと感じてきたことでした。
今回、川俣さんがそれを明確に言葉にしてくださったことで、
「まさにその通り」と深くうなずく自分がいました。
また、デフスポーツについては知らないことばかりで、たくさんの新しい発見がありました。
川俣さんの言葉に触れ、デフリンピックへの期待がますます膨らみました。
デフリンピック開幕まで、あと101日!
この大会が「終わり」ではなく、「始まり」となるように──。
川俣さんがこのような想いを胸に、デフリンピック応援アンバサダーとして活動されている姿は、とても意義深く、心から応援したいと感じました。
素敵なお話をありがとうございました!
そして明日、8月7日(木)は「デフリンピック100日前記念イベント」が開催されます!
川俣さんの想いにふれるこの機会、ぜひ足を運んでみてください✨