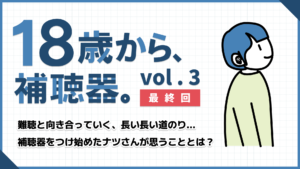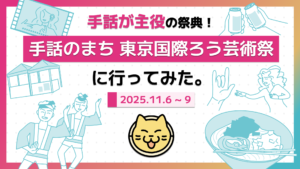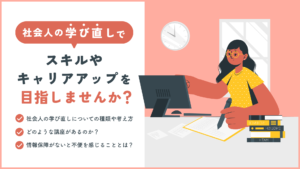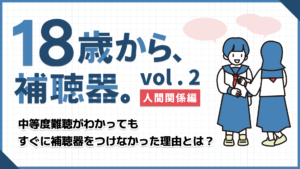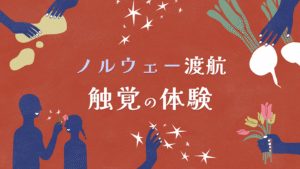皆さま、はじめまして!
このたび、キコニワでコラムを書かせていただくことになりました、まみねこです。
私は、生まれつき耳が聞こえません。
聞こえない世界で、私は何を感じ、どんなふうに生きてきたのか。
思春期の葛藤、学生生活、恋愛――
「聴こえない」ということと向き合いながら、悩み、考え、歩んできた人生を、このコラムで綴っていきます。
ここで私が伝えたいのは、「耳が聞こえない人を知ってほしい」「理解してほしい」ということではなく、ただ、触れて、感じてほしい・・ということです。
よろしければ、私というひとりのろう者の人生に、そっと触れてみてください。
もちろん、聴こえない人すべてが私と同じ道を歩んできたわけではありません。
これは、あくまでも「ひとつの人生の物語」として読んでいただけると嬉しいです。
さて、第一回目のテーマは 「母の涙と私のはじまり」。
母が私の聞こえないことに気づいた瞬間、そしてそのとき、母は何を思ったのか――。
どうぞ、最後まで読んでいただけると嬉しいです!
仮死状態で生まれた私
私の耳が聞こえないことが分かったのは、弟の泣き声だったと母は語っていた。
その前に――
私の誕生は決して順調なものではなかった。
私が生まれたのは、真夜中のことだったらしい。
体重は2000gほどの低体重児。さらに、仮死状態で生まれてきた。
母の体から取り上げられたとき、一切泣かなかった。
医師は私の足を持ち、逆さにしてお尻を叩いた。
その瞬間、ようやく産声をあげたという。
そしてしばらくの間、保育器の中で育てられた。
このようにして小さく生まれた私を、母は必死に育ててくれた。
それからしばらくして、年子の弟が生まれた。
母が感じた違和感
そんなある日、母は私たちを並べて寝かせていた。
掃除をしようと掃除機をかけると、弟はびっくりして泣き出した。
でも、私はピクリともせず、ただスヤスヤと眠っていた。
それを見て、母は「おかしい」と思ったという。
それまでも、
- 後ろから名前を呼んでも振り向かない。
- 手を叩いても、掃除機の音がしても、まるで気づかない。
そういうことが多々あったが、
「赤ちゃんってそんなものなのかな」
「深く寝てくれてありがたい」
「たまたまだろう、大きくなったら呼びかけに反応するようになるはず・・」
と思い込もうとしていた。
しかし、弟の反応とはっきり比べられたことで、それまで心のどこかで抱えていた違和感が、一気に大きな不安へと変わった。
“やはりおかしい・・・”
そう思うと、居ても立ってもいられなくなったという。
突然告げられた診断結果
その後、病院で聴力検査を受けた結果、医師は母にこう告げたという。
「この子は耳が聞こえません。治ることはありません。」
さらに、こう続けた。
「ろう学校という、耳が聞こえない子どもが行くところがあります。そこで話を聞いてみてください」
それを聞いた母は、うすうす感づいていながらも、まるで足元の地面が崩れ落ちるような感覚だったという。
誰にも頼れない、母の苦しみ
当時、母はまだ20歳だった。
周囲の反対を押し切って結婚し、自分の親やきょうだいに頼りにくい状態で私を産んだ。
さらに、当時の世間では、
- 手話という言葉すら知られておらず、
- 障害がある人は「かわいそうな存在」とされ、
- むしろ差別されるのが当たり前だった。
テレビでも、障害者を目にすることはほぼなかった。
そんな時代の中で、祖父母も私の将来を案じ、深く心配したという。
「この子はどうやって生きていくのか?」
「結婚できるのか、仕事はできるのか?」
母も、祖父母からそう聞かれるたびに、不安を募らせ、泣いてばかりいたという。
何よりも、一番心に刺さったのは――
「何も分からんのに、どうやって育てるつもりなんだ? 育てられるのか?」
という言葉だったと母は語っている。
※当時、女性は結婚が女の幸せだと教えられていた時代でした。
また、障害者が結婚できるイメージもなかったそうです。
当時のテレビでも、障害者=かわいそうな存在、世話をしてあげないといけない、お涙頂戴の存在として取り上げられており、それで祖父母は聞こえない私が幸せな結婚ができるのか?とそればかり心配していたといいます。
ろう学校で見つけた希望
その後、母は私をおんぶし、ろう学校へ話を聞きに行った。
そしてろう学校では、私に関するさまざまな検査が行われた。
そこで母は先生に何度も尋ねたという。
「治りますか?」
「この子はちゃんと大人になれますか?」
「(声で)話せるようになりますか?」
「私に育てられるでしょうか?」
不安が募り、母は涙をこらえきれなかったという。
しかし、先生は母にこう語った。
「ろう学校の生徒たちは、皆、元気に成長しています。」
「訓練をすれば、(声で)話せるようになる子もいますし、文字を書くこともできます。」
「ただし、お子さんと二人三脚で頑張ることが大切です。」
それを聞いた母は、少しだけ、私の将来に希望を持てたのかもしれない。
補聴器との出会い、そして新たな一歩
その後、先生から、
「まず病院で聴力検査を受け、その後補聴器センターで補聴器を作るように」と勧められた。
こうして、母と私の「ろう学校での生活」が始まった――。
※当時のろう学校の多くはどこも「声で話せるようになること」に重きを置いた教育でした。
また、当時は手話も広まっておらず、手話=猿真似と言われ、蔑まれていた時代でした。
そのため、母はまず何よりも「声で話せるかどうか」を第一に心配したそうです。
つづく…