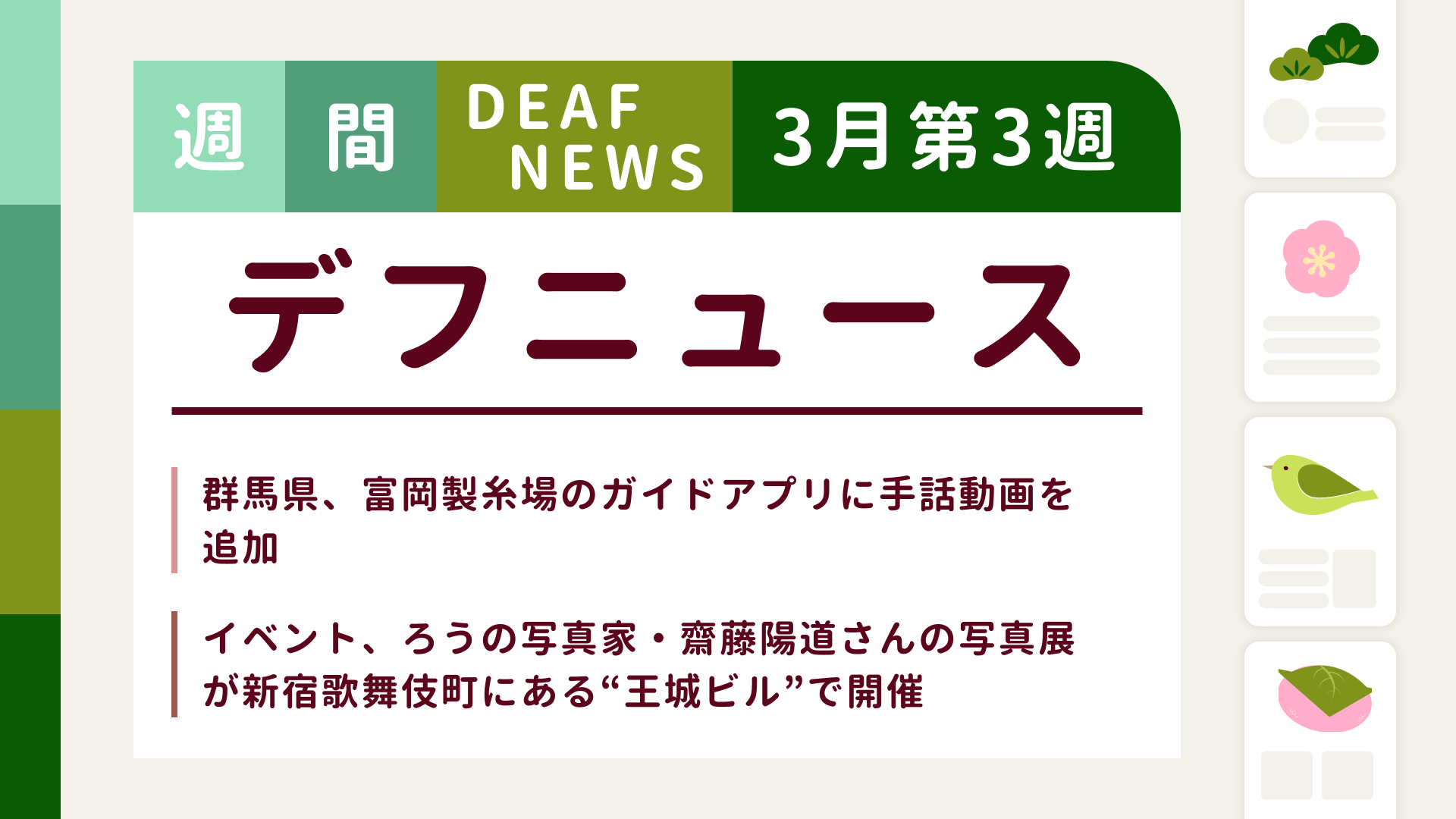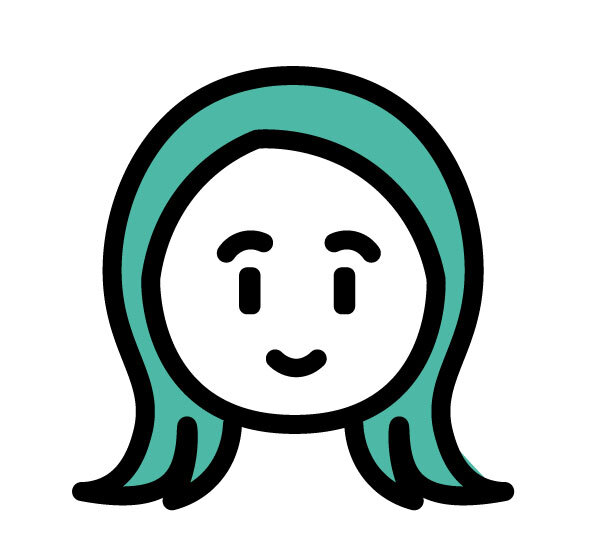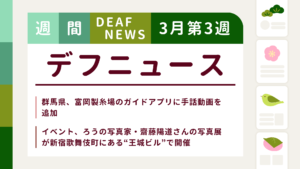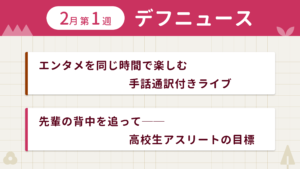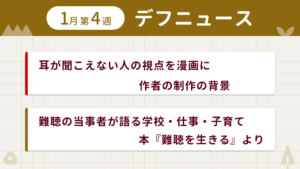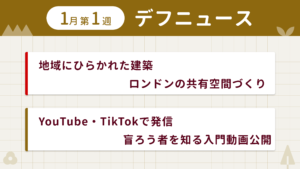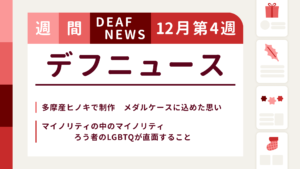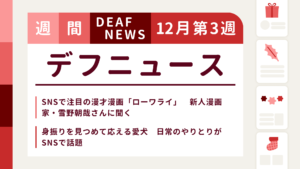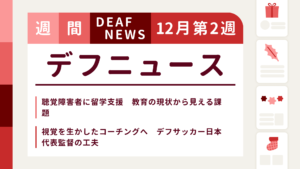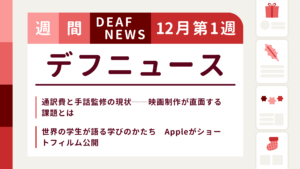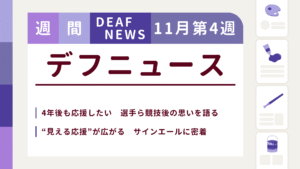皆さん、こんにちは!
先日は季節外れの雪に驚きましたね。暖かい日が続き、桜もそろそろ満開でしょうか。
さて、今週の週間ニュースは6つご紹介します!
群馬県、富岡製糸場のガイドアプリに手話動画を追加
群馬県富岡市は、富岡製糸場の音声ガイドアプリに手話動画を追加し、手話ガイドが約20カ所を紹介しています。これにより、事前予約必要なしで聴覚障害者がいつでも見学できるようになりました。


富岡製糸場では、手話による解説がいつでも見られるようになり、アクセスも便利になりましたね!「実際の手話ガイドの解説を受けたいから予約する」「近くにあったので立ち寄ってみた」など、ニーズに応じた選択肢があると、訪れる機会も増えますね!
イベント、ろうの写真家・齋藤陽道さんの写真展が新宿歌舞伎町にある”王城ビル”で開催
2025年3月27日〜30日まで新宿・歌舞伎町の”王城ビル”で、ろうの写真家・齋藤陽道さんの写真展「神話7年目━━人間が始まる」が開催されます。大自然の中で子どもたちを捉えた「神話」シリーズの集大成です。写真を通して、未来へと続く「神話」を描いています。


写真展だけでなく、染物ワークショップも開催されるそうです。残席数などの詳細を確認のうえ、ぜひ足を運んでみてください!
「めめ菓子工房」の店主・伊藤さんに取材した著者の視点や思い
横浜市青葉区にオープンした「めめ菓子工房」の店主・伊藤ホサナさんに筆談で取材を行いました。店名の由来やお菓子へのこだわりを伺い、手話を活かした唯一無二のお菓子店として、多くの人に親しまれています。


『日常生活の中でなじみ、「ろう者と聴者」ではなくて、「おいしいお菓子を作る人と食べたい人」という関係性で』という言葉がステキだなと思いました。
鑑賞サポートの取り組み、すべての人が芸術文化にアクセスできる環境を目指して
東京都は、誰もが芸術文化に触れられる環境整備を推進しています。芸術のアクセシビリティーの向上を目指して、助成制度「東京芸術文化鑑賞サポート助成」により、手話通訳付きや字幕・音声ガイドの提供をしようと普及活動しています。


鑑賞サポートに関する話を見る機会がなく、初めて知ることもありました。例えば、手話通訳者や芸術に関わる関係者のそれぞれの思い、「助成を受けるにはアクセシビリティー講座の受講が条件」などです。この鑑賞サポートが東京だけでなく、全国に広がることを願っています。
難聴の若者が抱える生きづらさとは?
NHK「#ろうなん3月号」では、若い難聴者の生きづらさをテーマに、耳鼻科医の片岡祐子氏とNPO法人「みみトモ。ランド」代表の高野恵利那氏を迎え、悩みや支援についてお話をしました。仕事の接客では、お互いに円滑なコミュニケーションができるように取り組んでいます。


私も中学や高校の頃、「コミュニケーションの取り方」が分からず、人との関わりが辛いと感じることがありました。接客などの職場では、聞こえの異なる社員に合わせたコミュニケーションの工夫は大切ですね。このような理解が広がることを願っています。
沖縄県、「手話フェスティバル」で日本とイギリスとの違いを紹介
石垣島で「手話フェスティバルin石垣」が開催されました。講演では、NHK手話ニュースキャスターの那須英彰さんと映画監督兼カメラマンのサミュエル・アッシュさんが、日英の手話や公的支援の違いを紹介しました。大会を主催した県聴覚障害者協会は、誰もが意思疎通できる社会を目指し活動を続けると語りました。


とても興味深い講演内容ですね!日本では、聴覚障害者向けの公的支援がいくつかあり、その中のひとつが意思疎通支援制度(手話通訳・要約筆記)です。利用範囲などは自治体によって異なりますが、海外ではどのような支援があるのでしょうか。日本との違いを知ると、新たな視点が得られそうですね。
いかがでしたか?
私は、NHKの記事「若い難聴者のコミュニティー「みみトモ。ランド」と、職場での工夫」に興味を持ちました。
全く聞こえない私も、かつては読唇でコミュニケーションを取っていたので、複数人の友達との会話で最初は理解できていても、話が盛り上がるにつれてついていけなくなることがよくありました。この記事には本当に共感することばかりです。
「みみトモ。ランド」は、悩みなどを語る場としての役割を担っており、難聴者が心から安心して話せることはとても大切だと感じます。
アパレルショップでは、難聴の社員との円滑なコミュニケーションのための工夫がされており、文字起こしアプリだけでなく、指さしボードも取り入れるとのこと。素晴らしい取り組みだと思います。安心感や働きやすさにつながっていますね!
それでは、素敵な週末をお過ごしください